
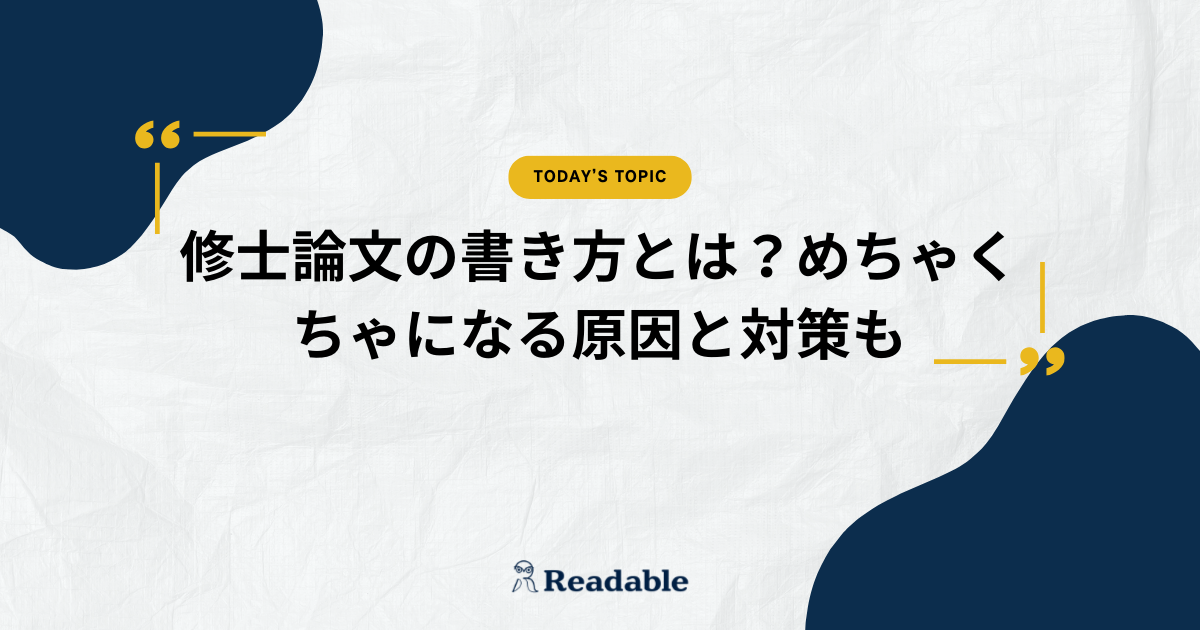
修士論文は、修士課程を終了する際には必須となる論文です。
修士論文が完成していなければ、修士課程や博士前期課程としての終了が見込めず、そのまま留年となることも考えられます。このように大事な修士論文ですが、ときにめちゃくちゃになることがあります。このようにならないためには、どのようにしたらよいでしょうか。
本記事では、修士課程で執筆することになる修士論文の書き方について、論文がめちゃくちゃにならない対策まで解説します。
目次
修士論文は、修士課程を終了する際には必須となる論文です。
論文とは、研究対象に関して、これまでの実験結果を明らかにして、自身の考え方や見解を示すと共に、それに基づいた研究成果をもとに、その考え方の内容の妥当性を、論文として表現するものです。修士論文でも同様に、修士課程で実施した自身の研究成果を、論文として発表することが大切です。
もし修士課程や博士前期課程を終了して、博士後期課程にすすむ場合は、その前段となる研究成果を2年間限定でまとめることが必要です。博士前期課程を終了して、企業などに就職する場合でも、短期間での成果を大学内外に公開することになります。このような短期間限定といえるのが、修士論文の特徴ともいえます。
また本コラムでも紹介しているように、論文作成には新規性が必要となります。たとえば、学術雑誌に論文を発表することは、研究者にとって重要な作業といえるでしょう。研究を開始して間もない人や、経験豊富な研究者にとっても、研究者としては論文発表を行う作業自体が大切なプロセスとなります。学術論文などとはレベルは違いますが、新規性や当該分野における有用性が必要となります。
修士論文の場合は、あたりまえですが、論文作成者が、ほぼ初めての本格的な論文となることです。論文としての新規性追及と、修士課程での教育というふたつの側面がうまく機能していることが、良い修士論文を作成するためには大切です。
多くの場合、修士号の取得のためには修士論文が必要となります。修士課程の修了にあたって必要な単位数を修得し、修士論文の審査と口頭試問に合格すれば晴れて修士号を取得できます。このように通常の学術論文とは異なり、教育面も重視されているのが修士論文なのです。
それでは修士論文がめちゃくちゃになる原因とは、どのようなものが考えられるでしょうか。
修士論文がめちゃくちゃとは、論文の内容が一定の水準に達していないことです。修士課程を完了できる一定の水準といえる、論文の内容が必要となります。
研究にそもそも熱心に取り組んでいなかったり、あるいは先年度に国内でも多大な社会的影響を与えたコロナ渦などで、思うように実験できなかったことなどもあったりするのではないでしょうか。特に研究成果が十分にない場合は、修士論文を完成させるのが難しくなります。このように自身の原因か、外部環境によるものかにかかわらず、いろいろな状況が論文作成に影響するのは否めません。いわゆる、修士論文がめちゃくちゃとなることもあるかもしれません。
博士後期課程に進学する、あるいはできそうな場合は、後期課程でなんらかの研究リカバーも期待できますが、修士の場合はそうも行きません。留年する人がいないわけではないですが、たいがい2年間という、研究期間が限定されているという制約がまずつきまといます。
修士論文がめちゃくちゃにならないためには、まず修士課程での研究と教育がうまく実行されていることが大切です。自身が受ける教育的な側面と、自身自体の成果の側面、努力といってもいいかもしれませんが、このふたつの側面がバランスよく保たれていなければなりません。
次に、めちゃくちゃにならないための修士論文の書き方についても説明します。
まず、文科系や理科系でも実験を伴わない修士課程での研究について考えてみます。
修士論文の研究テーマを決定するときは、批判的思考が大切です。既存の研究結果や研究常識への反論などを見出すことで新しい示唆を生み、意義のある研究テーマが出来上がります。
さらに論文の質を高めるには、論理的な構成で執筆することが重要です。論理的な構成に仕上げるには、あとで述べるアウトライン作成法などによる、フレームワークを意識するとよいでしょう。
論文の執筆において、研究の信頼性を確保するには、当該分野に精通するとともに、テーマに即した文献を用いることが重要です。単にアブストラクトを集めるだけではなく、文献を詳細に読むことで、研究背景を深く理解し、研究問題を明確に設定できるようになります。また、先行研究と自分の研究を比較し、自分の研究の位置付けや新規性を明示することも必要です。
参考:「論文の読み方を理解しよう!研究に役立つ、読み方のコツについても解説」
実験が主体となる理科系の修士課程においては、卒業研究とはレベルの違う、はじめての本格的な研究生活をおくることになります。このため研究背景の理解などと平行して、実験研究をできるだけ遂行しておくことが必要です。
今は問題があると思いますが、朝から晩まで研究室で過ごすぐらいでないと、2年間という短期間ですので、具体的な研究成果は望めないかもしれません(当方も修士課程を終了して企業に入る前の、この2年間が一番実験に没頭していたような気がします)。もちろんコロナ渦等で、大学への出入りが禁止されていたなどの事情がある場合もあり、不可抗力で研究の進展が遅いときもあります。ただこのような場合は、修士課程を運営している大学側からも、教育的な側面としてなんらかの救済策があるはずです。
文科系でも理科系でも、修士論文作成の前に、自身の研究的側面を充実させておく必要があります。
このような自身の研究成果をまとめて、さらに修士課程終了条件をクリアーするためのものが修士論文となります。
修士論文の作成・提出方法ですが、同じ大学でも学部や各研究室で異なる可能性があります。このため、所属する各研究室の指導教官の指示に従うのがよいでしょう。
また文科系と理科系では、先ほどとも関連しますが、事前準備の期間に違いがあります。通常理科系では、自身の実験結果のみを包含したものになるので、修士課程入学後できるだけ早く実験を開始することになります。たいてい複数名が同じ研究室に在籍することになるので、入学時に指導教官から当該研究室で実施する研究テーマ候補が、複数提示されることも多くなっています。この中から自身がどうしても実施したいと思うテーマを研究することになります。もちろん学士のときから、同じ研究室の場合はすでに当該分野にもある程度精通しているので、自身でもテーマ設定できることもあります。
このため論文作成の準備期間も、実験開始からはじまっていると考えるべきです。できた修士論文は大概の場合、指導教官の事前チェックがあります。なお指導教官も多数の学生を指導している場合もあり、その場合は時間がなかなか取れません。場合によっては、複数回のチェックや修正があるときもあります。このため、終了年度にはいったら、できれば早めに指導教官のアドバイスにしたがうことが得策です。
古くなりますが、ここでは筆者が作成した修士論文の構成例とその経緯を紹介します。
下記のような研究名称で、原稿用紙に直接記載(PCなしの時代)にて、合計用紙109ページとなっています。用紙1枚400字ですので、約4万文字程度であり、それほど多くはありません。最低8万文字以上というような大学もあるようですが内容が問題であり、文字数だけ多ければ良いというものでは本来はないと思います。
大学の博士前期課程(修士課程のこと)にて作成したもので、修士論文としてこれが作成されていないと、同大学の博士前期課程は終了したとは見なされませんでした。同期が4名で筆者を含む3名は修論作成後、企業にそれぞれ就職しております。なお、同期の学生1名が博士後期課程に進学となっています(この1名は博士号も同大学にて受領後、ある大学の助手(助教)となりました)。
筆者は実は、学部は別の大学を卒業(卒業論文もそこで)しており、同じバイオ分野とはいえ、綿栓(試験管にふたをする培養用のもの)の作り方から全く違うので、一から指導してもらったものです。このため、あらたな実験遂行というより当初はいわば丁稚のような研究生活でした。なお卒業論文とはいえ、原稿用紙10頁程度で卒業しているので、修論と卒論は全然違うものだなあ、と当時は感じたものです。企業に就職後、結果的に論文博士号受領のため、さらに別の大学で博士論文も作成しました。博士論文では英文記載を指定されていたこともあり、研究成果達成以外にも、執筆作業に相当手間取った経験があります。
なお当方の修士論文成果の一部は、大学の指導教官により、後日学術論文としてまとめて頂き、固定化酵素関連の海外学術誌にも掲載されました。もちろんファーストオーサーは、指導教官の先生ですが、セカンドオーサーとして当方の名前を、はじめて海外学術誌に記載してもらえることになったという、当方にとってはありがたい経緯もありました。
参考:「ファーストオーサーとは?選定から論文著者との関係、研究不正時の責任まで解説」
タイトル:〇〇の調整と◇◇製造への利用
序論:
1.本研究の目的とその背景
2.◇◇製造への〇〇酵素の利用に関する既往の基礎的研究
本論:
・実験方法
1.材料
2.方法
・実験結果
1.〇〇酵素の固定化法の検討
2.各種〇〇酵素の固定化収率
3.固定化〇〇の諸性質
4.固定化〇〇による連続酵素反応
5.固定化〇〇を用いた◇◇の製造
・考察
1.〇〇の固定化
2.固定化〇〇の性質
3.連続酵素反応における立ち上がり現象について
4.反応器の連続酵素反応に対する影響
5.固定化〇〇による◇◇の製造
6.◇◇熟成に関する〇〇酵素の寄与
要約:
謝辞:
文献:
ここでは修士論文作成時のポイントと注意点についても、まとめておきます。
修士論文は、なるべく教官や他の読者にもわかりやすく書くことが大切です。
とかく文字数頼みで内容は二の次でもよいという風潮が、修士論文作成にあたってないわけではありませんが、内容重視で論文作成をする方が、あとあと役に立ちます。もちろん最低限の文字数はクリアーしてからですが。企業などでは、できるだけ少ない文字数で内容を精緻にするという手法もあります。なお学術論文なら、文字数が多い方がよいと思われがちですが、少なくとも有名学術雑誌になるほど冗長な文章はきらわれ、論文審査にも大きく影響します。
また特にはじめての人にとって、修士論文の研究背景部分を書くのは、実はかなり難しいことです。それなりの文章を書くためには、その分野の十分な知識が必要とされるからです。また先行研究に対して、自分の主張を出す場合は、必ずどこまでが先行研究での主張で、どこからが自分の主張なのかをはっきりと区別することも必要です。先行研究の内容をそのまま取り入れるのではなく、場合によっては、批判的に検討することも必要となります。修士論文作成に利用するには、先行研究の内容をただまとめただけでは、論文にはなりません。
この辺が難しいところですが、その領域の専門家になれば、うまく解説できるようになります。複数の先行研究経験から来るもので、学生ではまだ理論的な検索の仕方が身についていなかったり、実際に触れている具体的な研究例が少ないためです。ただこの時期の経験は、研究者となっても貴重な経験ともいえ、しっかりと修士論文を書くようにしましょう。研究者でなくとも、社会にでれば、いろいろな課題や問題があり、それらに対して、自身の回答が求められる場合があります。修士課程終了のみを目的とするのではなく、適切な修士論文作成法をマスターしておけば、のちのち役に立ちます。
たとえば先ほどの当方の修士論文ですが、〇〇酵素の固定化法の検討などは、当然、実験結果の範疇に入ります。これに対して、連続酵素反応における立ち上がり現象や、反応器の連続酵素反応に対する影響、などは考察の部分で紹介した方がよいこともあります。なぜなら、連続反応カラムを利用する実験では、反応開始時の「立ち上がり現象」などは、いわゆる「反応工学」の分野の課題(といっても現在ではなく、その当時の課題)となっている普遍的な問題だったからです。
このような普遍的な課題でも、当該分野の研究初心者では気づかないこともかなりあります。このような研究初心者に対する教育的な側面もかなり大切で、むしろこのようなことが大学教育においては重要です。
まず論文作成に取り掛かる前に、文科系では、自身の研究テーマに関する文献や資料を収集して、あらかじめ読み込んでおく必要があります。
理科系でも、実験だけをするわけではなく、たいてい毎週、研究室などで、重要な研究論文の紹介や購読会なども実施されます。このような場も利用して、自分の実験研究の背景となる関連資料は読み込んでおきます。文科系、理科系ともに、関連研究や最先端の研究成果などの論文を過不足なく収集し、読み込むことが大切です。
執筆原稿の確認は大切で、自身での確認後、できれば指導教官や他の研究者にもみてもらうようにします。自分ではなかなか気づかない癖とか、言い回し表現などもあります。
仮につけておいたタイトルと抄録は、論文完成後にも最終の修正や調整をおこないます。いきなり修士論文の執筆にとりかかるのではなく、まず論文アウトラインを設定してから取り掛かるようにします。これは修士論文だけでなく、学術論文などさらに高度な論文を作成するときも同様です。
アウトライン作成のメリットですが、設計図ができるということと、研究指導が容易になる、という利点があります。アウトラインは、論文作成のための設計図の役割も果たしています。いきなり論文作成を開始すると、完成した論文が本人が最初に意図していたものと異なる可能性が多分にあります。もちろん、頭の中で熟考することも大切ですが、やはり実際に箇条書きで記載してみるメリットは十分にあります。
論文作成にあたり、もし研究室で研究指導を受けている場合などは、指導教官や研究助言者などに、あらかじめ見せて意見や指導をもらうことも可能となります。特に、研究を開始して間もない人ほど、このような機会を得ることが重要です。貴重な指導をしてもらえる機会を活かすためにも、まず論文アウトラインを作っておくことをおすすめします。
参考:「研究論文のアウトラインとは?研究に役立つアウトラインの構成から書き方まで解説」
はじめて執筆することになる修士論文の書き方と、修士論文作成がうまくいかない原因まで、詳細に解説しました。
修士論文は、修士課程を終了する際には必須となる論文です。
論文作成の主な目的は、学生が研究分野の既存の知識に基づいて、さらに論理的推論が実施できることを証明することにあります。最近は、ChatGPTなどによる文章作成もありますが、深層学習をまねて発達してきたAIではまだ及ぶことが少ない分野となります。このようなやり方で作成された論文を見抜くことも大学では、今後必要とされるかもしれません。当方も深層学習法によるバイオ研究に一部関与した経験がありますが、もしもAIで論文作成することになれば、いつまでたっても自身の能力は発展できないことになります。
本記事が、修士論文をはじめて作成(というのは通常、修士論文は大半の人がはじめて作成するわけです)するみなさまのお役に立てば幸いです。

研究や論文執筆にはたくさんの英語論文を読む必要がありますが、英語の苦手な方にとっては大変な作業ですよね。
そんな時に役立つのが、PDFをそのまま翻訳してくれるサービス「Readable」です。
Readableは、PDFのレイアウトを崩さずに翻訳することができるので、図表や数式も見やすいまま理解することができます。
翻訳スピードも速く、約30秒でファイルの翻訳が完了。しかも、翻訳前と翻訳後のファイルを並べて表示できるので、英語の表現と日本語訳を比較しながら読み進められます。
「専門外の論文を読むのに便利」「文章の多い論文を読む際に重宝している」と、研究者や学生から高い評価を得ています。
Readableを使えば、英語論文読みのハードルが下がり、研究効率が格段にアップ。今なら1週間の無料トライアルを実施中です。 研究に役立つReadableを、ぜひ一度お試しください!
Readable公式ページから無料で試してみる
都内国立大学にて、研究・産学連携コーディネーターを9年間にわたり担当。
大学の知財関連の研究支援を担当し、特にバイオ関連技術(有機化学から微生物、植物、バイオ医薬品など広範囲に担当)について、国内外多数の特許出願を支援した。大学の先生や関連企業によりそった研究評価をモットーとして、研究計画の構成から始まり、研究論文や公募研究への展開などを担当した。また日本医療研究開発機構AMEDや科学技術振興機構JSTやNEDOなどの各種大型公募研究を獲得している。
名古屋大学大学院(食品工業化学専攻)終了後、大手食品メーカーにて31年間勤務した経験もあり、自身の専門範囲である発酵・培養技術において、国家資格の技術士(生物工学)資格を取得している。国産初の大規模バイオエタノール工場の基本設計などの経験もあり、バイオ分野の研究・技術開発を得意としている。
学位・資格
博士(生物科学):筑波大学にて1994年取得
技術士(生物工学部門);1996年取得