
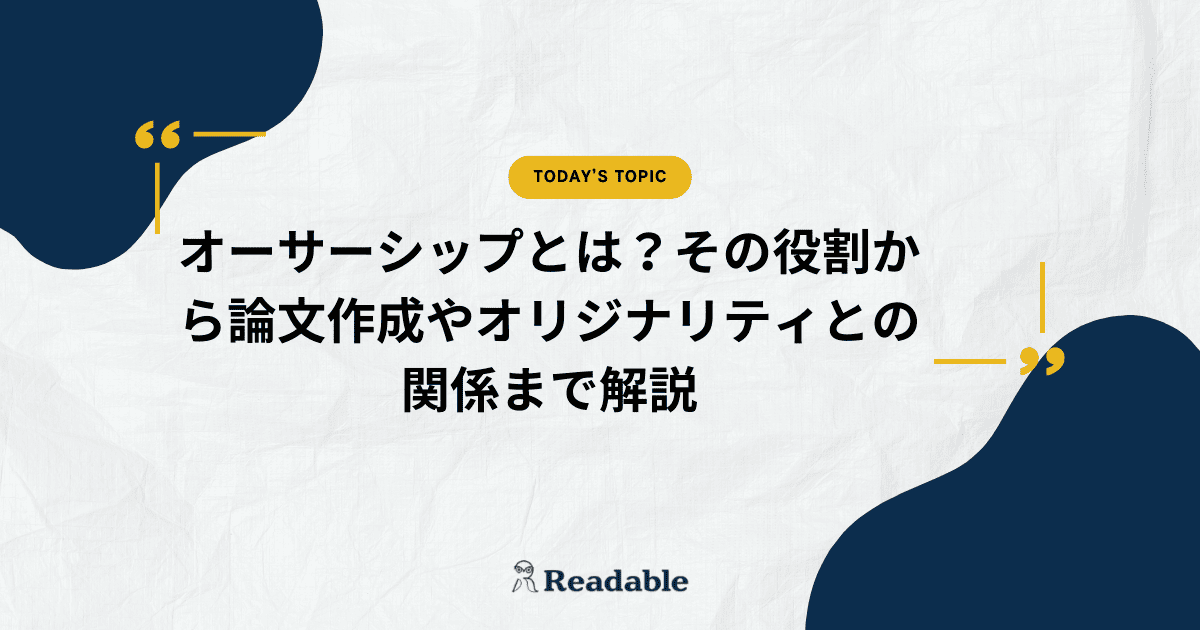
オーサーシップは、研究者が研究論文を書く場合には、避けて通れない概念です。
学術論文などの研究成果を記載するときには、論文の著者であるオーサー全員が関与することになります。
このオーサーシップには、論文を作成するという権限とともに、論文に対する責任という両方が存在しています。
本記事では、オーサーシップについて、その本来の役割から論文作成やオリジナリティとの関係まで解説します。
目次

オーサーシップ(authorship)とは、研究論文に記載されている研究内容について、責任を負うオーサー(author)として関与するとともに、名前を明記することを指しています。
より簡単にいえば、学術論文などの研究論文の著者リストに、当該研究者名を掲載することをオーサーシップともいえます。またオーサーシップでは、当該研究への貢献を認めるいわば権限付与の行為であるとともに、当該研究に対する責任を伴うものでもあるのです。
研究に対する権限と責任とは、当該研究全体にわたるもので、研究計画時、研究遂行時、論文作成時のすべてを包含しています。また論文作成後には、場合によっては、論文査読対応や研究公正に関する、いろいろな諸問題についても、広く対応しなければなりません。
次の項目で記載しますが、オーサーには、ファーストオーサー、セカンドオーサーやそれ以外の研究者など、その権限と責任の濃淡があります。但し、オーサーシップとして記載されたいずれのオーサーには、なんらかの責任と権限があるといえます。
国際医学雑誌編集者委員会(ICMJE)が定めた、オーサーシップに関するガイドラインには、「著者と指定された者は、すべて著者としての資格を有し、著者としての資格を有する者はすべて列記すべきである」と記載されています。また著者として認められるには、以下の4つの基準をすべて満たす必要があります。
■ 研究の着想と企画、データの取得、分析、解釈に実質的な貢献をしている。
■ 知的なコンテンツに関する記事を執筆または改定している。
■ 仕事のいずれかの部分の正確性、または完全性に関して、仕事のすべての面で説明責任を有することへの合意。
■ 最終版を承認している。
引用元:https://researcheracademy.elsevier.com/uploads/2018-02/2017_ETHICS_JPN_AUTH03.pdf

研究論文に著者名が記載されることにより、研究者それぞれが著者として認められると共に、研究の責任を負うことになります。
医学分野になりますが、オーサーシップに関する、一般的なガイドラインも紹介されています(International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)によるガイドライン:研究分野によって異なる場合あり)。
■ 著者の順序は、「共著者の共同決定」とする。
■ 研究に関与したが、ジャーナルの著者基準を満たさない者は、「Contributors(貢献者)」または「Acknowl-edged Individuals(定評のある人々)」として列記する。これには、助言によって研究を助けた人、研究場所を提供した 人、学部の監督者、経済的支援を獲得した人などが含まれる。
■ (医療分野等における)複数の拠点にわたる大規模な治験の場合は、一般に医師とセンターのリストを公開し、各貢献についての説明を添える。グループによっては、著者をアルファベット順に列記し、すべての著者が研究と発表に均等に貢献したという説明を添える場合もある。
引用元:https://researcheracademy.elsevier.com/uploads/2018-02/2017_ETHICS_JPN_AUTH03.pdf
オーサーシップでは、著者とは研究に多大な知的貢献をした研究者です。
リストに掲載される研究者の中で、第一に記載される著者はファーストオーサーとよばれます。論文完成に最も中心的な役割を果たした著者であり、当該論文に最大の新規性や有用性を付与し、さらには学術的な貢献をした人となります。
研究完成後の執筆作業では、セカンドオーサーなどの共著者のサポートを受けることもありますが、まず当該研究の遂行と実施に責任を持たなければなりません。また研究実施にあたっても、データの取得と分析、さらには最終原稿の執筆においても、最大の責任を負うことになります。
なお新規性や有用性の観点は、実は特許申請時の必要最低条件とも合致しており、研究論文の著者がそのまま関連の特許申請をおこなうこともあります。とくに著名な学術誌に投稿するような最先端の研究論文では、最近は、論文投稿と特許申請は平行して実行されています。
当方が勤務していた大学でも、一部の論文ではありますが学術誌への投稿と特許申請は、ほぼ同時並行で行われていました。このあたりの事情は、アジア各国でも日本より進んでいる国がかなりあります。
一時期、シンガポールの公的研究機関との共同研究を実施したのですが、有用な成果が出れば、先方は必ず特許申請をするという、共同研究契約となっていました。こちらが共同特許申請に合意しない場合は、先方だけで出願実施するということになります。
もちろん、発明者には国内大学の先生は入っていますが、いわゆる「共同出願人」ではないので、特許技術の権利は、国内大学側では行使できません(この案件は、その後共同出願されています)。このように、国内以上にファーストオーサーの権利を重視しているところが、アジア各国には複数存在しています。
ときに学術研究の世界での「著者」は、著者以上の意味を持ちます。特許出願も同等な権利のひとつともいえます。先ほどの例は、国内大学での共同研究論文ですが、国内企業でも先端研究を実施している企業ほど、学術論文の投稿以上に、特許出願を重視しています。
場合によっては、特許出願の方が先で、論文投稿や詳細なノウハウは保持しておく傾向のある企業も多くなっています。もちろん著名学術誌になるほど、最先端の成果には「新規性」が要求されるので、同時申請などを検討することも必要です。
多くの著名学術誌では、オーサーシップを定義する際にInternational Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)によるガイドラインに従っています。オーサーシップを実行するために、論文投稿の際には、以下の4つの過程全てに参加している必要があるとしています。
◆研究設計、データ収集および分析への多大な寄与
◆知的側面から重要な内容の執筆および修正
◆論文投稿前の最終検討および承認
◆研究の正確性や信憑性をしっかりと検討し、問題がないことを保障するために「研究に関する全ての面」で責任を持つことに対する合意
とくにファーストオーサーは、これらのすべての過程について責任を持つことが求められます。
セカンドオーサーともよばれる第二著者は、ファーストオーサーの次に、当該論文に実際の貢献度が高かった著者となります。
セカンドオーサーでは、研究計画を一緒に立てたり、当該の実験やデータ分析を共同で行ったりした人を記載します。場合によっては、博士課程の共同研究者を記載することもあり、第二著者も当然ながら、たとえば博士論文などにも貢献する研究実績となります。
セカンドオーサー以外でも、研究論文の著者リストに記載されている研究者では、先ほど記載した4条件になんらかの関与が求められています。
たとえば、当該研究論文がファーストオーサーで最終的に作成された場合でも、セカンドオーサーや他の著者も、登校前の論文を丁寧に検討して、誤りがあれば訂正しておかなければなりません。オーサーシップとは、単に自分の名前が記載されてよかったというものではなく、このような過程への責任と貢献などすべてを含むものといえます。
なお共同ファーストオーサーがいる場合もあり、この場合どちらかが第二著者ということになります。複数の融合分野を必要とするプロジェクトでよく見られ、研究者それぞれの貢献度は、研究論文の当該分野にも関連します。
たとえば新薬の開発に関する新規論文を開発したとき、ある部分では高分子化学などの基礎的分野の研究者が、新規化合物を作成し実験をするとともに、病院などで臨床研究によりその効果をあきらかにするなどといった研究論文は多くなっています。
このような場合、論文が複数作成されるときもあり、開発が初期段階の論文ですと、基礎的分野のファーストオーサーが、臨床段階の論文ですと医学部系オーサーが、それぞれ第一著者として、論文に記載される場合もあります。もちろん基礎的分野の著者が引き続き、第一著者を務めることもあり、成文化されているものではありません。
先ほども紹介しましたが、ICMJEではオーサーと認められない場合についても記載しています。
「研究に関与したが、ジャーナルの著者基準を満たさない者は、「Contributors(貢献者)」または「Acknowl-edged Individuals(定評のある人々)」として列記する。これには、助言によって研究を助けた人、研究場所を提供した 人、学部の監督者、経済的支援を獲得した人などが含まれる。」
オーサーとなる条件を満たしていない場合、謝辞の部分にその研究者の名前を記載します。オーサーとして記載するのと謝辞への記載を分けることにより、その研究に関して全面的な責任を負うオーサーとを区別することになります。
研究の一部にのみ参加した研究者などは、論文全体に対する責任を負うことはできません。このような、いわゆるゴーストオーサーやゲストオーサーは、当該研究のオーサーとは認められていません。

それではオーサーシップの役割とは、具体的にはどのようなものでしょうか。
ここでは、とくに重要な役割をおこなうファーストオーサーによるオーサーシップについて考えてみます。具体的には、研究計画時、研究遂行時と論文作成時の段階について解説します。
まず研究計画策定におけるオーサーシップの役割があります。
オーサーシップの中でもとくに重要な貢献と責任を持つのはファーストオーサー、またはその候補者です。研究終了時には、研究成果によりファーストオーサーが確定しますが、最初から候補者が決まっていたり、暗黙の了解などがある場合もあります。
ファーストオーサーは、研究論文の内容に対して重要な貢献をしており、まず当該の研究全体に対して、積極的に関与していなければなりません。また重要な構成要素となる研究全体の準備・検討・実施・分析などのそれぞれのプロセスに携わっていることも求められます。
単に論文執筆段階における論文作成のプロセスだけではなく、当該研究実施段階からの関与、というより研究計画の主導的プロセスが大切です。もちろんセカンドオーサーやそれ以外のオーサーとも、共同検討による研究計画の設定を実施しなければなりません。
このようなオーサー全体によるオーサーシップが、いわば理想の姿ともいえます。オーサーシップとは、論文執筆の論文作成段階だけではなく、すべてのプロセスで実施される必要があります。
研究計画、あるいはその前の段階の研究目標に対しても、知的な貢献をしなければなりません。当該研究で目標とするのはなにか、しっかりと検討しておく必要があります。
ときにはリサーチクエスチョンなどの手法を使用することも有効です。リサーチクエスチョンとは、研究計画設定の前の研究タイトルを策定することで、オーサーシップを発揮することにもつながります。
参考「リサーチクエスチョンとは?特徴・種類や作り方を紹介」:
リサーチクエスチョンを立てる場合、まずテーマの分野を選定することが大切です。研究者の場合、たいていは自身の専門分野から取り掛かることになります。
全くあたらしい分野の研究に取り組む場合は、その分野の研究者などの協力も得て、リサーチクエスチョンを作ることになります。また以前の分野からの研究経験が、あたらしい分野の理解に役立つこともあります。
たとえば有機素材分野の開発で、物理分野の研究者の視点が、有機化学における新分野の開発に役立ったりすることがあり、あらたなリサーチクエスチョンを作ることの助けになります。もし異分野の研究者同士で協力すれば、最終的な論文作成におけるオーサーシップへの貢献は、非常に大きなものとなるでしょう。
研究計画が決まったら、次にそれらを達成するための方法論的アプローチも検討します。
研究者全体で研究計画を作成することも有効ですし、あるいはファーストオーサーとなる研究者がまず計画して、それを当該の研究計画に落とし込んでいくこともあるかもしれません。
少なくともこのような共有感が研究遂行時には重要で、研究者全体による研究遂行になることが大切です。ファーストオーサー候補だけではなく、オーサー全員が自身の専門分野に基づく、実際の貢献が求められます。
その後、研究計画にそって実験をおこない、実験データを得ることになります。たとえば、実験や関連研究の文献レビューを行う、場合によっては、プログラミングコードを書くことなどの技術的貢献も必要です。
実験データが得られたら、その実験結果を分析・解析します。また実験データを伝えるためのグラフや表などを作成し、必要に応じて統計解析を行うことになります。
現代科学では、統計解析の重要性はますます高まっています。バイオ分野から、有機化学や物性物理分野まで、従来のデータとの有意差を提示することにつながります。解析に使用するデータの入手と処理方法が、たとえば新規素材の有用性を示すことにもなります。
使用するデータを得るための実験方法や場合によっては原料までチェックしなければなりません。実験データの正しい処理によって、適切なオーサーシップが発揮されるともいえます。
これらのすべてのプロセスに対して、ファーストオーサーはもし全ての実験に参画しなくても、少なくともその実験内容には精通している必要があります。
というのは、研究不正などで実験データの改ざんなどの指摘をうけることのないようにしなければならないからです。もしあらぬ疑いをかけられた場合でも、すぐに反論できる材料を持っていることがオーサーシップではとくに大切です。
研究遂行時における、データ収集・分析への貢献は、論文の執筆・修正や最終稿の承認などにとどまらず、オーサーシップの重要な要件となっています。
オーサーシップでは、論文作成時のオーサーの役割が大切です。とくに、ファーストオーサーと呼ばれるメインの論文著者の役割が鍵となります。
ファーストオーサーは、単に論文執筆段階における論文作成のプロセスだけではなく、当該研究実施段階、とくに研究計画の主導的プロセスから指導力を発揮しています。
また他の研究者との共同検討による研究計画の設定を行い、論文執筆段階だけの論文作成ではなく、学術論文が完成するまでのすべてのプロセスに精通していなければなりません。
研究論文には、必ず専門的なキーワードをいれるのもオーサーの責務です。他の研究者の検索結果において、自身の論文が正しく内容把握されるようになります。
また原著論文作成後は、かならず他のオーサーなどにチェックしてもらうようにします。研究論文のアウトライン(構成)を準備してから、実際の本文を作成すると論理的に執筆しやすくなります。
以下の記事では研究論文のアウトラインに関してより詳しく解説しています。
論文原稿が完成したら、すみやかに全てのオーサーに共有し、修正などがあればファーストオーサーが対応します。最後に論文を学術雑誌に投稿することになります。
研究計画の段階で投稿先がきまっていることもありますが、通常は、できあがった論文を検討して投稿先を決定することが多いようです。これもファーストオーサーが他の著者の意見も聞いたうえで、決定することになります。

オーサーシップにより作成された論文には、新規性や有用性を有する学術論文があります。
学術論文を学術雑誌に投稿することは、研究者にとって重要な作業といえるでしょう。学術論文を投稿する場合は、すべてではないですが、特にオリジナリティーのある研究成果が必要です。
このため自身の研究にあっても日頃から、新規性や有用性の高い成果を探求していくことも大切です。もちろんオリジナリティーばかり追及するのも考えものですが、海外大学の研究室などでは、いかにしてオリジナリティーを出すか、研究室内で常にディスカッションしているところもあります。
日本では、基礎研究など地道な研究自体を評価する旨もありますが、日進月歩の分野では、地道な研究に合わせて、しっかりとした研究評価やメンバーどうしのディスカッションが大切です。
論文査読時の対応にも、オーサーシップの発揮が重要となります。
学術論文においては、論文投稿時の査読対応も大切です。論文投稿後には、学術雑誌の査読者によって、論文の評価が行われるからです。
論文のオリジナリティーを重視する学術雑誌では、論文の投稿水準の維持にも力をいれています。また最近は研究公正ともよばれる、研究成果の真偽に関する問い合わせも多くなってます。このため有名な学術誌ほど、投稿後の論文が受理される割合は低くなっているのです。
オーサーシップにおいては、とくにファーストオーサーが研究論文に関する最終的な責任を持ち、中長期的にも問い合わせに応じられる体制が必要です。
研究論文には、コレスポンディングオーサーの連絡先が記載されている場合もあります。これにより、コレスポンディングオーサーが、その論文に関する問い合わせの代表者となります。
責任あるコレスポンディングオーサーとしては、すぐに連絡が取れる状態でなければなりませんし、後で述べるように万が一、研究不正があった場合には責任をとらなければなりません。学術誌の事務局とのコミュニケーションは、すべてタイムリーに行うことが必要です。
投稿後には、投稿学術雑誌の査読者から質問が来るのでこれにも対応します。単に査読者が勘違いしていることもありますが、質問には迅速に誠実に回答することが必須です。
ファーストオーサーとして実験全体に精通していることにより、もし論文投稿後に、査読者から実験データの疑義があった場合も、すみやかに回答することができます。
論文査読時における、評価ポイントととして、論文の完成度に加えて、新規性、有用性、信頼度などの観点から多角的に評価されます。
なによりオリジナリティーが一番重要な要素となるのです。一般的に査読者の氏名は公開されず、論文執筆者にもわかりません。複数の査読者の評価結果をもとに、編集委員会で審査が行われ、受理、修正必要、却下などの判断がくだされます。
投稿後には、一部修正などの連絡がある場合が多いので、この場合には、査読者の指摘事項に基づき、論文本文の修正や、場合によっては追加データなどの提出も行います。
この対応をおろそかにすると、最終段階の論文受理(Accept)にはつながりません。特に海外の著名学術誌への投稿では、英文でのやりとりになりますので、その内容にも注意が必要です。
研究公正とオーサーシップの関係についても、論文に対するオーサー責任という観点から解説します。
論文のオリジナリティーを重視する学術雑誌では、論文の投稿水準の維持を目標としています。最近は研究公正ともよばれる、研究成果の真偽に関する問い合わせも多くなっています。著名な学術誌ほど、投稿後の論文が受理される割合は低くなっているのです。
オーサーの中でもファーストオーサーは、研究論文に関わる全員の貢献を正しく確認することが必要です。というのは、研究不正が発覚した場合は、ファーストオーサーがまず責任を負うことになるからです。
残念ながら、海外大学だけではなく、国内大学、ときに有名大学でも研究不正にともなう研究論文の取り下げが複数おきています。万が一の場合は、迅速に対処することが求められており、ネイチャーなど国際的学術雑誌の姿勢は、最近特に厳しくなっています。
一部の学術誌では「研究公正」として、不正ではなく公正性の担保という考え方から議論されているようです。
ネイチャーでは、研究公正に関する世界的な調査レポートを公表しています。
下記リンク先:
「研究公正(research integrity)とは研究の提案、実施、評価における誠実で検証可能な手法を利用すること、規則および指針の順守に特別な注意を払い研究結果を報告すること、そして広く受け入れられている職業上の行動規範や基準に従うことであり、研究活動を正したり罰したりすることを目的として設けられている基準ではない。
しかし残念ながら、研究公正は、それが守られているときではなく、害されたときだけ大きく報道される。近年、高温超伝導や幹細胞などさまざまな分野で数多くの研究公正に抵触する事例が発生し、注目を集めている。」としており、生物学などの最先端分野での事例について検討しています。
ネイチャー発行事務局では、世界的な取り組みの一環として2024年1月末にかけて、日本科学振興協会と共同で、日本における研究公正のトレーニングの提供状況や内容の実態把握に関するアンケート調査を実施したとしています(調査対象国は、オーストラリア、英国、米国、インド、日本)。
この中で、同誌の「研究公正」部長は、研究公正と出版倫理に関する傾向と課題を概説しています。
同部長は、既発表論文の撤回件数が増加傾向にあり、2023年には1万編以上の研究論文が撤回されたと指摘しています。この中で、「1つの不正確な研究によってどれほどの被害が生じるのかを示す一例として、脳卒中患者の大腿骨近位部骨折に関する2005年の論文がある。
この論文は、不正なデータに基づいていることが判明して2016年に撤回されるまでの間、220回以上引用され、ヒトと動物を対象とした無作為化比較試験81件に影響を与えた」
と記載していますが、実はこの論文のファーストオーサーは、日本人なのです。
同レポートによると、日本では特にeラーニングによる研修が多く、実学が伴われていない傾向があるということです。とかく日本では、コンプライアンス研修なども含め、eラーニングによる研修が他国より多くなっています。大学ばかりでなく、官庁や企業でも同様な傾向があるようで、この辺の改善が必要かもしれません。
当方も大学勤務時に、研究倫理やコンプライアンスに関する、eラーニング研修を受けたことがありますが、これで解決するものではありません。研究者倫理として、いわゆる抽象論が多くなっていたりする傾向もありますが、その対局がオンライントレーニングとしているのでは、なかなかその間のギャップが埋まらないともいえます。
研究者が研究論文を書く場合に、オーサーシップはさけて通れない概念となっています。
またオーサーシップでは、その権限と責任の両方にも留意する必要があります。
学術論文などの研究成果を記載するときには、論文の著者であるオーサー全員が継続的に関与しなければなりません。適切なオーサーシップの発揮によって、はじめて投稿する学術論文が受理されることになります。
国内でも研究論文のアイデアが出るまでは、他の論文を読まないように指導している先生もいるようです。論文のアイデアが出てから、はじめて他の論文を検討することも、オリジナリティのある研究論文を作成する手助けになるかもしれません。
本記事が、学術論文を作成したり、これから投稿しようとしているみなさまのお役に立てば幸いです。

研究や論文執筆にはたくさんの英語論文を読む必要がありますが、英語の苦手な方にとっては大変な作業ですよね。
そんな時に役立つのが、PDFをそのまま翻訳してくれるサービス「Readable」です。
Readableは、PDFのレイアウトを崩さずに翻訳することができるので、図表や数式も見やすいまま理解することができます。
翻訳スピードも速く、約30秒でファイルの翻訳が完了。しかも、翻訳前と翻訳後のファイルを並べて表示できるので、英語の表現と日本語訳を比較しながら読み進められます。
「専門外の論文を読むのに便利」「文章の多い論文を読む際に重宝している」と、研究者や学生から高い評価を得ています。
Readableを使えば、英語論文読みのハードルが下がり、研究効率が格段にアップ。今なら1週間の無料トライアルを実施中です。 研究に役立つReadableを、ぜひ一度お試しください!
Readable公式ページから無料で試してみる
都内国立大学にて、研究・産学連携コーディネーターを9年間にわたり担当。
大学の知財関連の研究支援を担当し、特にバイオ関連技術(有機化学から微生物、植物、バイオ医薬品など広範囲に担当)について、国内外多数の特許出願を支援した。大学の先生や関連企業によりそった研究評価をモットーとして、研究計画の構成から始まり、研究論文や公募研究への展開などを担当した。また日本医療研究開発機構AMEDや科学技術振興機構JSTやNEDOなどの各種大型公募研究を獲得している。
名古屋大学大学院(食品工業化学専攻)終了後、大手食品メーカーにて31年間勤務した経験もあり、自身の専門範囲である発酵・培養技術において、国家資格の技術士(生物工学)資格を取得している。国産初の大規模バイオエタノール工場の基本設計などの経験もあり、バイオ分野の研究・技術開発を得意としている。
学位・資格
博士(生物科学):筑波大学にて1994年取得
技術士(生物工学部門);1996年取得