
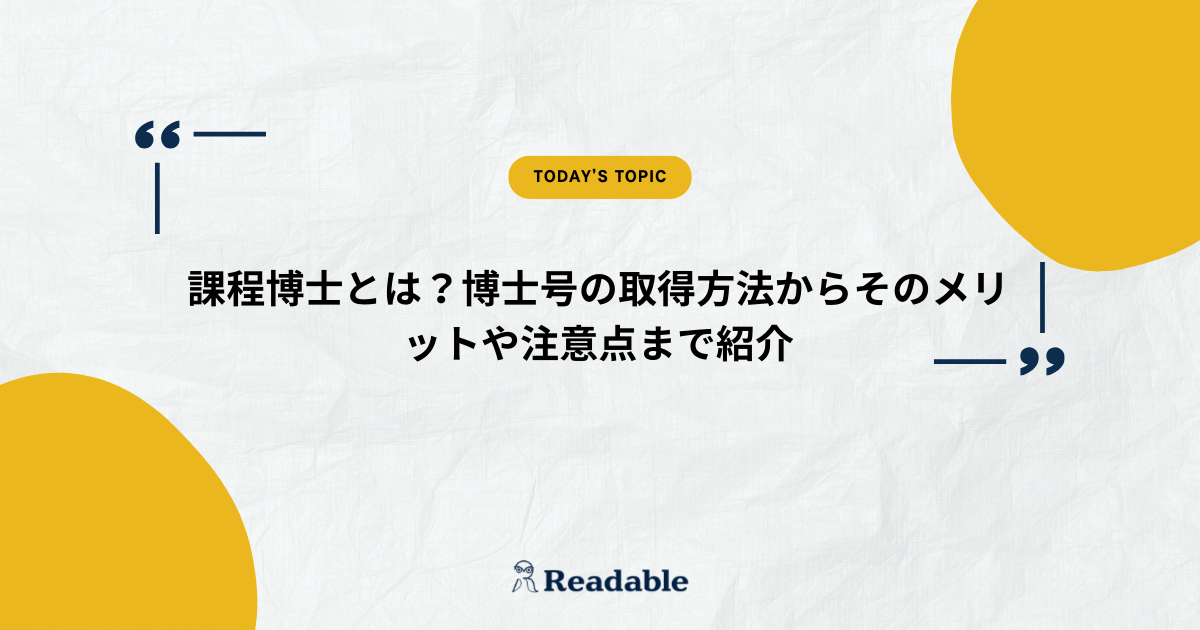
課程博士とは、論文博士に対する我が国の独特の用語です。
博士号には、大学院の博士課程により博士号を取得する課程博士と、研究所や企業などに就職後に取得する論文博士という、ふたつの資格があります。
このように博士課程で博士号を取得した人のことをいいますが、海外では、通常は大学院にて博士号を取得するので、日本でいう課程博士がほとんどということになります。
本記事では、課程博士の定義から、大学院での取得方法や、メリットや注意点まで解説します。
博士号には、大学院で博士号を取得する課程博士と、大学卒業後に取得する論文博士があります。
博士の学位授与の円滑化については,これまで,学位制度の見直しや関係者自身の意識改革とその自主的努力により,徐々に改善傾向が見られるが,特に人文社会科学系については,いまだ不十分である。また,近年では留学生の博士学位授与率が専攻分野によっては低下傾向にある。
このような状況を踏まえ,課程制大学院の本来の目的,役割である,厳格な成績評価と適切な研究指導により標準修業年限内に円滑に学位を授与することのできる体制を整備することが必要である。その際,これらの取組が大学院教育に求められる学生の個性,創造性の伸長に資する教育・研究指導を妨げるものであってはならないことにも留意すべきである。
引用先:https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/05090501/009.htm
このように博士号、いわゆる課程博士について、いまだいろいろな問題があることが伺えます。特に、理工学系と比較して、人文社会科学系では学位授与の円滑化が不十分であるとの記載もあります。さらには、大学院における成績評価と研究指導の重要性が強調されており、学生ひとりひとりの創造性の発展と両立すべきことが指摘されています。
課程博士では、博士課程に入学し、定められた期間で所定のカリキュラムを履修しながら研究を進め、在学中に博士論文の審査に合格することで学位を取得します。
すなわち、課程博士においては、大学院教育とその終了という「教育的側面」と博士論文の審査という、いわゆる「研究的側面」を両立させることが求められているといえます。
このように、大学院の博士課程に在籍し、授業や研究活動に参加し、卒業論文を提出して博士号を取得するのが、課程博士といえます。
論文博士の取得の場合は、大学卒業後に、あらためて大学院に博士論文を提出して審査されるのに対して、あくまで大学院の課程内で授与されるものなのです。実は、海外では博士号といえば、ほとんどの場合課程博士のことを指しています。論文博士は、日本独特の制度であり、いわば従来からの慣習も一部含めた妥協の産物ともいえます。
課程博士とは、学校教育法による「学位規則」として、下記のように設定されています。
(博士の学位授与の要件)
第四条 法第百四条第三項の規定による博士の学位の授与は、大学院を置く大学が、当該大学院の博士課程を修了した者に対し行うものとする。
課程博士とは、以上のように、大学院の博士課程に進学し、所定の単位を取得したうえで博士論文の審査に合格した場合に授与される学位であると明確に記載されているのです。
課程博士の大学院教育には、4年制学部を卒業したのか、医学・薬学などのいわゆる専門的学位が授与される6年制学部を卒業したのかによって、一部ことなります。ただ博士号としては、いずれも課程博士として同様に授与されます。
実は、論文博士についても、同じ「学位規則」の中に規定されています。
(博士の学位授与の要件)
2 法第百四条第四項の規定による博士の学位の授与は、前項の大学が、当該大学の定めるところにより、大学院の行う博士論文の審査に合格し、かつ、大学院の博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認された者に対し行うことができる。
このように、大学院の行う博士論文の審査に合格し、かつ、大学院の博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認された者については、博士号を授与できるとしています。論文博士となるわけですが、博士号としてはいずれも同等なものになります。
論文博士とは、大学院の博士課程に在籍せずに、提出した博士論文の審査に合格することで、博士号を授与される制度です。課程博士と異なり、博士論文の審査会で評価されることで博士号を得る、日本特有の制度です。正規の博士課程を終了していなくても、大学院に博士論文を提出することにより取れる資格が、論文博士なのです。
論文博士をとるには、まず大学院のある大学に申請する必要があります。また大学院であれば、どこでも良い訳ではなく、自身の研究テーマに沿った研究課程を有する大学院でなくてはなりません。
「論文博士」について、さらに詳しく知りたい人は、下記の当コラムも参考にしてください。
引用先:論文博士とは?取得方法からそのメリット・デメリットまで紹介
課程博士では、博士課程のある大学院に入学して、修了時に博士論文を提出して、博士課程内で博士号を取得することになります。
課程博士の取得には、通常の4年生学部卒業の場合と、最近増えている、医学・薬学系などの6年生学部を卒業した場合があります。
4年制の学部を卒業した場合は、博士前期課程(従来の修士課程のこと)2年間修了後、さらに博士後期課程3年間の教育や研究生活を送ることになります。
6年制の学部を卒業した場合は、博士課程4年間を修了し、博士論文の審査が通れば、年限上での博士号取得の資格を得ることができます。
まず大学院の博士課程、すなわち博士前期又は後期課程か、医学系などの博士課程に入学することが必要です。課程博士での、博士論文となる研究テーマに関連する大学院の課程を選択します。自身が希望する研究課題に近い大学院を選ぶようにしましょう。
また博士前期課程では、当然入学試験があります。通常は当該課程がカバーする研究領域に関する基礎科目や専門科目などの試験があり、それらに対する試験準備もそれなりに大切です。同じ大学の場合は、大学院の試験も大学学部の講義にリンクしている場合などもあり入学しやすい可能性もあります。他大学から別の大学院を目指す場合は、あらかじめ過去問などが入手できれば、それらを参考に検討をすすめます。またたいてい面接試験があり、専門的な内容の質問があるので、これにも準備が必要です。
入学には、修士学位や専門職学位、またはこれと同等の学力があると認められた者などが対象となります。なお当該の入学試験や選考基準は、各大学の規定に従います。
特に博士前期課程では、かなりの数の所定の単位を修得する必要があります。たとえば、平日午前中はこのような講義の受講があり、午後は自身の研究活動などが必要であり、場合によっては、夜まで実験を継続することもあります。このため結構な時間を博士号取得のためには費やさなくてはなりません。
当方も博士前期課程(従来の修士課程)に在籍したことがあり、この時期が一番大学に出入りした時間が長かった経験があります。課程博士はもらっていませんが、前期課程の修了時には修士論文が完成していないと課程修了とは見なされませんでした。
その当時は、同期が4名で筆者を含む3名は修論作成後、企業にそれぞれ就職しております。なおこの中から、1名が博士後期課程に進学となっています。博士号も同大学にて受領後、ある大学の助手(助教)となりました。当方は、学部は別の大学を卒業(学士論文も作成)しており、同じバイオ分野とはいえ、綿栓(試験管にふたをする培養用のもの)の作り方から全く異なる研究環境でした。
博士論文の準備と作成にもそれなりの時間がかかるので、大学院入学後、すぐ取り掛かることが大切です。
指導教官のもとで、専門分野に関する研究活動を行うとともに、最終的な博士論文の研究テーマを設定します。この研究テーマは入学後、早期に決定されることになります。修士論文なら2年目になってからということが考えられないわけではありませんが、博士論文はそうも行きません。あらたな研究視点があればよいということだけはなく、理工学分野では、それなりの研究成果が必要です。研究成果が出ないから別の研究テーマにするということがないではないですが、別のテーマになったから成果が出るというものではありません。自身が入学時に研究してみたいテーマがあるはずで、それもない場合は、博士とはいいにくいことになります。
博士論文は、当該研究分野にとって新規性と有用性があるものでなくてはなりません。いわゆる原著論文の作成と同様な新規性が求められます。さらに専門的な内容であること、そして学術的に貢献するものであることが必要です。このように一定以上の研究成果をもとに、博士論文を執筆することになります。
当該の博士論文の構成については、当方のコラム「論文博士とは?取得方法からそのメリット・デメリットまで紹介」も、参考にしてください。
博士論文が作成できたら、大学院の審査委員会による論文審査(本審査)を受けます。またこれ以前に予備審査として、主査1名と副査数名からなる教官による論文内容の具体的な評価もあります。また課程博士以外に、論文博士を希望する人がいる場合も、同様な予備審査などのプロセスを経ています。
本審査に合格すると、はれて博士号が授与されることになります。
博士課程を修了した学生には「博士(◇◇)」の学位が授与されます。(◇◇)には、学位に付記する専攻分野の名称が入ります。
以前は、理学博士などの記載でしたが、最近は博士(理学)などの記載がほとんどとなっています。当方も論文博士ではありますが、博士(生物科学)を取得しています。取得時が切り替え時期であり、両方とも指定ができましたが、上記の審査委員会が大学院生物科学系に所属しており、同大学では博士(生物科学)という呼称を推奨していたことによります。現在は、ほぼ後者のような表記になっています。なお英文表記では、いずれも「Doctor of Philosophy」となることにも留意が必要です。
学位論文を取得する前に、まず博士課程のすべての科目を所定の成績以上で修了していなければなりません。このように単なる博士号の取得ではなく、教育的側面と研究的側面の両立が大切です。
大学院の年限にもよりますが、大学学部と同様に授業や実験など、実際に科目での講義に出席しなければならないので、最終年度での学生の負担はかなりのものとなります。課程博士では、このように教育的側面と、研究者のたまごとしての研究的側面の両立が求められているといえます。
このため最終年度ではかなりの負担がかかることになり、研究的側面において必要な博士論文の骨格となる、研究データをなるべく早めに得ておくことが必要です。博士論文での「研究テーマ」の設定など、いわゆる原著論文と同等な手順も求められます(研究テーマの設定や、論文構成の立て方などについては、本欄でいろいろなコラムがありますので、是非参考にして下さい)。
このため教官からの指導があるとはいえ、自身の努力が非常に大切です。文科省でも指摘されている、特に、大学院における成績評価と研究指導の重要性が強調されることになります。また指導ばかりにたよるのではなく、自身で考えて努力することが大切です。
課程博士は、当該分野の研究者として独り立ちする第一歩です。大学に残る場合は、ゆくゆく学生を自分が教育する立場になります。また企業に就職する場合でも、博士号を取得していると、それなりに新規性のある研究を任されることになるので、日頃から自分で当該研究領域を切り開いていく覚悟が求められます。
課程博士取得時のメリットとしては、下記のようになります。
課程博士の最大のメリットは、指導教官から常時、指導を受けながら研究を進められることです。
課程博士の場合、3年ほど博士課程に在籍し、指導教授から研究指導を受けながら研究活動に取り組めます。そのため、査読付き学術雑誌への論文掲載を目指したり、博士論文の基礎となる論文の作成を進めたりしやすい環境と言えます。
論文博士の場合、博士課程に在籍していないため、指導教官から指導を受けながら研究を進めることができません。このため研究の最初の段階でまず非常に苦労することになります。自身が考えている研究テーマ自体が、まず当該分野で検証され、しかも新規性と有効性を保持しているかという問題があります。これは実はかなり難しい問題で、いわゆる「原著論文」をまとめ上げるのと同等な課題であり、審査委員会などの評価がないと、独学ではなかなかたどりつけないレベルとなります。研究初心者の場合はなんらかのアドバイスを受けて実施すべきところで、かなりの時間と労力もかかります。
論文博士では、博士論文の水準まで論文をまとめ上げることが難しいというデメリットもあります。これに対して課程博士では、博士課程の目標でもある、研究者として独力で研究が実施できるというレベルまで到達する「教育的側面」を十分に享受することができるのは大きなメリットです。
課程博士では、履歴書に「大学院博士課程修了」という学歴記載が可能となります。
これに対して、論文博士として博士号を取得した場合、どの大学で取得しても学歴としては反映されません。資格としては、博士号を記載できますが、大学卒業欄は以前と同じことになります。当方も論文博士をある大学院から授与されていますが、学歴欄は以前の大学のままとなっています。
課程博士の取得においては、次のような課題があります。
課程博士の場合、大学院での費用負担はかなりのものになります。
これは日本でも海外大学でも同じ課題となっており、一般的に欧米の大学の方がさらに多額の費用が必要です。博士前期課程、いわゆる修士課程でさえ、かなりの高額となります。さらに3年間暮らしていく住居や生活費などもかかり、これらもばかにならない金額です。博士後期課程に進学する場合のネックとしては、自身の研究レベルより、費用負担の方が大きいかもしれません。当方も学歴としては、博士前期課程(修士課程)の修了者で、同じ研究室には4名修士候補が在籍していましたが、後期課程に進学したのはそのうち1名のみでした。
国立大学の場合、入学金として約30万円以上、授業料として年間約50万円以上が必要となります。これより10万円もさらに高い授業料をかしている国立大学もあります。私立大学の場合は、国立大学よりもさらに費用がかかり、平均でも数百万円という極めて高額となります。海外ではと思われるかもしれませんが、米国などのアイビーリーグの私立大学では、桁が違うレベルです。難関私立大学では年間少なくとも8万ドル以上なので、円安でもあり約1千万円以上の費用となります。
国内で取得する論文博士の場合は、自身が企業や研究機関で働いており給料もいただけます。このため、課程博士の場合とは、差し引きすればかなりの費用差異となります。奨学金など、大学院での支援制度もありますが、卒業後の奨学金の返済が課題となっています。企業などに就職しないと、奨学金の返済が難しいという事態が考えられます。奨学金返済は米国でも社会問題となっており、日本でもまだまだ支援が必要です。
このような問題を少しでも解決するため、文科省としても、修業年限内の学位授与を促進しているようです。大学院における円滑な学位授与を促進するため、改善策等を検討するとしています。
特に、学位授与に関する教員の意識改革の促進や、学生を学位授与へと導く教育のプロセスを明確化する仕組みの整備とそれを踏まえた適切な教育・研究指導の実践などの課題をあげています。またこれに合わせて、各大学院における学位の水準の確保にも取組み、今後は、学位論文等の積極的な公表や論文審査方法の改善なども行うとしています。
課程博士については、今後も継続的な改善策の検討が必要です。
博士課程では、後期課程でも通常3年以上の時間がかかるわけですから、年額の学費が年数分だけ、総額として支出されます。大学院の授業料も、博士課程での大学支出費用に充当されています。留学生を増やすと大学院経営が改善すると思われがちですが、実際には一部留学生からの授業料の回収が難しいときもあります。これらの問題で困っている国立大学もときにはあるようです。回収が比較的容易な国内学生と違い、授業料をおさめず故国に帰ってしまう一部の留学生に困っている大学もありました。
文科省では、授業料以外でもいろいろな問題が、博士号取得にも影響していることを認めています(下記)。
引用先:https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/gijiroku/attach/1412776.htm
現在、標準修業年限内に、博士論文を提出するに至らなかった学生の中には、例えば、授業料負担や就職等の関係のみならず、将来の研究計画に基づいて博士の学位を取得できるという見込みが不分明であるためなど、様々な理由により退学し、その後に「論文博士」を申請する者が見られる。
これらの実態は様々であり、種々の考えがあると推測されるが、実質的には博士課程における研究成果として評価すべき部分が少なくないことから、こうした者を「課程博士」として位置づけている大学もある。
これにより、我が国の課程制大学院制度の修了の考え方、「課程博士」、「論文博士」の用語の使われ方などに混乱が生じており、かえって「課程博士」の円滑な授与、学位の国際的な質保証に影響を与えかねないとの指摘もある。
また、博士論文を提出せずに退学したことを「満期退学」や「単位取得後退学」などと呼称していることがあるが、このことの背景の一つとして、課程制大学院の趣旨が徹底されていないことが考えられる。
このため、学位に関するこれらの考え方を整理した上で、その水準の確保を図りつつ、大学院に5年以上在籍し、必要な単位を取得、博士論文の審査試験に合格するなど博士課程の修了要件を満たした「課程博士」の円滑な授与の促進方策について検討する必要がある。
今のところ、まだ解決策がみつかったとは聞いていませんが、博士の呼称に関する課題があることを列記しています。すなわち課程博士と論文博士という日本独自の課題で、海外にはない問題となります。また学歴記載においても、大学院の満期退学や単位取得後退学などさまざまな呼称が、実際にも使用されているようです。
このように博士号については、課程博士と論文博士を含めてさまざまな問題や課題があり、継続的な検討が今後も必要です。
日本では科学技術立国として、科学技術政策が以前から推進されてきましたが、課程博士の課題、特に大学院費用負担の問題は残ったままです。
研究から開発まで、国家戦略として一貫して推進しているアジアの国も複数あります。これに対して国内では、大学院博士課程教育などを含め、文科省の政策が必ずしも適正なのかどうか検討が必要なのではないでしょうか。またいつまでも検討中としてそのままというのも困ります。
どうも日本では文科省と経産省、最近は環境省も含め、政策がちぐはぐなことが多く、国家戦略といえるものがあるかどうかも疑問です。たとえばの例ですが、大学院からの国際出願、特にPCT出願の費用などを、特許庁を管轄する経産省でもつことなども考えられ、大学院の研究費用をサポートする体制も必要です。
科学技術立国という看板をまだおろしていないのなら、それを推進する博士課程の学生への支援ももっと必要ではないでしょうか。特に大学院学生の支出費用はかなりの高額ですので、一定水準レベル以上の国内学生には、無償にするとかがあってもよいかと存じます。
国費留学生に選ばれると、毎月10万円以上の奨学金と大学学費まで免除されるという制度もあり、かなりの数の日本への留学生がこれを利用しています。この制度を管轄する文科省では、国内学生、特に大学院生にもその利用範囲を拡大すべきなのではないでしょうか。
資源のない国として科学技術政策が推進されてきましたが、まだまだ国内での研究開発が大切です。本記事が、課程博士を目指している学生や、関心のあるみなさまのお役に立てば幸いです。

研究や論文執筆にはたくさんの英語論文を読む必要がありますが、英語の苦手な方にとっては大変な作業ですよね。
そんな時に役立つのが、PDFをそのまま翻訳してくれるサービス「Readable」です。
Readableは、PDFのレイアウトを崩さずに翻訳することができるので、図表や数式も見やすいまま理解することができます。
翻訳スピードも速く、約30秒でファイルの翻訳が完了。しかも、翻訳前と翻訳後のファイルを並べて表示できるので、英語の表現と日本語訳を比較しながら読み進められます。
「専門外の論文を読むのに便利」「文章の多い論文を読む際に重宝している」と、研究者や学生から高い評価を得ています。
Readableを使えば、英語論文読みのハードルが下がり、研究効率が格段にアップ。今なら1週間の無料トライアルを実施中です。 研究に役立つReadableを、ぜひ一度お試しください!
Readable公式ページから無料で試してみる
都内国立大学にて、研究・産学連携コーディネーターを9年間にわたり担当。
大学の知財関連の研究支援を担当し、特にバイオ関連技術(有機化学から微生物、植物、バイオ医薬品など広範囲に担当)について、国内外多数の特許出願を支援した。大学の先生や関連企業によりそった研究評価をモットーとして、研究計画の構成から始まり、研究論文や公募研究への展開などを担当した。また日本医療研究開発機構AMEDや科学技術振興機構JSTやNEDOなどの各種大型公募研究を獲得している。
名古屋大学大学院(食品工業化学専攻)終了後、大手食品メーカーにて31年間勤務した経験もあり、自身の専門範囲である発酵・培養技術において、国家資格の技術士(生物工学)資格を取得している。国産初の大規模バイオエタノール工場の基本設計などの経験もあり、バイオ分野の研究・技術開発を得意としている。
学位・資格
博士(生物科学):筑波大学にて1994年取得
技術士(生物工学部門);1996年取得