
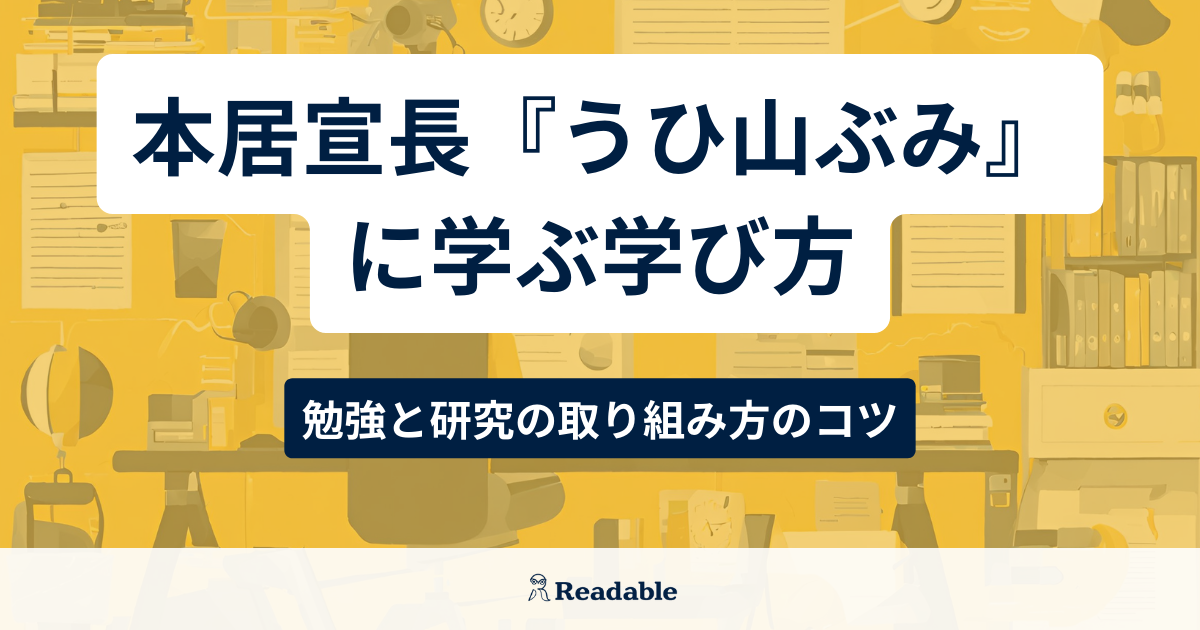
『うひ山ぶみ』は、『古事記伝』全 44 巻を書き終えた本居宣長が弟子たちに請われて書いた古学の入門書です。「うひ山ぶみ」は直訳すると「はじめての山歩き」ですが、このタイトルは巻末に添えられた
いかならむ うひ山ぶみの あさごろも 浅きすそ野の しるべばかりも
はじめての山歩きに着る粗末な麻布のような、こんな拙いわたしの教えでも、せめて裾野(初学)の標にはなるだろう
『うひ山ぶみ』訳・白石良夫、以下同
という歌に由来します。学問への入門と、はじめて山に入っていく様とをかけているのですね。『うひ山ぶみ』は古学への入門書でありながら、古学に限らない学問一般の心構えや取り組み方についても多くを教えてくれます(もっとも、大和魂を掲げ、漢意を排除することの重要性を説いた本居宣長ですから、その教えをコンピュータ科学の研究に活かすことを本人が良しとするかは定かではありませんが。)私は昔からこの本が好きだったのですが、研究者になった今読むとよりいっそう学問や研究についての深い洞察が得られる本だと感じます。これから研究をはじめる(「うひ山ぶみ」に乗り出す)大学生はもちろん、受験生から研究者までおすすめの一冊です。本稿では特にお気に入りの箇所を紹介します。
【原文】詮ずるところ学問は、ただ年月長く倦まずおこたらずして、はげみつとむるぞ肝要にて、学びやうは、いかやうにてもよかるべく、さのみかかはるまじきこと也。いかほど学びかたよくても、怠りてつとめざれば功はなし。[…] 不才なる人といへども、おこたらずつとめだにすれば、それだけの功は有る物也。[…] 才のともしきや、学ぶことの晩きや、暇のなきやによりて、思ひくづをれて止むることなかれ。とてもかくても、つとめだにすれば出来るものと心得べし。すべて思ひくづをるるは、学問に大きにきらふ事ぞかし。
【現代語訳】ようするに、学問は、ただ年月長く倦まず怠らず、励みつとめることが肝要なのだ。学び方はどのようであってもよく、さほどこだわることはない。どんなに学び方がよくても、怠けてしまってはその成果はおぼつかない。[…] 才能のない人でも、怠けずに励みつとめさえすれば、それだけの成果はあがるものである。[…] 才能がないとか、出発が遅かっただとか、時間がないとか、そういうことでもって、途中でやめてしまってはいけない。とにもかくにも、努力さえすれば出来るものと心得るべきである。諦め挫折することが、学問にはいちばんいけないのだ。
私はいわゆる頭が良いタイプではなく、少なくとも瞬発的に良いアイデアが閃くというようなステレオタイプな頭の良さはないと自認しているのですが、その中で研究をライフワークにするという決断をする際には、「不才なる人といへども、おこたらずつとめだにすれば、それだけの功は有る物也。」という言葉にたいへん勇気づけられました。私の個人ブログで紹介した 4 年以上続けている毎朝の論文読みなど、こつこつ積み上げる努力をしてこられたのも根底にはこのような考えがあります。並大抵の人がこのようなことを言うと口先だけのように聞こえてしまいますが、自ら 40 年以上にわたり研究生活を送り、多くの弟子も育ててきた本居宣長が言うとずっしりとした言葉の重みとともに説得力を感じます。同じようなことに悩み、進学したり研究者になるか悩んでいる人の背中を押す言葉になるはずです。
【原文】いづれの書をよむとても、初心のほどは、かたはしより文義を解せんとはすべからず。まづ大抵にさらさらと見て、他の書にうつり、これやかれやと読みては、又さきによみたる書へ立ちかへりつつ、幾遍もよむうちには、始に聞えざりし事もそろそろと聞ゆるやうになりゆくもの也。
【現代語訳】どんな書物を読むのにも、初心のうちは、はじめから文義を理解しようとしてはいけない。まずおおまかにさらっと見て、ほかの文献にうつり、これやかれやと読んで、さらに前に読んだものにかえればいい。それを繰り返せば、最初に理解できなかったことも徐々にわかるようになるものだ。
【原文】文義の心得がたきところを、はじめより一々に解せんとしては、とどこほりてすすまぬことあれば、聞えぬところは、まづそのままにて過すぞよき。
【現代語訳】文意の解しがたいところを、はじめからひとつひとつ解きあかそうとすると、滞って先にすすまないことがある。そんなときは、不明なところはそのままにしておいて、先にすすめばいい。
新しく物事をはじめる際、細かな計画を立てたのはいいもののそのとおりに進められず、うまくいかないがためにやる気がしおれて止めてしまうというのはよくある失敗パターンです。初心者のうちは、まずは全体像を俯瞰できるようになることだけを一直線に目指し、そこから段々と細部へと進んでいくトップダウン方式が何事においても習得方法の王道だと思います。私も新しいトピックを学ぶ際には、このように進めることを心がけています。特に研究に繋がる最先端のトピックだと、情報が整理された形で得られないため、 1 から 10 まで順番に学べることはまずありません。細部からはじめてしまうと、自分がいまどの位置にいるのかが分からないため、進んでる感が得られず、やる気を保つことが困難です。「思ひくづをれて止むること」が学問にとってもっともいけないことであるとは前項でも紹介した通りです。
とはいえ、あまり極端に走り、目が滑っているだけ、内容を理解せず素読しているだけ、では効果は薄いので、理解できないところは 3 分考えて、分からなかったら次に進む、というような時間の目安を自分で設けておいて、飛ばしたところにはまたレベルアップしてから立ち返ってくるのが良いと思います。これは私が競技プログラミングをしていたとき、東大金子先生の実践的プログラミングの講義資料で見つけて取り入れたアイデアです。
経験が少ない段階では,15 分以上悩まないことをお勧めする.手掛かりなく悩んで時間を過ごすことは苦痛であるばかりでなく,初期の段階では学習効果もあまりないので,指導者や先輩,友達に頼る,あるいは一旦保留して他の問題に取り組んで経験を積む方が良いだろう.
問題解決のためのプログラミング一巡り
ここでは 15 分となっていますが、学んでいるトピックや熟達度合いに応じて柔軟に変えると良いでしょう。
【原文】殊に世に難き事にしたるふしぶしをまづしらんとするは、いといとわろし。ただよく聞えたる所に心をつけて、深く味ふべき也。こはよく聞えたる事也と思ひて、なほざりに見過せば、すべてこまかなる意味もしられず、又おほく心得たがひの有りて、いつまでも其誤りをえさとらざる事有る也。
【現代語訳】難解なところをまず知ろうとするのは、たいへんよくない。平易なところにこそ心をつけて、ふかく味わうことをしなくてはならない。わかりきったことだと思っていい加減に見過ごせば、微妙な意味が感得できず、さらに間違って解釈していても、その誤りにいつまでも気がつかないものである。
私は高校生のころ、竹内外史『層・圏・トポス』をあまり理解もせずカッコつけて読んでいました。線形代数は志賀浩二『線形代数30講』をさらっと一度だけ読み通して完全に理解した気になっていましたが、線形代数の奥深さは一冊一度の通読で習得できるようなものではなく、理系あるあるの「あの時もっとちゃんと線形代数を勉強していれば」を完璧に踏み抜きました。もちろんそういう背伸びの読書は視野を広げてくれるので、排除するべきというわけでは決してありませんが、もうすこしバランスに気をつけても良かったのではないかと今では思います。
基本事項を完璧に仕上げることの重要性は受験勉強から研究まであらゆる学問の段階でいえます。解の公式や余弦定理や等比数列の和の公式など、重要な定理を暗記ではなく自力で瞬時に導けるようにする、というのは私が受験生のときにもやっていましたし、私の周りの受験数学が得意な人たちは皆やっていたように思います。公式や定理を使って解く計算問題や証明問題はあくまで枝葉であり、根本である公式や定理そのものを深く理解するというのはこの考え方に通じます。
研究においても基本的な事項をしつこく復習するのは大事だと感じています。私の研究分野は流れが早いので、ついつい先月や昨日発表された論文を読んでしまいますが、大きな学びが得られたり、良い研究のアイデアが思い浮かぶのは古典的で基本的な論文を読んでいるときであることが多いように思います。Transformer を使った(言ってしまえば枝葉の)論文は何十本も読んだが、Transformer の元論文は一度読んだきりというような研究者も多いのではないかと思います(機械学習分野以外の研究者の方は、Transformer の部分を当該分野の基本的なキーワードで置き換えてください。)私も思い当たる節は多いので、この言葉には改めて深く考えさせられます。
【原文】書をよむに、ただ何となくてよむときは、いかほど委しく見んと思ひても限りあるものなるに、みづから物の注釈をもせんとこころがけて見るときには、何れの書にても、格別に心のとまりて、見やうのくはしくなる物にて、それにつきて又外にも得る事の多きもの也。されば、其心ざしたるすぢ、たとひ成就はせずといへども、すべて学問に大きに益あること也。是は物の注釈のみにもかぎらず。何事にもせよ、著述をこころがくべき也。
【現代語訳】書物を読むのに、ただなんとなく読むときは、どんなに詳しく読もうと思っても、限りがある。自分で注釈をしようと心掛けて読むと、どんなものでも意識して気にとめるから、読み方が精緻になる。また関連してほかに得ることも多い。したがって、注釈は、それが完成しなくとも、学問にとって大いに有益なのである。これは注釈に限ったことではない。なにごとにせよ、著述を心掛けねばならない。
私は論文や教科書やブログ記事を多く書く方ですが、その理由は著述の対象に「格別に心のとまりて、見やうのくはしくなる物にて、それにつきて又外にも得る事の多き」ためというのが一つあります。メタ的ですが、このブログ記事を書いている今も、うひ山ぶみについて多くのことを学んでいます。もちろん、他にも書く理由は(研究したことは発表しないと意味がない、など)さまざまあるのですが、インプットのためのアウトプットという理由も心に留めておくと、インプットとアウトプットの両面で役に立つと思います。
【原文】又、古人の歌はみな勝れたる物のごとくこころえ、ただ及ばぬ事とのみ思ひて、そのよしあしを考へ見んともせざるは、いと愚かなること也。いにしへの歌といへども、あしきことも多く、歌仙といへども、歌ごとに勝れたる物にもあらざれば、たとひ人まろ・貫之の歌なりとも、実によき歟あしき歟を考へ見て、及ばぬまでも、いろいろと評論をつけて見るべき也。すべての歌の善悪を見分くる稽古、これに過ぎたる事なし。大きに益あること也。
【現代語訳】古人の歌はみな優れたもののように心得て、ただ及びもつかないとばかりに思って、そのよしあしを考えてみようともしないのは、まことに愚かである。古の歌が優れているというのでもない。だから、たとえ人麻呂・貫之の歌であっても、ほんとによいものかそうでないかをよく考えて読む、及ばぬまでも、いろいろと評論して読む、歌のよしあしを見分ける修練にこういうやり方以上のものはなく、おおいに有益である。
先人の主張や常識を疑うというのは研究の基本です。先にも述べましたが、古典的で基本的な論文を読んでいるとき、そこでの前提や主張を疑うことが良い研究のアイデアに繋がることがよくあります。「たとひ Hinton, Bengio の論文なりとも、実によき歟あしき歟を考へ見て、及ばぬまでも、いろいろと評論をつけて見ること」は、研究を上達させるための実際上のテクニックとしても有益であると思います(機械学習分野以外の研究者の方は、Hinton, Bengio の部分を当該分野の偉大な研究者で置き換えてください。)
本稿は白石良夫全訳注『本居宣長「うひ山ぶみ」』を基にしました。
原文、訳文、注釈が付いて文庫本 253 ページとコンパクトなので、本稿で興味を持った方は全文を読んでみることをおすすめします。
うひ山ぶみは本居宣長個人の体験を基に書かれた指南書ですが、エビデンスに基づいた勉強法を知りたい方は以下の二冊をおすすめします。
竹内龍人『進化する勉強法』
本書はトピックごとに関連する実験心理学の研究を紹介する方式を取っています。全ての研究の元論文が引用されていることはもちろん、実験設定や定量的な結果の紹介があり納得感が強いです。私は実験心理学は専門ではありませんが、そういう風に介入群を設定するのか、など、一研究者として実験設定を読み込むのも面白かったです。
安川康介『科学的根拠に基づく最高の勉強法』
こちらは Improving students’ learning with effective learning techniques: Promising directions from cognitive and educational psychology [Dunlosky+ Psychol. Sci. Public Interest 2013] という有名なモノグラフに基づいた勉強法の解説書です。こちらも実験設定や定量的な結果を含む複数の実験研究を紹介しています。『進化する勉強法』と比べると、著者個人の経験や具体的な活用方法がふんだんに盛り込まれているのが特徴です。
勉強法に興味がある人であれば、聞いたことがある・知らず知らず実践しているテクニックが大半だとは思いますが、定量的な実験結果を読むと各テクニックについて新しい印象も得られます。
例えば、学習対象を何も見ずに能動的に記憶から引き出すアクティブリコールが有用であると述べられています。実験としては、14 分間全てを資料の読み込みに使ったグループと、7 分間資料を読み込み、残りの 7 分をアクティブリコールに使ったグループでは、後者の方が内容をよく覚えており、この差は勉強を終えてから時が立つにつれて広がったというもの [Roediger+ Psychol Sci. 2006] や、何もヒントの無い状態で思い出した学生のほうが、文章の一部が空欄になっているというようなヒントのある状態で思い出した学生たちよりも、記憶の定着が良かったというもの [Carpenter+ Mem Cognit. 2006] などが紹介されています。
ジョッシュ・ウェイツキン『習得への情熱』
逆に、カッチリとエビデンスがあるものではなくとも、達人の個人的経験から得られるような、検証し難いがその分深い洞察の方が好みだという方には、ジョッシュ・ウェイツキン『習得への情熱』がおすすめです。基本的なことがらを極限まで体の中に染み込ませる「より小さな円を描く」という考え方は、『うひ山ぶみ』で述べられている「ただよく聞えたる所に心をつけて、深く味ふべき也。」という考えと驚くほど符合します。
トップになるために必要なのは、ミステリアスなテクニックなんかではなく、一連の基本的技術とされているものだけを深く熟達させることだ。どんな分野でも深さは広さに勝る。深く掘り下げることで、自分の中に隠れているつかみどころのない無意識的でクリエイティブな潜在性を引き出すための道を切り開くことができるからだ。
習得への情熱
京都大学情報学研究科博士課程修了。博士(情報学)。Readable を開発・運営している。専門は機械学習とデータマイニング。著書に『最適輸送の理論とアルゴリズム』『グラフニューラルネットワーク』がある(ともに講談社)。
連絡先:@joisino_ / https://joisino.net