
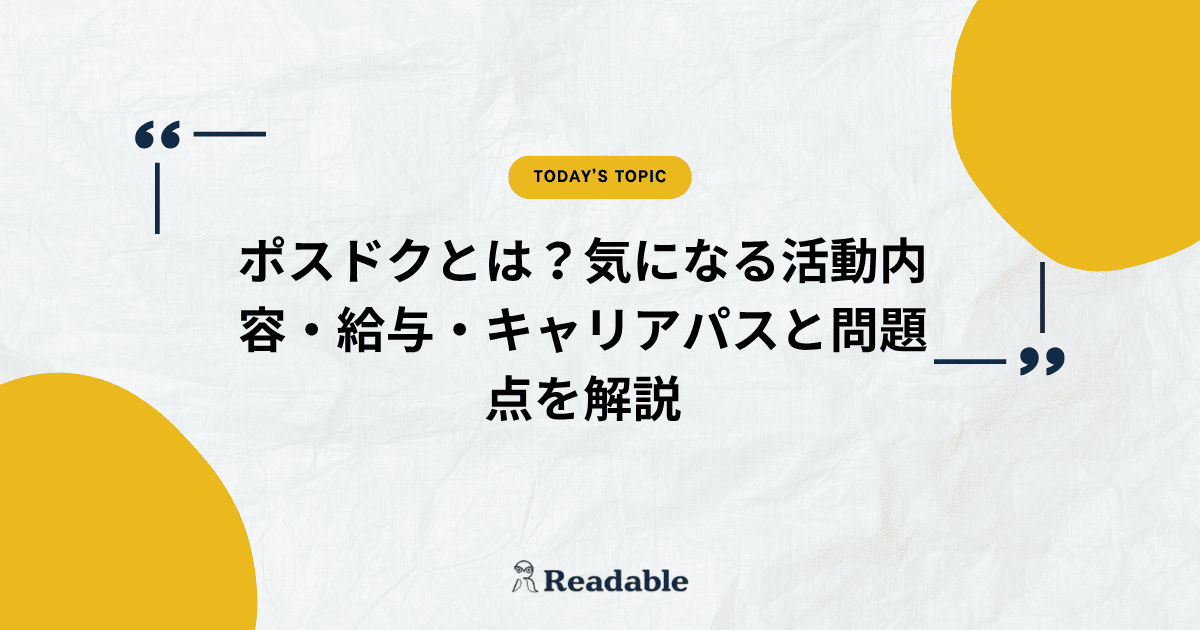
博士課程を終えたものの、その後のキャリアをどう描けば良いのか?多くの方が直面するこの課題。あるいは「ポスドク」という言葉は耳にするけれど、具体的な活動内容や待遇、将来性についてはよくわからない。
そんな疑問や不安を抱える方へ、本記事では、ポスドクという選択肢の実態を、活動内容から給与、キャリアパス、そして見過ごせない問題点に至るまで、徹底的に深掘りし、あなたのキャリア選択の一助となる情報を提供します。
目次
まずは、「ポスドク」という言葉の正確な意味と、研究の世界における彼らの立ち位置、そして日々の活動内容について見ていきましょう。
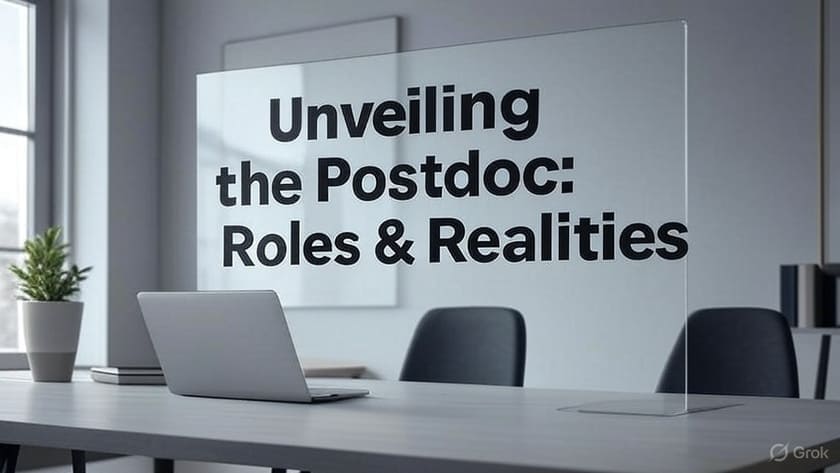
ポスドク(ポストドクター)とは、大学院博士後期課程(ドクターコース)を修了し博士号を取得した後、大学や公的研究機関などで研究活動に従事する任期付きの研究者を指します。「博士研究員」とも呼ばれます。
日本のアカデミアにおけるキャリアパスでは、ポスドクは多くの場合、助教や准教授といったより安定した任期の定めのない職(テニュアポスト)を得るための一時的なステップ、あるいは専門的な研究能力をさらに高めるための訓練期間として位置づけられています。大学の教員組織では、一般的に教授を頂点として准教授、助教と続き、ポスドクはその下に位置づけられることが多いです。この期間に研究実績を積み上げ、次のキャリアステップを目指すことが期待されます。
しかし、この「訓練期間」が意図せず長期化し、不安定な状況が続く「ポスドク問題」も深刻な課題です。博士課程修了者が増加する一方で、大学教員のポストは増えていないという構造的な問題があり、結果として多くの博士人材がポスドクという形で一時的に吸収されている側面も指摘されています。実際に、2021年度の調査ではポスドクの67.9%が翌年度もポスドクを継続しており、この「訓練期間」が長期化する傾向がデータからも読み取れます。
ポスドクは、博士課程で培った専門知識を活かし、最先端の研究に携わることで、研究者としての独立に向けた重要な経験を積む期間とされています。
ポスドクの最も中心的な活動は、自身の専門分野における研究の推進です。これには、日々の実験や調査、データ分析、そしてそれらの成果を学術論文としてまとめ、国内外の学会で発表するという一連のプロセスが含まれます。
研究テーマは、所属する研究室の主宰者(PI:Principal Investigator)の研究計画に沿ったものであることが一般的です。大規模な研究プロジェクトに参加する場合、そのプロジェクトの目標達成に貢献することが求められ、研究の方向性がある程度定まっていることが多いです。例えば、JST CRESTのような大型プロジェクトでは、プロジェクト全体のゴール達成に向けた研究遂行が主な業務となります。
論文執筆は、研究成果を世界に発信し、研究者としての業績を構築する上で不可欠です。質の高い学術雑誌への論文掲載は、その後のキャリア形成において重要な評価指標となります。また、学会発表は、自身の研究成果を他の研究者と共有し、フィードバックを得る貴重な機会であると同時に、研究者コミュニティにおけるネットワークを構築する場でもあります。
ポスドク期間は、任期内に一定の研究成果を上げ、それを論文や発表という形で示すことが強く求められるため、研究活動への集中度は非常に高いと言えます。この期間にどれだけ質の高い業績を積み上げられるかが、その後のキャリアを大きく左右すると言っても過言ではありません。
ポスドクは自身の研究活動に専念することが基本ですが、所属する研究室やプロジェクトによっては、研究以外の業務にも関与することがあります。これには、学生の教育指導、研究資金の獲得活動、研究室運営の一部などが含まれます。
学生指導については、所属先の研究室の方針やプロジェクトの性質により関与の度合いは異なりますが、学部生や大学院生の研究指導や実験補助、セミナー運営などを担当する場合があります。これは、将来的に大学教員を目指すポスドクにとっては教育経験を積む良い機会となり得ます。
研究資金の獲得も重要な業務の一つです。日本学術振興会の科学研究費助成事業(科研費)のような競争的資金に応募し、自身の研究プロジェクトを推進するための資金を確保する努力が求められることがあります。特に、JSPS特別研究員PDのような自由度の高いポスドクの場合、科研費への応募は積極的に行われます。
研究室運営への関与としては、プロジェクトの進捗管理、予算管理、実験機器や消耗品の発注・管理、研究成果報告書の作成、プロジェクト関連の広報活動、成果報告会といったイベントの企画・運営などが挙げられます。
これらの業務は、研究プロジェクトを円滑に進めるために不可欠であり、ポスドクにとってはプロジェクトマネジメント能力を養う機会ともなります。ただし、これらの業務の比重が大きくなりすぎると、自身の研究活動に支障をきたす可能性もあるため、バランスが重要です。
研究者としてのキャリアを考える上で、経済的な安定は非常に重要な要素です。ここでは、ポスドクの給与体系や平均的な収入、そして社会保険や福利厚生の現状について詳しく見ていきます。
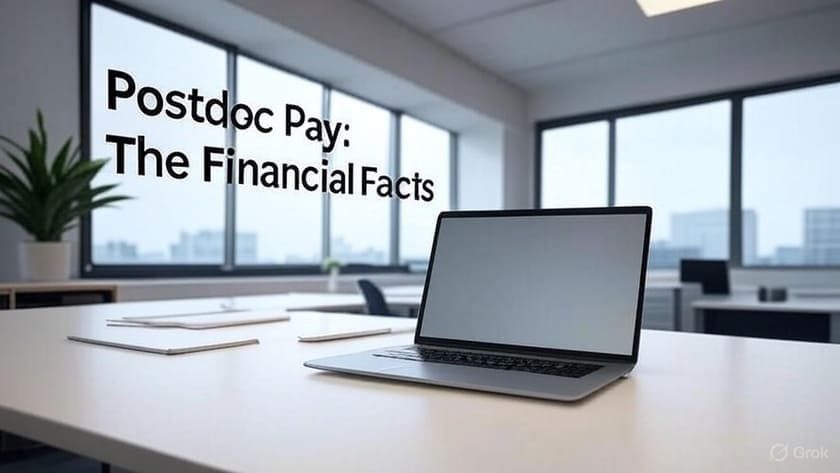
ポスドクの給与は、その財源によって大きく異なるのが実情です。主な財源としては、日本学術振興会(学振)の特別研究員制度、科学研究費助成事業(科研費)による雇用、JST(科学技術振興機構)などの大型プロジェクト資金、あるいは大学独自の予算などが挙げられます。
表:主な財源とポスドクの給与・研究費の目安
| 財源の種類 | 月額給与(目安) | 年間研究費(目安) | 備考 |
| 学振PD | 36.2万円 | 150万円以内 | 研究奨励金として支給 |
| 科研費雇用 | プロジェクトによる(例:PIが年400万円程度負担し、手取り月30万円弱など) | プロジェクトによる | PIの裁量による |
| JST等大型プロジェクト | プロジェクトによる(比較的安定) | プロジェクトによる | プロジェクト目標達成が主 |
| JAXA宇宙航空プロジェクト研究員例 | 年収目安450万円(月額換算約37.5万円) | 個人への支給なし | 手当等あり |
このように、ポスドクの給与は財源によって幅があり、一概には言えません。応募する際には、給与だけでなく研究環境や任期、研究費の有無などを総合的に確認することが重要です。
ポスドクの平均年収や月給は、雇用形態や専門分野、経験年数によって大きな幅があります。
文部科学省科学技術・学術政策研究所の「ポストドクター等の雇用・進路に関する調査(2021年度実績)」によると、月額給与で最も割合が高いのは「35万円以上40万円未満」の層(16.8%)でした。次いで「30万円以上35万円未満」が16.4%となっています。
しかし、一方で「20万円未満」しかもらっていない層も15.2%存在し、過去の調査では調査対象者の半数が月給30万円に届かず、1割は20万円にも達していなかったという報告もあります。さらに深刻なケースとして、3〜4人に1人が月額給与15万円未満または無給で研究活動に従事しているという指摘もあり、2021年度の調査でも11.3%のポスドクが所属先と雇用関係がない(無給の可能性が高い)とされています。
専門分野によっても給与に差が見られ、過去の調査では工学分野が約33万円であるのに対し、人文・社会科学分野は約21万3,000円と低い傾向にありました。
これらの給与水準から生活水準を考えると、月給30万円以上であれば都市部でも単身であれば比較的安定した生活を送れる可能性がありますが、賞与がない場合が多く、任期付きであるため将来的な収入の不安定さは常に付きまといます。月給20万円未満の場合や、家族を養う必要がある場合は、経済的に厳しい状況に置かれることも少なくありません。実際に、ポスドクの約2割がアルバイトなどで収入を補っているというデータもあります。
アメリカのポスドクと比較すると、日本のポスドクの平均給与は低い傾向にあるという指摘もあります。例えば、アメリカのNIH(国立衛生研究所)のポスドクの給与基準は経験年数に応じて定められており、初年度でも年額5万ドルを超えることが一般的です。
ポスドクとして生活していく上では、給与額だけでなく、家賃補助の有無、研究費の使途の自由度なども生活水準に影響を与えるため、総合的な待遇を確認することが重要です。
ポスドクの社会保険や福利厚生の状況は、雇用形態や所属機関によって大きく異なり、必ずしも十分とは言えないのが現状です。
最大の課題の一つは、社会保険への未加入問題です。文部科学省の調査によると、2021年度においてポスドクの32.2%が所属機関の負担による社会保険(健康保険、厚生年金保険など)に加入していませんでした。これは、雇用契約が短期間であったり、非常勤扱いであったり、あるいはそもそも雇用関係がないとされたりする場合があるためです。社会保険に未加入の場合、国民健康保険や国民年金に自身で加入する必要があり、保険料の全額自己負担は経済的な負担増に繋がります。また、厚生年金に加入できないことは、将来の年金受給額にも影響します。
福利厚生に関しても、任期付き研究員であるポスドクは、常勤職員と比較して利用できる制度が限られている場合があります。例えば、通勤手当や住居手当が支給されないケースや、育児休業や介護休業といった制度の利用が難しい、あるいは制度自体が存在しないこともあります。特に女性研究者にとっては、出産や育児に関するサポート体制の不備がキャリア継続の大きな障壁となることがあります。
研究機関によっては、共済組合への加入や、健康診断、保養施設の利用などが可能な場合もありますが、これは雇用主である機関の規定に大きく左右されます。日本学術振興会の特別研究員PDの場合、以前は雇用関係がないため社会保険の適用がありませんでしたが、近年では受入研究機関が希望すれば雇用契約を結び、社会保険に加入できるような制度改善も進められています。
このように、ポスドクの社会保険・福利厚生は不安定な雇用形態と密接に関連しており、生活基盤の脆弱さを示す一因となっています。キャリア選択の際には、給与だけでなく、これらの待遇面もしっかりと確認し、自身のライフプランと照らし合わせて検討することが極めて重要です。
ポスドク期間は一時的なステップと捉えられますが、その後のキャリアは多岐にわたります。アカデミアに残る道、民間企業へ進む道、そして海外での挑戦など、様々な可能性を探ります。
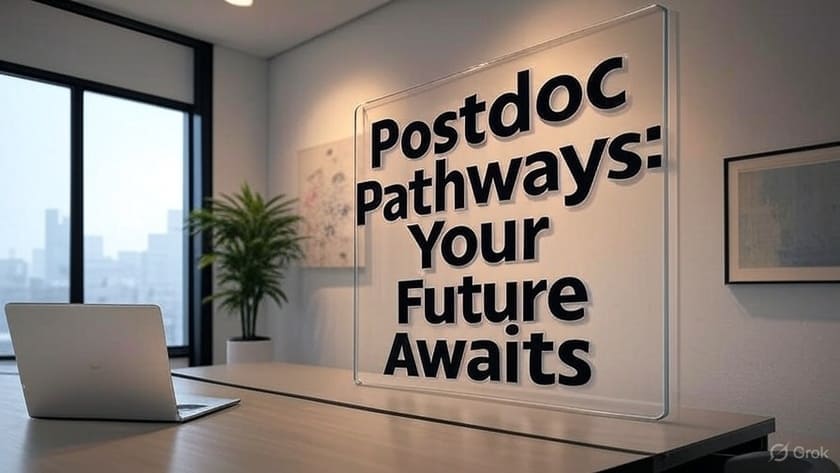
ポスドク後のキャリアとして最も伝統的かつ多くの人が目指すのは、大学や公的研究機関における任期の定めのない常勤教員(テニュアポスト)です。具体的には、助教、講師、准教授、そして教授へとステップアップしていくキャリアパスが一般的です。
ポスドクの経験は、助教のポストに就くための重要な実績として評価されることが多いです。助教は、自身の研究を主導しつつ、学生の教育や指導にも携わるポジションであり、准教授や教授へと繋がるキャリアの第一歩と位置づけられています。
しかし、このアカデミアでのキャリアパスは非常に狭き門となっています。文部科学省の調査(2021年度実績)によると、ポスドクから次年度に大学教員等(助教、助手、講師など)の職に就いたのは全体のわずか9.0%に過ぎません。さらに、これらの大学教員ポストも任期付きである場合が少なくなく、安定した職を得るまでにはさらなる競争が待ち受けています。博士号取得者の増加に対し、大学教員のポスト数は増えていないため、アカデミアにおける常勤ポストの競争率は極めて高いのが現状です。
この厳しい状況は、ポスドクの多くが不安定な任期付きポジションを渡り歩かざるを得ない「ポスドク問題」の核心的な側面の一つです。アカデミアでのキャリアを目指す場合、質の高い研究業績を継続的に上げること、国内外の研究者とのネットワークを構築すること、そして教育経験を積むことなどが求められます。また、近年ではテニュアトラック制度を導入する大学も増えており、これは若手研究者が審査を経て安定的な職を得るための仕組みとして注目されています。
アカデミアのポストが限られている現状を受け、ポスドク修了後のキャリアとして民間企業への就職を選択する人が増えています。博士課程で培った高度な専門知識や研究遂行能力は、多様な産業分野で活かすことが可能です。
主な就職先としては、以下のような分野や職種が挙げられます。
文部科学省も、企業と連携した長期インターンシッププログラムの支援や、博士人材データベース(JGRAD)の運営などを通じて、博士人材の民間企業へのキャリアパス多様化を後押ししています。
民間企業への就職を考える際には、自身の専門性やスキルが企業のどのようなニーズに合致するのかを的確に把握し、アピールすることが重要です。また、アカデミアとは異なる企業文化や評価制度への理解も求められます。「35歳が一つの分かれ目」という指摘もあり、早期からの情報収集と準備が有利に働く傾向があります。
グローバルな視点を持つ研究者にとって、海外でのポスドク経験はキャリアを大きく飛躍させる可能性を秘めています。異文化環境での研究活動は、新たな知見や技術を習得するだけでなく、国際的な人脈形成にも繋がります。
海外ポスドクのメリットとしては、以下のような点が挙げられます。
一方で、デメリットや注意点も存在します。
海外でのポスドクを経験した後のキャリアとしては、日本に帰国して大学や研究機関のポストを目指す、海外でそのまま研究を続ける、あるいは国内外の民間企業に就職するなど、多様な道が開かれています。重要なのは、海外での経験を自身の強みとしてどのように活かしていくかという視点を持つことです。
ポスドクという立場は、多くの可能性を秘めている一方で、深刻な問題も抱えています。ここでは、ポスドクが直面するキャリアの不安や精神的な負担、そして「ポスドク問題」と呼ばれる構造的な課題について掘り下げます。
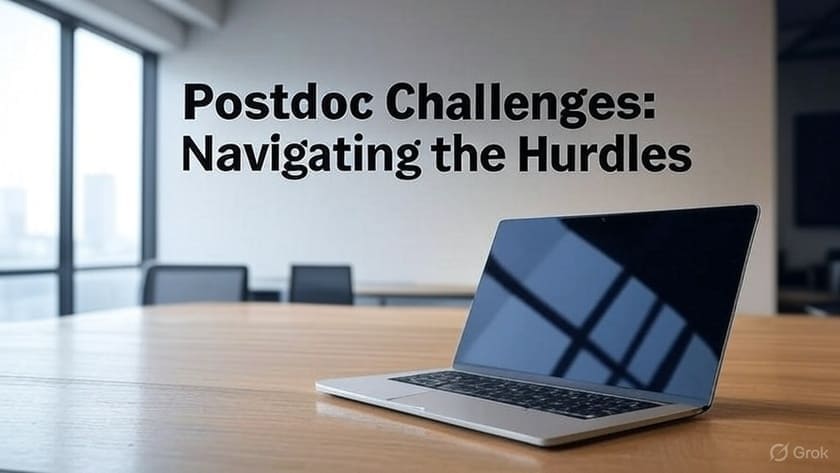
任期満了後のキャリア不安:雇用の不安定さ
ポスドクが抱える最大の悩みの一つが、任期満了後のキャリアに対する深刻な不安と、それに伴う雇用の不安定さです。ポスドクの多くは1年から数年程度の任期付きで雇用されており、任期が終了するまでに次のポジションを見つけなければならないというプレッシャーに常に晒されています。
文部科学省の調査(2021年度実績)によると、ポスドクの任期は「3年未満」が77.0%を占めています。平均雇用期間が1年というデータもあり、常に次の職を探し続けなければならない状況は、研究に集中することを困難にさせます。任期満了後に再任用されるケースもありますが、「任期満了につき雇い止め」となることも多く、次の任用先が決まらなければ無職になる可能性も否定できません。
この雇用の不安定さは、ポスドクの生活設計に大きな影響を与えます。安定した収入の見通しが立たないため、結婚や出産、住宅購入といったライフプランを立てにくいと感じる人も少なくありません。実際に、2021年度の調査では、ポスドクの67.9%が翌年度もポスドクを継続しており、安定した常勤職への移行がいかに難しいかを物語っています。博士課程修了者が非正規雇用から正規雇用へ移行する割合は、他の学歴層と比較して著しく低いというデータもあります。
このようなキャリアの不安と雇用の不安定さは、ポスドクが疲弊し、研究への意欲を削がれる大きな要因となっています。
ポスドクは、研究成果を出すことへの強いプレッシャーと不安定な雇用状況から、ワークライフバランスを保つことが難しく、精神的な負担を抱えやすい傾向にあります。
研究活動は時間的な制約が少なく、成果を出すためには長時間の労働が常態化しやすい環境です。ある調査では、大学の研究者は企業の研究者よりも長時間働き、兼業の割合も高いという結果が示されています。休日が週1回未満であったり、平日睡眠時間が短かったりするポスドクも少なくありません。このような状況は、心身の健康を損なうリスクを高めます。
任期内に成果を上げなければ次のポストがないというプレッシャーは、「このまま研究を続けていけるのだろうか」「次のポストは見つかるだろうか」といった将来への不安を常に抱えさせ、精神的に大きな負担となります。孤独感や他の研究者との比較による劣等感を感じやすい環境も、メンタルヘルスを悪化させる要因となり得ます。
特に女性研究者にとっては、出産・育児といったライフイベントと研究キャリアの両立が大きな課題となります。不安定な雇用形態や長時間労働が前提となる環境では、育児休業の取得や復帰後のキャリア継続が困難な場合が多く、キャリアを断念せざるを得ないケースも見られます。
これらのワークライフバランスの乱れや精神的な負担は、個人の幸福度を低下させるだけでなく、研究活動の質の低下や、優秀な人材がアカデミアから離れてしまう原因ともなり得ます。研究機関における労働時間管理の改善や、メンタルヘルスサポートの充実、そして多様な働き方を許容する環境整備が求められています。
「ポスドク問題」とは、博士号という高度な専門知識と研究能力を持つにもかかわらず、多くのポスドクが不安定な雇用形態、低い経済的処遇、そして将来へのキャリアパスの不透明さといった深刻な困難に直面している状況を指す社会的な課題です。
この問題の背景には、主に以下の構造的な要因が挙げられます。
これらの構造的な課題は、個々の研究者の能力や努力だけでは解決が難しく、優秀な人材の海外流出や、若者の博士課程進学意欲の低下を招き、結果として日本の科学技術力やイノベーション創出能力の低下にも繋がりかねない、国全体の大きな問題として認識されています。
ポスドク問題に関しては以下の記事でより詳しく解説していています。
本記事では、「ポスドクとは何か」という基本的な定義から始まり、その具体的な活動内容、多くの方が気になる給与や経済的な実情、そしてポスドク修了後の多様なキャリアパスについて解説してまいりました。さらに、ポスドクを取り巻く「ポスドク問題」と呼ばれる雇用の不安定さや精神的負担といった構造的な課題にも光を当てました。
博士課程を終え、研究者としての道を歩み始めるにあたり、ポスドクという選択肢がどのようなものであるか、その実態をご理解いただけたのであれば幸いです。確かにポスドクの道は平坦ではなく、多くの課題や困難が伴うことも事実です。しかし、そこで得られる研究経験や専門性は、その後のキャリアにおいてかけがえのない財産となるでしょう。
重要なのは、現状を正確に把握し、自身のキャリアプランを主体的に考え、積極的に行動することです。アカデミア、民間企業、海外と、道は一つではありません。ご自身の探究心と情熱を信じ、未来を切り拓いていかれることを心より応援しております。

研究や論文執筆にはたくさんの英語論文を読む必要がありますが、英語の苦手な方にとっては大変な作業ですよね。
そんな時に役立つのが、PDFをそのまま翻訳してくれるサービス「Readable」です。
Readableは、PDFのレイアウトを崩さずに翻訳することができるので、図表や数式も見やすいまま理解することができます。
翻訳スピードも速く、約30秒でファイルの翻訳が完了。しかも、翻訳前と翻訳後のファイルを並べて表示できるので、英語の表現と日本語訳を比較しながら読み進められます。
「専門外の論文を読むのに便利」「文章の多い論文を読む際に重宝している」と、研究者や学生から高い評価を得ています。
Readableを使えば、英語論文読みのハードルが下がり、研究効率が格段にアップ。今なら1週間の無料トライアルを実施中です。 研究に役立つReadableを、ぜひ一度お試しください!
Readable公式ページから無料で試してみる

東大応用物理学科卒業後、ソニー情報処理研究所にて、CD、AI、スペクトラム拡散などの研究開発に従事。
MIT電子工学・コンピュータサイエンスPh.D取得。光通信分野。
ノーテルネットワークス VP、VLSI Technology 日本法人社長、シーメンスKK VPなどを歴任。最近はハイテク・スタートアップの経営支援のかたわら、web3xAI分野を自ら研究。
元金沢大学客員教授。著書2冊。