
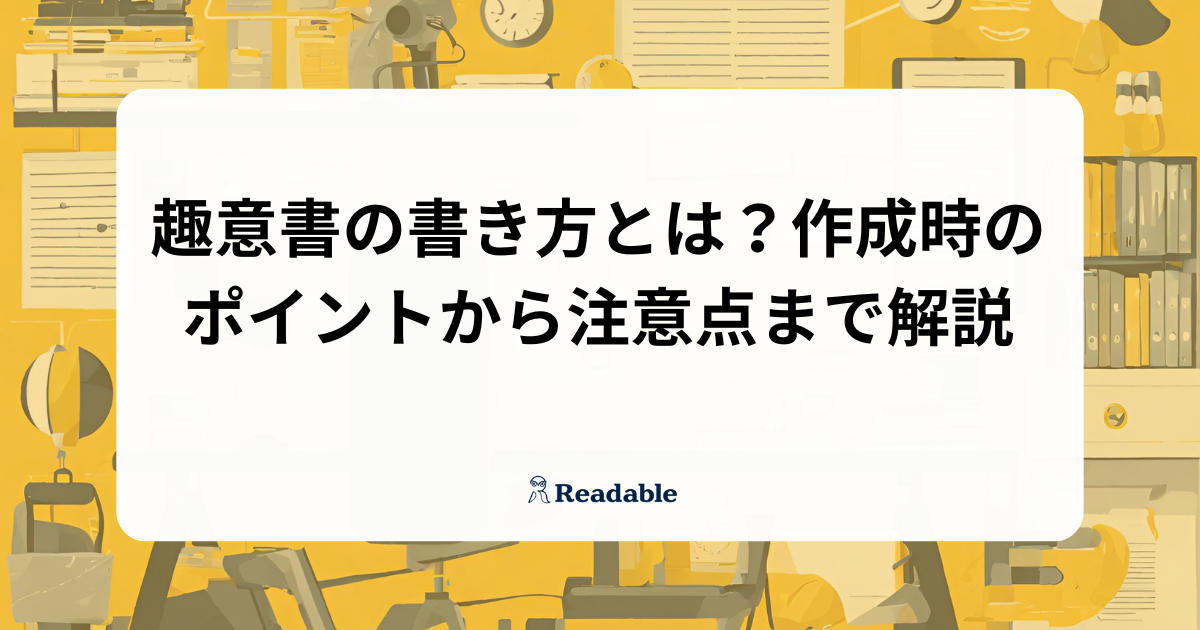
社内外での新規企画案件の上程において、趣意書が必要となることがあります。
趣意書とは、社内外での新規企画案件から、学会や団体の設立時などに広範囲に使用される文書です。学会や団体の設立には、関係者以外に広く趣旨に賛同してもらうため、趣意書の作成がかかせません。また新規の設立ほど重要な事項ではなくても、学会開催時などではなんらかの趣意書作成も大切です。
本記事では、趣意書の書き方について、作成時のポイントから注意点まで紹介します。
目次
趣意書とは、社内の企画プロジェクトや、社外のあらたな事業の提案やイベント開催などに作成されるものです。当該案件の関係者や場合によっては関係者以外の人にも、その計画の趣旨を理解してもらうことを、その目的としています。
趣意書の使用範囲には、会社や団体設立、寄付金募集、各種協力依頼や学会開催などがあります。これらの趣旨に賛同してもらうために作成する文書であり、特に寄付をお願いする場合や、団体の設立の際には、それに共感してもらえるように趣意書を作成しなければなりません。
趣意書には、活動の背景や目的、期待する効果、実施方法が記載されており、関係者の賛同を得る上で重要な役割を果たします。法人や団体の設立などでも広く使用されており、説得力のある内容が求められます。特に会社や組合を設立する際には、設立趣意書として、ほぼ必ず作成が必要となります。当該関係者や組合員に趣旨を説明し、賛同や経済的支援を得るために役立つ場合が多くなっています。
また趣意ではなく主意を用いる、質問主意書と呼ばれるものもありますが、これは質問内容を分かりやすくまとめたものです。それに対して趣意書とは、たとえば学会の開催に際し支援をお願いするために、趣旨を記載したものになります。
それでは関係者から賛同や協賛を得るためには、趣意書はどのように記載すべきなのでしょうか。
たとえば学会開催などでの趣意書の記載内容は、以下のようになります。
1. 時候などを含めた挨拶
2. 当該の学術団体などの紹介
3. 趣意書の目的と内容
4. 開催場所や時期などの説明
なお趣意書には決まったフォーマットは特にはないので、記載の順番や内容にも決まりはありません。基本的には上記の流れで作成されている場合が多く、読みやすい流れになっていることが大切です。
文章の構成が明確でないと、読み手に趣旨が伝わりにくく、読みづらい文書となってしまいます。このため、あらかじめ大見出しや小見出しなどをつけて、見出しごとに分けて作成すると、読みやすい趣意書になります。
◇ ご協力のお願いを記載する
特にお願いを記載することが大切です。学会開催であれば、その目的や、開催する学術大会のテーマ、そして協賛の依頼などを記載します。たいていの場合は、当該大会の開催代表者が既に設定されており、この方の名前でお願いを記載します。
◇ 開催概要を記載する
大会などの日時や大まかなプログラムなど、開催概要を記載します。たとえば前年度の実績から推定した、おおよその大会参加人数を記しておくと、趣意書をもらう企業としては判断がしやすくなります。
なお大会の実行委員会組織を記載し、抄録への広告掲載や、ランチョンセミナーや企業展示などの募集要項も記載するようにします。また、当該の申込書フォーマットも必ず添付しておきます。
趣意書作成のポイントとしては、どのような点に気をつければよいでしょうか。
趣旨説明は、具体的に記載することが重要で、学術団体の紹介から、大会の趣旨までわかりやすく記載します。先ほど記載したように、広報部門など技術系でなくても理解できるように作成しましょう。趣旨が伝わらないと、賛同者を多く集めることができないので、重要な部分は、より明確にすることが大切です。
また丁寧な表現を用いれば、趣意書を受け取る企業などへの敬意が伝わり、支援の意思決定もスムーズになると思われます。趣意書とは、活動の目的や意義を伝えて賛同を得るための文書です。丁寧な言葉で分かりやすく記載し、必要な情報を網羅することで、関係者の協力も得やすくなります。
資金支援をお願いする場合は、その理由を具体的に記載することが重要です。どのような目的でその資金が必要なのかや、具体的な使用用途など、企業などでも納得しやすい説明を心がけます。当該大会の説明だけではなく、当該団体の説明も明確にしましょう。また予算書なども添付すれば、その金額や使途が明確になり、支援を検討してもらいやすくなります。できるだけ具体的な情報を提供することが大切です。
資金支援や現物などの援助をお願いする場合は、予算書などの資料も参考として添付しておくのがポイントです。具体的な金額や内容が把握できると、読み手もある程度の状況を把握しやすくなり、検討しやすくなります。
趣意書は、大会ホームページに掲載しダウンロードしてもらう形式も使用されます。ただ依頼される企業も、たいていは広報部門が窓口となり、当該大会に特に詳しい訳ではありません。このため大会ホームページをみてほしいといった旨だけ記載した趣意書がないわけではありませんが、これはあまりおすすめできません。紙の文書やメール案内の場合にも、すぐ当該案内の詳細がわかる方が親切です。
趣意書作成時の注意点としては、下記のようになります。
趣意書の説明に矛盾や重複があると、信頼度が低くなるなど、読み手の興味をなくしてしまう場合があります。趣意書チェックのときには、誤字脱字はもちろんですが、矛盾点や重複がないかも必ずチェックするようにしましょう。
趣意書作成はひとりで行っても、チェックは他の人に、できれば複数人にしてもらうことをおすすめします。自分では気づかなかった誤字脱字、矛盾点や重複などが指摘されやすくなる効果があります。さらに追加した方が良い内容や、他の関係者からのアドバイスをもらうことにより、より良い趣意書を作成することができます。
趣意書は、敬語などを使用する丁寧な言葉遣いを意識することが大切です。趣意書では謹啓、敬白を活用するなど、より丁寧な表現が適しています。また、ご協力を賜りますようお願い申し上げますなど、より改まった表現を使用することで、依頼内容が伝わりやすくなります。
趣意書とは、お願いをするために作成する文書ですので、より丁寧な文書にすることがポイントです。最近は電子メール等で簡素な形式が多用されていますが、敬語の使用には特に気をつけましょう。理系の学術団体であっても、敬語の使用法がしっかりしていると広報部門の人などには、しっかりとした団体であると認められる可能性も高くなります。
趣意書の書き方について、その目的から作成時のポイントや注意点まで紹介しました。
趣意書とは、賛同してもらうプロジェクトや団体活動などの目的や意義を関係者に伝えるための重要な文書です。学術団体などの新規事業の提案や学術大会の開催時に使用され、関係者を得るために作成されます。また新しい学会や団体の設立には、関係者以外に広く趣旨に賛同してもらうため、趣意書作成は必須となります。
趣意書の作成は、学術論文などとは異なり、ご協力をお願いすることが主眼です。このため、趣意の内容を明確に記載することが大切ですが、賛同を得るためには、適切な敬語等も使用し、できるだけ丁寧な文書にしましょう。
本記事が、これから趣意書などを作成する方々のお役に立てば幸いです。

研究や論文執筆にはたくさんの英語論文を読む必要がありますが、英語の苦手な方にとっては大変な作業ですよね。
そんな時に役立つのが、PDFをそのまま翻訳してくれるサービス「Readable」です。
Readableは、PDFのレイアウトを崩さずに翻訳することができるので、図表や数式も見やすいまま理解することができます。
翻訳スピードも速く、約30秒でファイルの翻訳が完了。しかも、翻訳前と翻訳後のファイルを並べて表示できるので、英語の表現と日本語訳を比較しながら読み進められます。
「専門外の論文を読むのに便利」「文章の多い論文を読む際に重宝している」と、研究者や学生から高い評価を得ています。
Readableを使えば、英語論文読みのハードルが下がり、研究効率が格段にアップ。今なら1週間の無料トライアルを実施中です。 研究に役立つReadableを、ぜひ一度お試しください!
Readable公式ページから無料で試してみる
都内国立大学にて、研究・産学連携コーディネーターを9年間にわたり担当。
大学の知財関連の研究支援を担当し、特にバイオ関連技術(有機化学から微生物、植物、バイオ医薬品など広範囲に担当)について、国内外多数の特許出願を支援した。大学の先生や関連企業によりそった研究評価をモットーとして、研究計画の構成から始まり、研究論文や公募研究への展開などを担当した。また日本医療研究開発機構AMEDや科学技術振興機構JSTやNEDOなどの各種大型公募研究を獲得している。
名古屋大学大学院(食品工業化学専攻)終了後、大手食品メーカーにて31年間勤務した経験もあり、自身の専門範囲である発酵・培養技術において、国家資格の技術士(生物工学)資格を取得している。国産初の大規模バイオエタノール工場の基本設計などの経験もあり、バイオ分野の研究・技術開発を得意としている。
学位・資格
博士(生物科学):筑波大学にて1994年取得
技術士(生物工学部門);1996年取得