
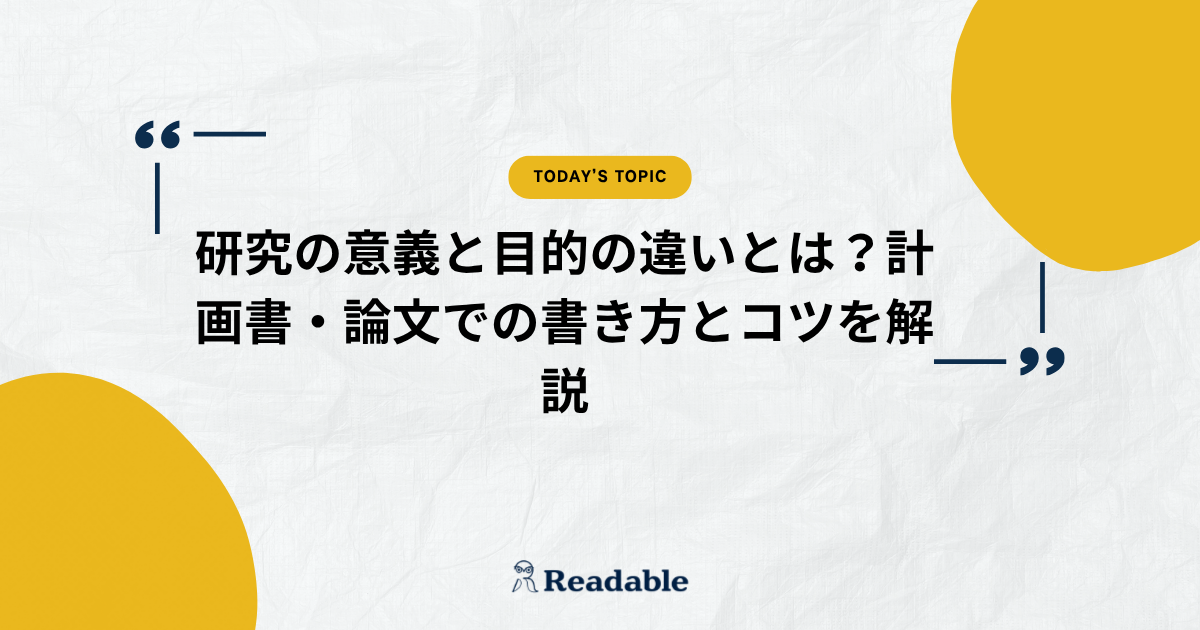
研究計画書や論文で『研究の意義』を書くように言われたけれど、『目的』とどう違うのだろう?自分の研究の価値を、どうすれば審査員や指導教官に説得力をもって伝えられるのか?
研究を進める多くの学生や若手研究者が、一度はこのような壁に突き当たります。この二つの概念の混同は、研究計画全体の説得力を弱めかねない重要な問題です。この記事では、その根本的な違いの解説から、評価される計画書・論文を書くための実践的なステップ、さらには具体的な例文まで、あなたの悩みを解決するための全てを解説します。
目次

研究の目的とは、その研究を通じて最終的に「何を明らかにするのか」、あるいは「何を実現するのか」という具体的な到達点、つまりゴールを指し示すものです。これは、「この研究は何をしますか?」という問いに対する、直接的かつ明確な答えに他なりません。
研究計画書においては、この目的が研究全体の方向性を定める羅針盤の役割を果たします。なぜなら、目的を具体的に設定することで、研究の範囲が明確になり、どのような手法でゴールを目指すのかという具体的な計画を立てるための土台となるからです。
研究における目的は、一つの大きな目標から、それを達成するための小さな目標まで、いくつかの階層で構成されることがあります。例えば、以下のような階層構造が考えられます。
このように、壮大なビジョンから、自身の研究で直接的に取り組む具体的なゴールまでを意識することが重要です。
具体的な事例を見てみましょう。看護研究の分野では、「終末期がん看護に携わる当院一般病棟の看護師が感じるストレス要因を明らかにすること」といった記述が研究目的にあたります。これは、この研究が達成しようとしている具体的なゴールを明確に示しています。同様に、農業分野の研究では、「ドローンによる自動農薬散布を実現する」というのも目的の一例です。この目的を達成するために、AIの画像認識技術を開発するといった具体的な研究計画が立てられます。
したがって、研究目的を記述する際は、自身の研究が具体的に「何を」解明し、どのような状態を実現しようとしているのかを、簡潔かつ明確な言葉で示すことが求められます。あまり長く書く必要はなく、「この研究の目的は、・・・を明らかにすることである」といった簡潔な一文でも十分に伝わります。
研究の意義とは、その研究自体が持つ価値や、研究を行うことで社会や学術分野にどのような変化や影響をもたらすのかを説明するものです。目的が研究の「What(何を)」を指し示すのに対し、意義は「Why(なぜ)」、つまり「なぜその研究が重要なのか?」という問いに答える役割を担います。研究の価値を外部に伝え、その正当性を担保する上で極めて重要な要素です。
なぜなら、研究費の審査員や学術誌の査読者は、研究計画や論文の細部すべてに目を通す時間がない場合、この「意義」の部分を読んで、その研究が重要である理由や、結果が誰にとって意味深いものかを判断する傾向があるからです。また、研究は対象者に負担をかける可能性もあるため、その負担を上回る価値があることを示す倫理的な妥当性の観点からも、意義の明確化は不可欠です。
具体的な事例で考えてみましょう。前述の看護研究の例で、目的が「看護師のストレス要因を明らかにすること」であったのに対し、その意義は「看護師のストレス軽減、ひいては患者ケアの質向上につながることが期待される」ことになります。
目的の達成が、結果としてどのようなポジティブな影響を生むのかを示しているのです。また、医学の分野で「新しい抗生物質を発見する」という研究が行われた場合、その臨床的な意義は「病原菌の感染を以前よりも早く治療できるようになる」ことです。
このように、研究の意義は、研究成果がもたらすより広範な価値や重要性を説明する役割を担います。その貢献の方向性は、主に以下の二つに大別されます。
結論として、研究の意義を記述することは、自身の研究が単なる自己満足ではなく、学術コミュニティや社会全体にとって価値ある取り組みであることを論理的に証明する行為なのです。
研究の「目的」と「意義」は、それぞれ独立した概念ではなく、密接に関連し合っています。この二つの関係性を端的に表現するならば、目的は「研究プロジェクトの内部で達成すべき具体的なゴール」であり、意義は「そのゴール達成がプロジェクトの外部世界に対して持つ価値の表明」と言えるでしょう。この「内部の論理」と「外部への正当化」というフレームワークで捉えることで、両者の関係性がより明確になります。
目的がなければ、研究は方向性を見失い、何をすべきかが分からなくなります。一方で、意義がなければ、なぜその研究に時間や資金といったリソースを投じるべきなのか、その正当性を他者に説明することができません。優れた研究計画とは、この内部的なゴール設定と、外部への価値説明が、説得力のあるストーリーとして一貫しているものです。
この関係性をより深く理解するために、異なる分野の具体例を比較してみましょう。ここでは、前述の「農業用ドローン」と「看護研究」の例を使い、目的と意義がそれぞれどのような役割を果たしているのかを表で整理します。
| 研究分野 | 目的(What:何を明らかにするか) | 意義(Why:なぜそれが重要か) |
| 農業 | AIの画像認識による自動運転ドローンを開発し、農薬散布を自動化する | 農業従事者の労働力不足を解消し、持続可能な農業の実現に貢献する |
| 看護学 | 一般病棟看護師が終末期がん看護に対して感じるストレス要因を明らかにすること | 看護師のストレスを軽減し、それによって患者ケアの質向上につなげること |
この表から分かるように、「目的」は研究者が直接的に取り組む、具体的で測定可能なタスクを記述しています。ドローンの開発や、ストレス要因の特定は、研究の範囲内で達成可能なゴールです。
それに対して「意義」は、その目的が達成された結果として生じる、より広範で長期的なインパクトを説明しています。労働力不足の解消や患者ケアの質の向上は、研究成果が社会にもたらす価値そのものです。
このように、目的と意義をセットで考える思考プロセスは、自身の研究計画を構造化し、その価値を多角的に捉えるための強力なツールとなります。まず、研究の内部的なゴール(目的)を明確に定義し、次に、なぜプロジェクト外部の人間がその結果に関心を持つべきか(意義)を論理的に説明する。このプロセスを経ることで、研究計画の説得力は飛躍的に高まるのです。

研究の意義を構成する一つ目の柱は「学術的貢献」です。これは、あなたの研究が所属する専門分野の知識体系、すなわち「学術」に対して、どのような新しい価値をもたらすのかを示すものです。
学術研究の本質は、未知の事柄を解明し、新しい知識を発見することにあります。したがって、学術的貢献を語ることは、自身の研究が人類の知のフロンティアをいかに押し広げるのかを宣言する行為に他なりません。
なぜ学術的貢献が重要なのでしょうか。それは、学術が先行研究の積み重ねの上に成り立っているからです。あなたの研究は、無数の先人たちが築き上げてきた知識の体系に、新たな一つのブロックを加える試みです。そのブロックが、既存の知識とどう関連し、どのような新規性(オリジナリティ)を持つのかを明確にしなければ、研究の価値は誰にも理解されません。オリジナリティを尊重する姿勢は、分野や領域が異なっても、あらゆる学術分野に共通する価値観なのです。
学術的貢献には、具体的にいくつかの形態があります。自身の研究がどれに当てはまるかを意識することで、意義をよりシャープに記述できます。
例えば、物理学の研究者が「ものごとを数理的に整理して、統一的に理解していくこと。その結果を論文として発表することで、人類共通の知識となります」と語るように、個々の研究成果は論文という形で公表され、人類共通の知的財産として蓄積されていきます。
結論として、学術的貢献を明確に記述することは、自身の研究が専門分野という広大な知の地図の中で、どの位置にあり、どのような独自の価値を持つのかを力強く示すために不可欠です。
研究の意義を構成する二つ目の柱は「社会的貢献」です。これは、研究成果が学術コミュニティという枠を超えて、広く社会全体や人々の生活に対して、どのような良い影響を及ぼすのかを示す視点です。
研究は、単に知的好奇心を満たすだけでなく、人類の文化・文明の進歩に貢献するという大きな目的を持っています。社会的貢献を明確にすることは、その研究が実社会の課題解決にどう寄与するのかを具体的に示す行為です。
研究が社会に貢献する形は多岐にわたります。自身の研究が、どのような形で社会にポジティブな変化をもたらす可能性があるのかを具体的にイメージすることが重要です。社会的貢献の典型的な例としては、以下のようなものが挙げられます。
例えば、心理学の研究は、人々のメンタルヘルスを改善し、生活の質(QOL)の向上に直接的に貢献する可能性があります。また、自然科学の研究は、自然の法則や原理を解明することを通じて、私たちの生活を豊かにする新しい技術やサービスを生み出す基盤となります。これらの研究は、その成果が社会に還元されることで、大きな価値を生むのです。
研究成果がもたらす意義は、基礎的なデータや結果の範囲を超えて、他の研究者やその分野の関係者、そして一般の人々に研究の重要性を説明するものです。したがって、自身の研究が、どのような社会的課題に関心を持ち、その解決に向けてどのような貢献ができるのかを明確に言語化することは、研究費の申請や社会からの理解を得る上で極めて重要になります。
研究の社会的貢献を意識することは、研究者としての視野を広げ、研究の価値を最大化することにつながるのです。
「私の研究は、直接的な社会応用を目的としない基礎研究だから、社会的貢献なんて書けないのでは?」と考える研究者もいるかもしれません。しかし、一見すると社会との接点が見えにくい基礎研究にも、学術的貢献と将来的な社会的貢献という両面で、計り知れないほど大きな意義が内在しています。この二つの貢献は排他的なものではなく、むしろ深く結びついているのです。
多くの基礎研究は、研究者自身の「とにかく明らかにしたいこと、知りたいことがある」という純粋な知的好奇心によって駆動されています。その探求は、必ずしも特定の社会課題の解決を直接の目的とはしていません。しかし、歴史を振り返れば、社会を根底から変えるようなイノベーションの多くが、このような基礎研究の予期せぬ成果から生まれているという事実は、繰り返し証明されてきました。
例えば、ある物理学者は自身の研究を「散らかった部屋をきちんと整理整頓するように、ものごとを数理的に整理して、統一的に理解していくこと」と表現しています。このような純粋な学術的探求の積み重ねが、人類共通の知識となり、時間を経て熟成されることで、社会を一変させるような技術が生まれてくるのです。学術的貢献と社会的貢献の関係性を整理すると、以下のようになります。
| 貢献の種類 | 焦点 | 具体例 |
| 学術的貢献 | 専門分野内の知識の進展(知的好奇心に基づく探求) | 新しい数理モデルの構築、未発見の素粒子の予測、生物の新たな遺伝子機能の解明 |
| 社会的貢献 | 実社会への影響・還元(学術的貢献の長期的・予期せぬ応用) | GPS技術、インターネット、mRNAワクチン、新素材の開発 |
このように、今日の社会を支える多くの技術は、過去の基礎研究という土台の上になりたっています。基礎研究の営みは、すぐには目に見える形にはならなくても、回り回って社会に大きな変革をもたらし、人々の生活を支えているのです。
したがって、基礎研究に従事する研究者であっても、自身の研究の意義を自信を持って語るべきです。その研究が、人類の知識体系をどのように豊かにするのか(学術的貢献)、そしてその知の蓄積が、長期的視点でどのような社会的価値を生み出す可能性を秘めているのか(将来的な社会的貢献)。この両面を言語化する能力は、研究費を申請する際や、社会からの理解と支援を得る上で、極めて重要なのです。

説得力のある「研究の意義」を記述するための最初の、そして最も重要なステップは、先行研究を徹底的にレビューし、広大な学術の領域の中で自身の研究がどのような「位置づけ」にあるのかを明確にすることです。
これは、いわば研究の世界における住所を特定する作業です。この位置づけが曖昧なままでは、どれだけ素晴らしい主張をしても、それは根拠のない独り言になってしまいます。
なぜなら、研究の価値は、既存の知識体系との関係性の中で初めて生まれるからです。先行研究を整理する目的は、その分野で「何がすでに明らかにされており、何がまだ解明されていないのか」という知識の最前線、すなわち「リサーチ・ギャップ」を特定することにあります。そして、この「まだ誰も答えを出していない問い」こそが、あなたの研究が存在する理由、つまり研究の必要性そのものになるのです。
先行研究を整理し、リサーチ・ギャップを見つけ出すためには、いくつかの批判的な視点を持つことが有効です。
これらの視点から既存の研究を丹念に読み解くことで、自身の研究が貢献できる独自の切り口が見えてきます。そして、その位置づけを文章で表現する際には、効果的な構文があります。それは、「これまでの研究は〇〇であった。これに対して、本研究は〇〇を〇〇するものである。」という型です。この構文は、先行研究の到達点と限界(踏み台)を簡潔に示した上で、それに対して自身の研究がどのような新しい一歩を踏み出すのかを明確に対比させることができます。
このように、先行研究の海の中で自らの研究を正確に位置づける作業は、説得力のある意義を記述するための揺るぎない土台を築くために、決して欠かすことのできないステップなのです。
研究の位置づけを明確にしたら、次のステップは、その研究の価値を読者に納得させるための「説得」のプロセスに入ります。研究の意義を記述する行為は、単なる事実の客観的な描写ではありません。それは、研究費の審査員、学術誌の査読者、指導教官、あるいは倫理審査委員会の委員といった、あなたの研究の価値を判断し、その実行を承認する権限を持つ人々を説得するための、情熱的なプレゼンテーションなのです。
この「説得」というマインドセットを持つことが極めて重要です。なぜなら、研究の実行には、多くの場合、資金や設備、倫理的な承認といった他者からのリソース提供や許可が必要となるからです。
読者は、「なぜ数ある研究テーマの中から、この研究が重要なのか」「なぜ提案されているアプローチが優れているのか(筋が良いのか)」、そして「その研究は倫理的に妥当なのか」といった問いに対する、論理的で納得のいく答えを求めています。
例えば、患者さんや一般の方を対象とする研究(特に看護学や医学、心理学など)では、倫理的な妥当性を示すことが強く求められます。研究は、参加者に少なからず時間的・身体的・精神的な負担をかける可能性があります。そのため、その負担を上回るだけの重要な意義、つまり研究の有効性(例えば、看護実践へのインパクトや患者のQOL向上への寄与など)があることを、倫理審査委員会に対して明確に伝え、納得してもらわなければなりません。効果が期待できない研究や、意義が乏しい研究は、倫理的に実施が許可されない可能性もあるのです。
この「説得」という意識を持つことで、文章の表現は大きく変わります。単に「本研究は〇〇を明らかにすることを目的とする」と記述するだけでは不十分です。そうではなく、「〇〇という未解明の問題を本研究で明らかにすることは、△△という学術的な課題の解決に大きく貢献する。ひいては、□□という喫緊の社会問題の改善にもつながるため、本研究は今まさに取り組むべき高い価値を持つ」というように、因果関係と価値判断を明確に含んだ、より力強い主張を構築することが可能になります。
研究の位置づけを固め、説得力のある論点を構築したとしても、それが読者に伝わらなければ意味がありません。最終ステップは、その熱意と論理を、誰が読んでも理解できる「簡潔で分かりやすい言葉」で表現する技術です。特に、研究の意義を説明するセクションは、専門外の読者の目にも触れる可能性が高い部分であるため、このステップの重要性は計り知れません。
なぜ簡潔さが重要なのでしょうか。それは、研究の価値を伝えようとするあまり、文章が冗長になったり、専門用語を多用したりすると、かえって要点が曖昧になり、読者に最も伝えたい核心が伝わらなくなってしまうからです。
研究計画書はスペースが限られていることも多く、要点を絞って記述する能力が求められます。また、あなたの計画書を読むのは、同じ分野の専門家だけとは限りません。例えば、倫理審査委員会の委員には、法律家や一般市民など、多様なバックグラウンドを持つ人々が含まれています。彼らに研究の価値を理解してもらうためには、専門的な「内輪の言葉」を避け、平易な表現を心がける必要があります。
効果的な記述のためには、以下のポイントを意識すると良いでしょう。
結論として、研究の意義を記述する最終段階では、一度専門家としての視点から離れ、「どうすればこの研究のワクワクするような価値を、専門外の人にも伝えられるだろうか」と自問することが鍵となります。その問いから生まれる簡潔で分かりやすい言葉こそが、あなたの研究の価値を届けてくれるのです。
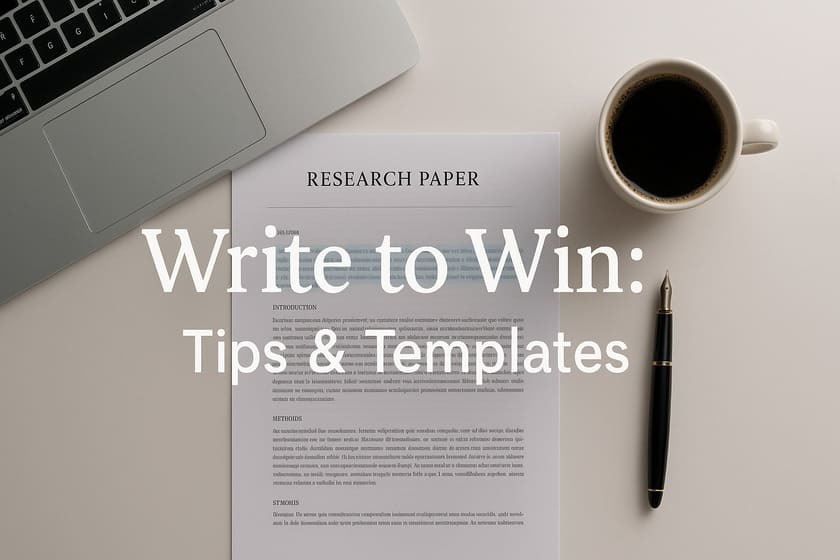
研究の意義をゼロから書き出すのは難しいと感じるかもしれません。しかし、優れた研究計画書や論文には、効果的に意義を伝えるための共通した「型」や「定型表現」が存在します。これらの構文を知識として持っておくことで、自身の研究内容に合わせて応用するだけで、論理的で説得力のある文章を効率的に作成することができます。
これらの定型表現は、単なる言葉のテンプレートではありません。それぞれの表現が、研究の価値を特定の角度から照らし出す機能を持っています。例えば、将来的な貢献の可能性を示唆したり、先行研究との対比を明確にしたりと、目的に応じて使い分けることが重要です。
ここでは、様々な場面で活用できる、研究の意義を記述する際の代表的な定型表現と構文を紹介します。
これらの表現を自身の研究計画に当てはめてみましょう。例えば、「これまでの研究はAという側面からの分析が主流であった。これに対して、本研究はBという新たな手法を用いることで、これまで見過ごされてきたCのメカニズムを解明するものである。この成果は、Dという学術分野の議論を深めるだけでなく、将来的にはEという社会問題の解決に向けた新たな示唆を与えることができるだろう。」
このように、定型表現を組み合わせることで、研究の位置づけ、独自性、そして多角的な貢献を構造的に示すことが可能になります。
「研究の意義」は、研究計画書で書く場合と、研究が完了した後に論文で書く場合とでは、その目的と読者が異なるため、表現のニュアンスや強調すべきポイントが微妙に異なります。この違いを理解し、書き分けることで、それぞれの文書の説得力を最大限に高めることができます。
最も大きな違いは「時間軸」です。研究計画書は「未来」に行う研究の価値を説明し、実行の承認や予算の獲得を目指す「提案書」です。そのため、研究がもたらすであろう「可能性」や「期待」を強調する未来志向の記述が中心となります。
一方、論文は「過去」に完了した研究の成果を報告し、その知見が学術的にどのような価値を持つのかを確定的に示す「報告書」です。こちらは、研究によって実際に得られた「事実」と「確かな貢献」を記述することが中心となります。
この違いをより具体的に理解するために、両者の特徴を比較してみましょう。
| 研究計画書における意義 | 論文における意義 | |
| 目的 | 研究の実行許可や予算獲得のための「説得」 | 研究成果の価値を位置づけ、読者に「報告」 |
| 時間軸 | 未来(これから行う研究) | 過去(完了した研究) |
| 表現 | 推量形・期待(〜が期待される、〜に貢献できるだろう、〜の可能性がある) | 断定形・事実(〜を明らかにした、〜という点で意義がある、〜に貢献した) |
| 強調点 | 研究がもたらす「ポテンシャル」や「将来性」 | 研究によって得られた「新たな知見」や「確定的な貢献」 |
この違いを踏まえて、同じ研究テーマに関する意義の記述が、研究計画書と論文でどのように変わるかを見てみましょう。
このように、研究計画書では「可能性」や「期待」といった言葉で未来の価値をアピールするのに対し、論文では「明らかにした」「提供する」といった断定的な言葉で、研究が達成した確定的な価値を報告します。このニュアンスの違いを意識することが、それぞれの文書の目的に沿った、より効果的なコミュニケーションにつながるのです。
研究の意義を記述する際には、その価値を正しく伝えられなくするだけでなく、審査員や読者に準備不足や未熟な印象を与えてしまう、いくつかの典型的な「失敗パターン」が存在します。意図せずこれらの罠に陥ることを避けるため、事前に代表的な失敗例とその改善策を理解しておくことは非常に重要です。
これらの失敗は、多くの場合、「目的」と「意義」の違いを十分に理解できていないことや、自身の研究を客観的に位置づける作業が不足していることに起因します。以下に挙げるNG例を反面教師として、自身の記述をチェックしてみましょう。
これらの失敗例を避けるだけで、あなたの研究計画書や論文の質は格段に向上します。常に客観的な視点を持ち、具体的で論理的な記述を心がけることが、説得力のある「研究の意義」を書き上げるための鍵となります。
「研究の目的と意義の違いが分からない」「どう書けば価値が伝わるのか」といった執筆当初のお悩みは、この記事を通じて解消できたのではないでしょうか。
本記事では、まず「目的(何を)」と「意義(なぜ)」の根本的な違いを具体例と共に解き明かしました。
次に、研究の価値を「学術的貢献」と「社会的貢献」という2つの柱で捉える視点を提示し、最後に、先行研究の整理から説得力のある文章作成まで、実践的な3つのステップと具体的なコツを解説しました。
研究の意義を自分の言葉で明確に言語化する力は、単に計画書や論文を書き上げるためのテクニックではありません。それは、自身の研究の価値を深く理解し、その進むべき道を示す羅針盤を手に入れることであり、あなたの研究活動全体を前進させる強力なエンジンとなります。
自信を持って、あなたの研究が持つ素晴らしい価値を、論理的かつ情熱的に世界へ示してください。

研究や論文執筆にはたくさんの英語論文を読む必要がありますが、英語の苦手な方にとっては大変な作業ですよね。
そんな時に役立つのが、PDFをそのまま翻訳してくれるサービス「Readable」です。
Readableは、PDFのレイアウトを崩さずに翻訳することができるので、図表や数式も見やすいまま理解することができます。
翻訳スピードも速く、約30秒でファイルの翻訳が完了。しかも、翻訳前と翻訳後のファイルを並べて表示できるので、英語の表現と日本語訳を比較しながら読み進められます。
「専門外の論文を読むのに便利」「文章の多い論文を読む際に重宝している」と、研究者や学生から高い評価を得ています。
Readableを使えば、英語論文読みのハードルが下がり、研究効率が格段にアップ。今なら1週間の無料トライアルを実施中です。 研究に役立つReadableを、ぜひ一度お試しください!
Readable公式ページから無料で試してみる

東大応用物理学科卒業後、ソニー情報処理研究所にて、CD、AI、スペクトラム拡散などの研究開発に従事。
MIT電子工学・コンピュータサイエンスPh.D取得。光通信分野。
ノーテルネットワークス VP、VLSI Technology 日本法人社長、シーメンスKK VPなどを歴任。最近はハイテク・スタートアップの経営支援のかたわら、web3xAI分野を自ら研究。
元金沢大学客員教授。著書2冊。