
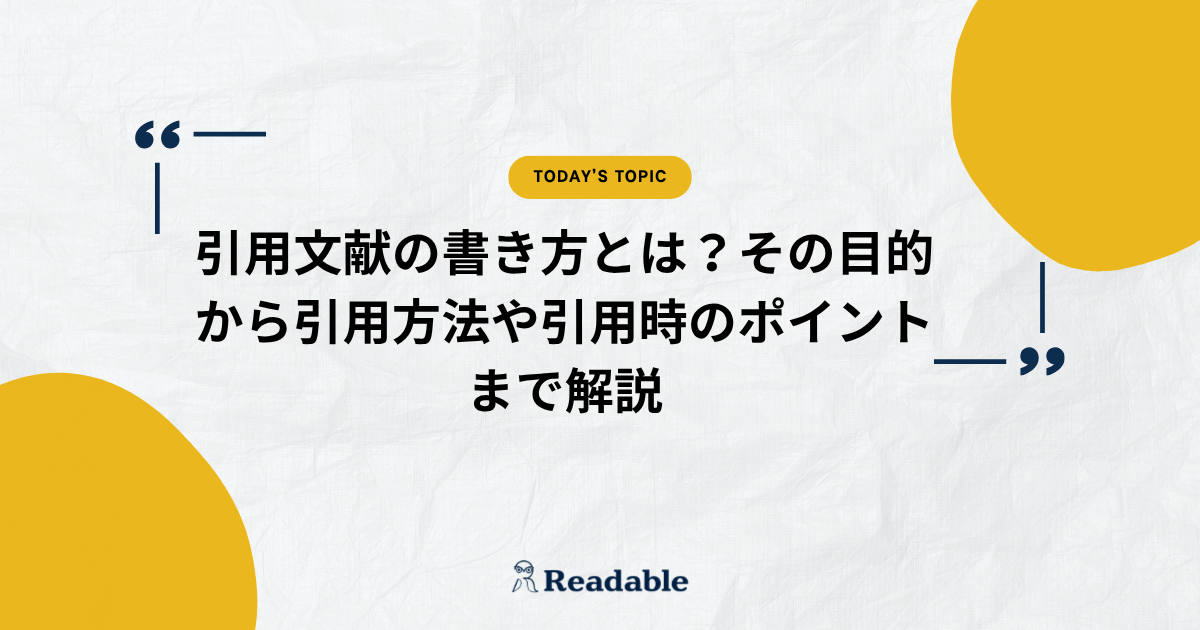
引用文献とは、研究論文などを作成する場合に避けて通れない資料となっています。
引用とは、どこから引用してきたのか、その出典を明示することです。他の研究論文に書かれていることを、自身の論文で用いる場合には適切な手順が必要となります。また他の著作物に書かれているデータや方法などを参考にした場合も同じです。
本記事では、引用文献の書き方について、その目的から引用方法や引用時のポイントまで解説します。
目次
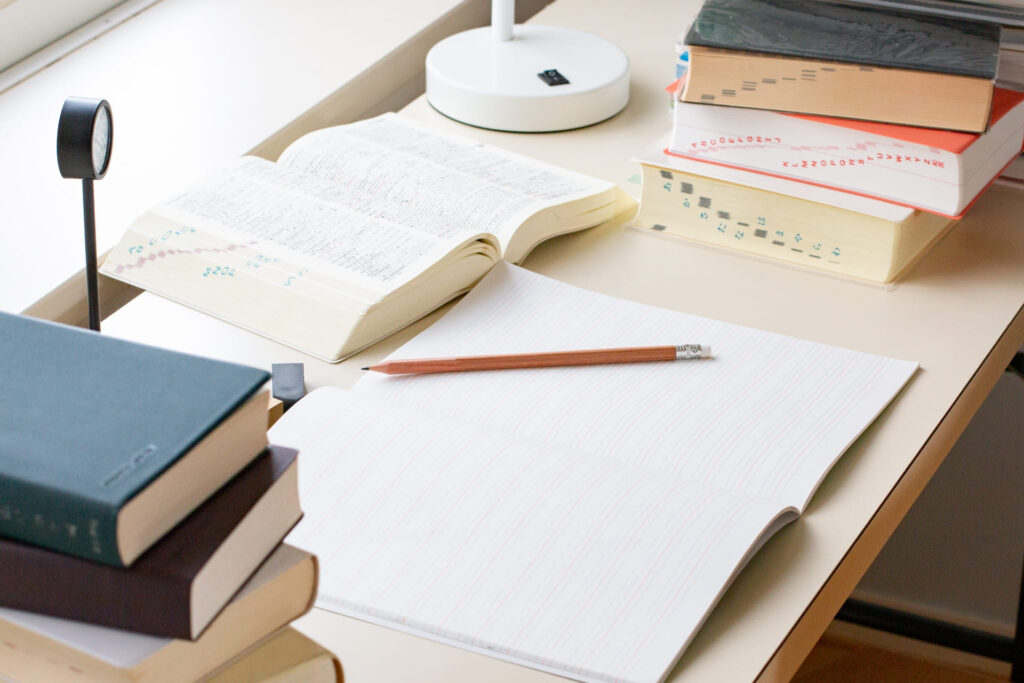
引用文献の選定やその記載は、研究論文の執筆にはさけては通れない作業です。
たとえ論文作成自体の目的が、新規性を追及するものであったとしても、新しい発見は既存の研究成果を前提に成立するものです。まして、従来の研究からの改善点を訴求するような論文の場合は、既存文献の考察と引用が欠かせないものとなります。
研究論文では、通常の場合、研究背景、研究方法、研究結果や考察などの項目にわけて執筆されますが、研究結果などの一部を除いて、いろいろな段階で、引用文献を参照しなければならないことがあります。
研究背景やさらには考察の部分では、自身の研究テーマと従来からの研究成果との比較作業を行います。自分の研究テーマのオリジナリティを実証するには、他者の研究との比較作業が求められます。オリジナリティの程度はありますが、いずれにせよ既存研究との比較や区分が重要になります。自分が採用した手法などについては、たとえば既存文献からその一部を抜粋して、実験方法を組み立てます。このような場合、必ず既存文献を引用文献として、自身の研究論文の中にも記載しなければなりません。
研究論文に記載すべき既存文献の引用目的についても考えてみます。
従来のこれまでの研究をふまえて、自身の研究も成り立っており、その研究成果が最終的に自身の論文となっています。これまでの先行研究をふまえることと、自身の研究がそれらのなかにどのように位置づけられるのか、を明確にすることが大切です。このために、論文の引用作業があるといえます。
次に、論文の引用にあたっては、今後自身の論文をみる他の研究者、すなわち読者がすぐ引用元を特定できるようにしなければなりません。論文の読者としては、筆者がどのような研究や文献を根拠として用いているのか、を確かめる必要があります。自然科学分野でいえば、自身の論文をみた読者が同じような研究をする場合、すぐに再現ができるものでなくてはなりません。なぜなら自身の研究は、自分だけの成果というのではなく、広く当該の研究分野に共有されるべき成果だからです。このため、他者が自分と同じ実験をおこない同様な実験結果を得ること(再現性)は、科学では特に重視されます。
またたとえ新たな研究であっても、かなりの部分は過去の研究の蓄積の上に成り立っています。研究論文には、これまでの先行研究をふまえることや、自身の研究がどこに位置づけられるのかを明確にすることが求められているといえます。
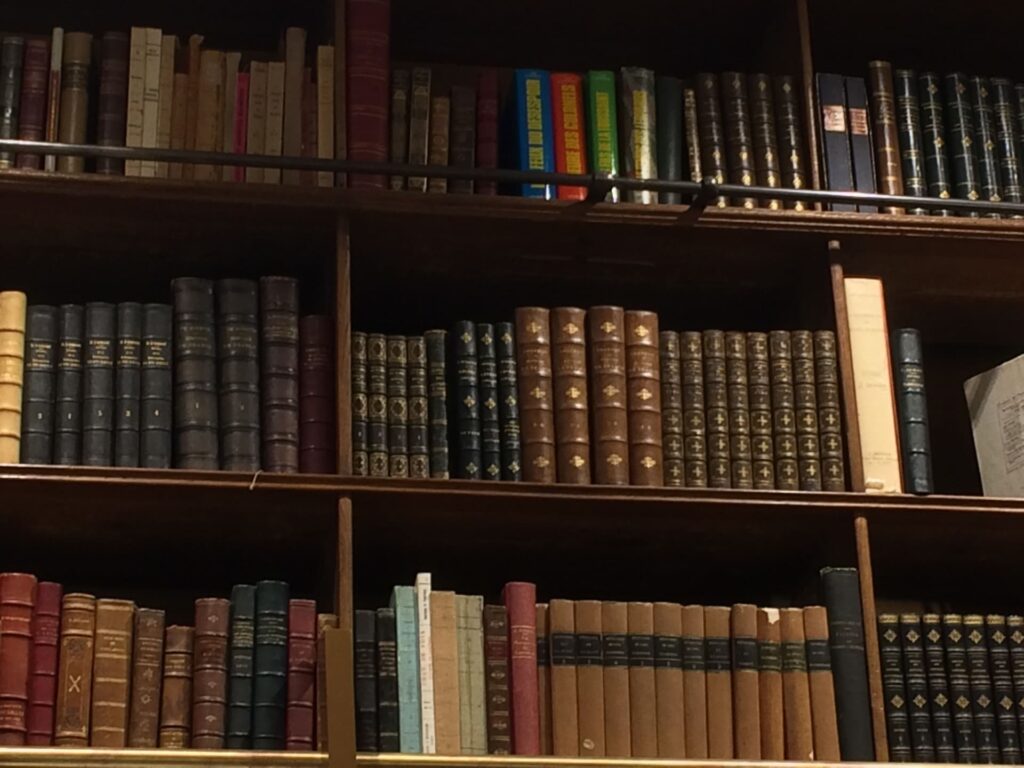
引用文献の記載は、論文執筆においては脇役ではあるものの重要な作業です。このような重要な既存論文の引用方法ですが、どのようにすればよいでしょうか。
論文引用の書き方としては、直接引用、ブロック引用や、間接引用があります。
直接引用では、引用文献の内容を、その表現のまま引用したいときに使用します。この場合、引用した既存文献の文章はそのまま引用して、改変はおこないません。
直接引用したいときは、引用部分を「・・・・・」として記載します。
〇〇は、「・・・・・」と述べている。
などの例があります。
たとえば、2015年の研究成果を記載する場合は、下記のようになります。
〇〇(2015)は、「・・・・・」と述べている。
また英語論文でよくみられる例として、下記のような併記例もあります(〇〇、△△は、著者名)。
・・・・・(〇〇、2020)、・・・・・(△△、2010)
さらに直接引用の中でも、文章の集合体をそのまま紹介する、ブロック引用という方法もあります。
既存文献の短文だけでなく、短文の集合体や長文を引用したい場合に使用します。自然科学系の論文でも、既存論文の実験方法に記載されている一部、またはそのほとんどを使用して、自身の研究に使用する場合があり、ブロック引用はかなり用いられている引用方法です。なおブロック引用したいときは、通常、引用部分の上下を一行あけて記載します。
直接引用と異なり、間接引用では当該の論文や書籍の内容を、引用をおこなう著者が自身の理解に基づき、内容要約する方法です。
短文やその集合体、さらには長文を含めて既存論文のかなりの部分に記載されている考え方や理論などを、自分で要約して使用することもあります。自然科学系でも、〇〇の理論などと引用する場合、引用元の記載と合わせて、自身で考えるところの〇〇理論を記載するなどの例がそれにあたります。
〇〇は、・・・・・であると指摘しており、同様な観点から検討をおこなった。
など、研究論文において、研究背景や考察などの項目でも使用される引用方法です。
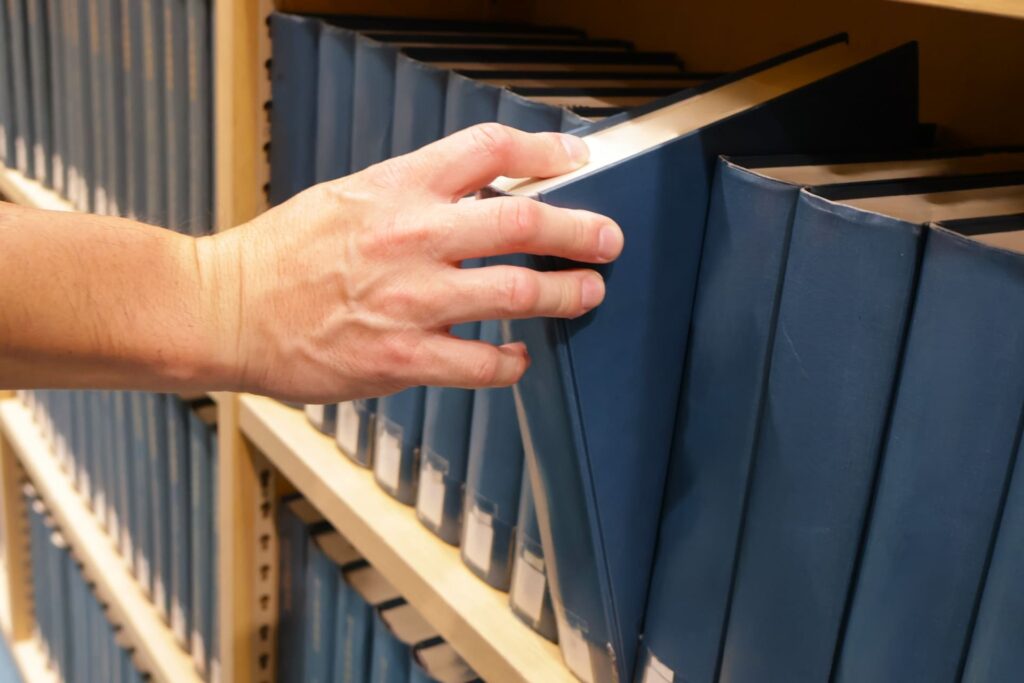
引用文献の書き方には、直接引用と間接引用があるわけですが、それでは実際の論文ではどのように記載したらよいでしょうか。
また研究論文では、論文の最後に引用文献をリスト化して記載する項目もあります(参考文献やREFERENCESなどの項目)。初めて論文を作成する場合は、どのようにしたらよいか迷うことになります。
実は、論文内での直接引用などと、引用された文献のリスト化は一体で理解すべきものです。とはいっても初めてですと、なかなかわかりにくい部分もあるので、実際の論文(下記の例では、当方の修士論文と博士論文でのリスト化を紹介)において説明してみます。
なお引用文献のリスト化については、論文内で記載された順番に基づく番号順方式、名前・出版年を併用する著者のアルファベット順方式があります。
アルファベット順方式は、論文が英語で作成されている場合に多くみられる方式です。日本語論文の場合は、アイウエオなどの順番で使用する方式はほとんどみられず、記載された順番による番号順方式が多いようです。
またアルファベット方式では、論文を読む際に、引用文献を適宜参照する場合は大丈夫ですが、後で当該論文の引用文献を総説的に理解する場合は、どこに記載されているかで悩むこともあります。論文著者は、引用文献リストをあらかじめ作成してから、論文執筆するので問題ありませんが、論文の読者では(引用文献に関する)全体像を理解するのはやや難しくなります。
比較的よく使用されている、番号順の場合のリスト化についてまず解説します。
当該論文に記述された順番に、番号をふってリスト化する方式です。なお番号は下記のように、文章の末尾に当該番号をふっていきます。このため末尾の参考文献欄には、番号順に、その出展を記載していくことになります。
たとえば、
〇〇は、「・・・・・」と述べている1)。
番号順方式として、かなり古く恐縮ですが、当方の修士論文の例を下記にあげてみます。
1. 〇〇、固定化酵素(1975)△△出版
2. □□、Immobilized enzyme technology(1975)▽▽ Press
゜
27.〇〇、Enzymologia, 38,39(1970)
主に論文の記載になりますが、引用文献として関連書籍も使用される場合があり、その場合は出版社名も記載します。
まず上記1の引用文献は、修士論文内で下記のように記載されています。
「酵素を固定化するには、・・・する方法がある(1)。」
すなわち本論文の研究背景を説明する上で、引用文献(この場合は書籍)を紹介している部分となっています。なお引用文献の書き方としては、いわゆる間接引用にあたり、固定化する複数の方法を、著者(当方)にて解説しております。
2の引用文献では、同じ論文内で以下のように記載されています。
「これらの固定化酵素を実際上利用するためには、・・・などの諸問題を解決しなければならない(2)。」
となっており、本論文の研究テーマ(実際に利用可能な固定化方法の検討)やその背景を説明している部分です。引用文献の書き方としては、同じく間接引用にあたります。
27の引用文献は、論文内の「考察」にて以下のように記載されています。
「すでに多孔質ガラスに吸着されたパパイン酵素(27)において、そのことが指摘されている」
当該の論文でみうけられた(固定化酵素の)ある現象が、27の引用文献でもみられています。修士論文とはいえ、専門家が実施した現象を修士課程の学生でも再確認できていることになります。以上のように番号順でリスト化することにより、当該論文における引用文献を網羅して紹介することができます。
次に英語論文などでよく使用されている、アルファベット順の場合のリスト化についても解説します。
論文引用時に、アルファベット順で、引用する論文の著者と出版年を記載していく方式です。末尾の参考文献欄には、アルファベット順でそれぞれの出展が明記されます。
リスト化方法が、アルファベット順の場合も、当方の博士論文例にて解説します。たとえば当該論文にて、「REFERENCES」の項目には下記のように記載されています。
1. 〇〇、・・・(1990)Clinical pharmacology of caffeine.
Annu. Rev. Med., 41:277-288
2. □□、・・・(1976)Acquired sensory control of satisfaction in man.
Br. J. Psychol., 67:137-147
゜
56. △△、・・・(1984) Relationship between caffeine concentrations in plasma
and saliva. Clin. Pharmacol. Ther., 36:133-137
まず引用文献1は、博士論文内で下記のように紹介されています。
「While not universary observed (〇〇 et al., 1990), a number of studies・・・」
先ほどの修士論文例と同様に、INTRODUCTIONにおける研究背景を説明している部分にあたります。すなわちこの論文の研究テーマは、従来あまり研究されてこなかった部分を解明することになるのです(まったく新規な研究テーマというのはなかなか難しいものですが、従来の文献と比較しても研究のオリジナリティがあることを強調している部分です)。なお引用文献の書き方としては、いわゆる間接引用にあたります。
引用文献56では、METHODS AND MATERIALS(実験方法)の項目に関連する文献となります。
「Caffeine is commonly consumed bitter substances that reliably appears in saliva shortly after ingestion (△△ et al., 1984).」
となっており、同論文の主要テーマである、苦味物質接種時の生体反応を調査する部分に関連しています。すなわち生体反応を調査する上で、唾液成分は重要な指標となるので、これを当該実験系で実施するということになります。このように引用文献は、論文の骨格の一部ともなる実験方法(の設定)についても、深く関与しています。
以上のように研究論文では、研究テーマとも関連する研究背景の項目から、研究方法や考察の部分まで、広範囲に引用文献が利用されていることがわかります。脇役というより、むしろ欠かせない事項ともいえます。研究のオリジナリティは、基本的には研究者が設定すべきですが、そのオリジナリティ(があるかどうか)は自身の論文の引用文献が決めているともいえます。
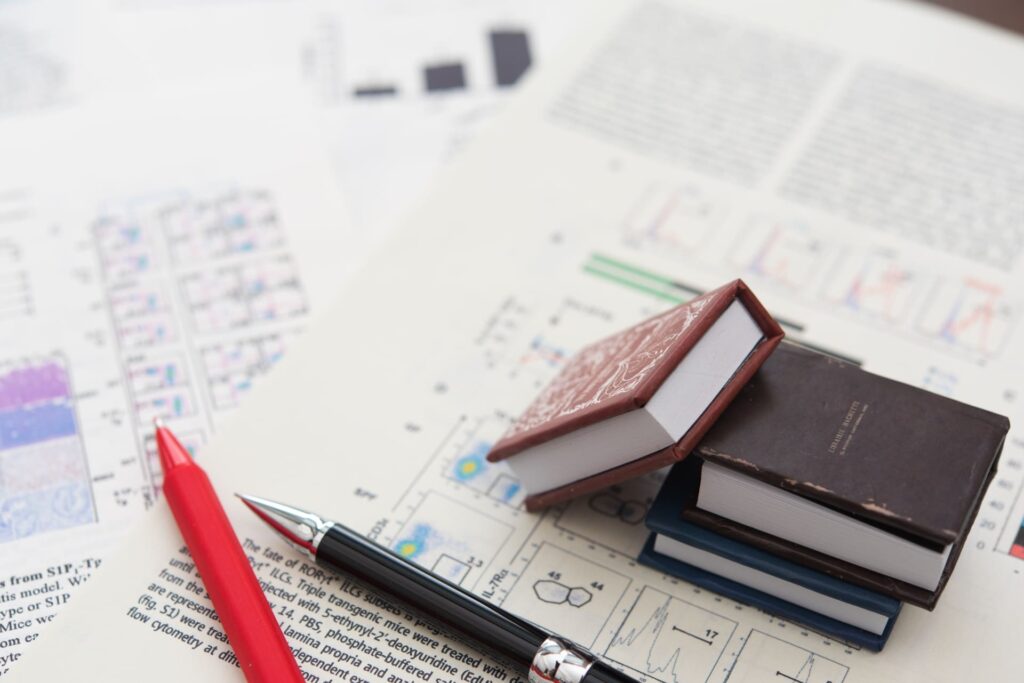
引用を適切に行うことは、論文を書く際に守らなければならない注意点のひとつです。このような論文作成における引用時のポイントとしては、どのようなものがあるのでしょうか。
これまで記載しましたように、自身の研究のオリジナリティを証明するためには、引用文献の記載が必須ともいえます。
引用とは、既存文献の研究紹介ではないかと思われる向きもないではないですが、実は、既存の研究と自分の研究を比較して、自身の研究成果を示す格好の機会です。
どのような点が、既存研究と異なるのかを明瞭に示すことができます。たとえ同様な実験手法を用いても、全く同じ結果とはならないこともあります。再現性が確認できるなら、既存文献と異なった結果であっても、論文に明記することもできます。
もしなぜ違う結果となったのか、考察などで十分に検討することもできるのです。このようなおびただしい研究成果の積み重ねが、現代の科学、特に科学的なエポックを生み出しています。古くなりますが、地動説と天動説の論争においても、実験データの積み重ねがそれを可能にしたのです。現代物理学でも、たとえばカミオカンデのフォトンセンサーなどの改良により、新しい視点が切り開かれているともいえます。
このような科学のエポックではなくとも、他の研究との比較によって、自分自身の研究が、それらとどのような点で異なるのかを指摘することが大切です。論文の引用を通じて、どのような新しい知見を提供しているのかを示すことができます。
また引用を適切に行うためには、自身と他者との研究成果の区別をすることも欠かせません。
どこが他者の研究成果で、どこからが自分の考えや研究成果なのかを、明確に区別して書かなければなりません。特に研究論文の考察においては、自他を明確に区別して論考することが求められます。この明確性がなければ、いわゆる原著論文などの学術誌に掲載されるような論文での査読基準には合致しません。他者の研究成果を用いて、あらたな考察をしても砂上の楼閣ということになります。
また自他の成果を区別するとは、他者の研究に敬意を払うためでもあります。学術誌でも、ときに研究不正の課題がクローズアップされることがありますが、著作権の問題以前に盗作などとされてしまうこともありえます。自身の論文が出版後でも、どこまでが既存研究で、どこからが新たな研究成果なのか明確にわかるようにしなければなりません。
このためにいろいろな引用ルールが慣習法として、従来設定されているのです。なお学術雑誌では、特に論文の「投稿規定」として、引用ルールを細かく記載している場合もあります。学会誌や、各大学でも同様な論文作成規定があるところもあり、これらの規定やルールにはしたがい、受理してもらえる研究論文を作成することが大切です。
このように引用を適切におこなうことが大切ですが、引用数とその内容については、必要かつ十分なものとしなければなりません。
自身の論文にほんとうに必要な既存文献を検索などで抽出するプロセスも重要です。参考文献は、実験方法や考察に関連する研究論文を、自身及び他の研究者を含めて、網羅的に検索して明記します。論文検索の手法で、関連の参考文献を適切に過不足なく、記載する必要があります。なおネットでの論文検索についても、科学系サイトなら大丈夫ですが、いわゆる一般サイトからの資料引用は避けるようにします。
また過度に引用数をふやしても、自身の研究論文の内容が充実する効果は期待できません。引用が主体で、既存文献を網羅して紹介するレビュー形式の論文もありますが、通常の学術論文とは異なります(システマティックレビューやナラティブレビューなど:本コラムでもその内容を紹介していますので、興味がある人は一度読んでみて下さい)。
なお論文引用にあたっては、既存文献のアブストラクトのみをみて引用するのではなく、実際の内容についても十分理解してから引用することが大切です。英語論文などもその全文を読んでから引用することをおすすめします。英語でそのまま理解できればよいですが、もし難しい場合は、PDFをそのまま翻訳してくれる「Redable」なども利用して、まず日本語で読んでみるようにすれば、原著者の趣旨を十分理解してから引用することにもつながります。
このように書くと、いろいろな研究成果が日夜生じているような先端科学の分野では、自分の成果が利用されてしまうのではないか、と懸念する向きもあるかもしれません。科学は基本的には人類共有の財産であり、このような成果の積み重ねが現代の科学を形成しているともいえます。
それでも自身の研究を簡単にまねされたくないという場合は、特許を申請しておくのも、ひとつの解決策です。特に先端科学分野では、いわゆるPCT出願を用いておけば、自身の研究の新規性や有用性が、世界中で知的財産権として維持されることにもつながります。
引用文献の書き方について、その目的から引用方法や引用時のポイントまで紹介しました。正しい引用文献の書き方には、出典を明示することがその前提となっています。
既存文献に書かれていることを、自身の論文の中でそのまま使用する場合だけでなく、既存論文が提示している考え方や理論などを用いる場合もあり、引用の仕方はさまざまです。また実験方法では、よく既存論文の手法を参考にしたり、そのまま使用して新たなデータを得たりしています。
自然科学系の研究論文の場合、研究方法の項目には、実験法の紹介をかねて既存文献の引用は不可欠なものとなっています。論文のオーサーには、研究論文がいわば砂上の楼閣とならないようにする責任があります。
さらにいえば引用文献とは、会計報告での各種資料のようなものです。官公庁などでは、毎年いろいろな会計報告が実施されていますが、その会計報告には正確な情報開示が欠かせません。
会計検査院によると、各省庁からの国連やASEANなどの国際機関への事業支出に対して、剰余金や繰越金などの資料がないものがかなりの程度あったそうです。会計報告自体を受けていなかったものもあり、いわば複数の事業では、事業支出自体が砂上の楼閣ともよべるかもしれません。
また研究論文においては、研究内容にオリジナリティがあることが必要です。このため、研究論文のアイデアが出るまでは、あえて他の論文を読まないようにとされていることもあります。ただ論文のアイデアが出てからは、必ず他の論文とも比較検討し、必要な論文は研究背景などで引用文献として書かなければなりません。
自分の研究テーマがもつ特徴や強みを明確にするためには、他者の論文と比較してその内容を検討したり、自身の研究との相違点を明らかにすることが大切です。引用文献の引用の仕方は、論文や著書などの内容によりさまざまです。本記事が、はじめて論文を作成する場合など、引用文献の適切な書き方についてご参考になれば幸いです。

研究や論文執筆にはたくさんの英語論文を読む必要がありますが、英語の苦手な方にとっては大変な作業ですよね。
そんな時に役立つのが、PDFをそのまま翻訳してくれるサービス「Readable」です。
Readableは、PDFのレイアウトを崩さずに翻訳することができるので、図表や数式も見やすいまま理解することができます。
翻訳スピードも速く、約30秒でファイルの翻訳が完了。しかも、翻訳前と翻訳後のファイルを並べて表示できるので、英語の表現と日本語訳を比較しながら読み進められます。
「専門外の論文を読むのに便利」「文章の多い論文を読む際に重宝している」と、研究者や学生から高い評価を得ています。
Readableを使えば、英語論文読みのハードルが下がり、研究効率が格段にアップ。今なら1週間の無料トライアルを実施中です。 研究に役立つReadableを、ぜひ一度お試しください!
Readable公式ページから無料で試してみる
都内国立大学にて、研究・産学連携コーディネーターを9年間にわたり担当。
大学の知財関連の研究支援を担当し、特にバイオ関連技術(有機化学から微生物、植物、バイオ医薬品など広範囲に担当)について、国内外多数の特許出願を支援した。大学の先生や関連企業によりそった研究評価をモットーとして、研究計画の構成から始まり、研究論文や公募研究への展開などを担当した。また日本医療研究開発機構AMEDや科学技術振興機構JSTやNEDOなどの各種大型公募研究を獲得している。
名古屋大学大学院(食品工業化学専攻)終了後、大手食品メーカーにて31年間勤務した経験もあり、自身の専門範囲である発酵・培養技術において、国家資格の技術士(生物工学)資格を取得している。国産初の大規模バイオエタノール工場の基本設計などの経験もあり、バイオ分野の研究・技術開発を得意としている。
学位・資格
博士(生物科学):筑波大学にて1994年取得
技術士(生物工学部門);1996年取得