
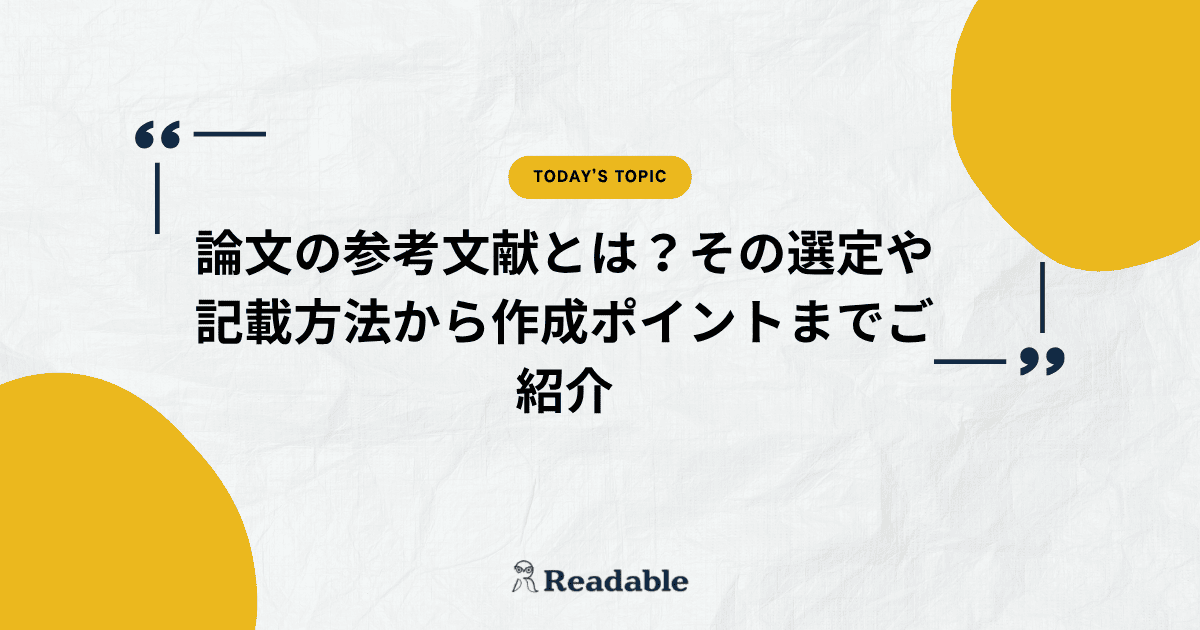
論文執筆において、参考文献の選定やその記載は、脇役とはいえ重要な作業となります。
参考文献の選定にあたっては、自身の論文をみる他の研究者、すなわち読者がすぐ当該の文献を特定できるようにしなければなりません。論文の読者としては、著者がどのような研究や文献を根拠として用いているのかを確かめる必要があります。
本記事では、参考文献の選定や記載方法、さらには作成ポイントまで紹介します。
目次

論文の作成において、参考文献の選択と記載は重要なポイントです。
たとえば、実験結果の項目で使用した文献(実験方法など)は必ず、参考文献の項目にも記載しなければなりません。
参考文献に記載した方法にそのまま従う場合は、その論文を記載するだけでよいですが、実験にあたってなんらかの工夫や修正をしている場合もあります。参考文献を引用するだけでなく、過不足なく実験方法の記載項目にもふれておくことが大切です。
また参考文献の記載にあたっては、関連した論文を抽出し、実際に読んでおく必要があります。特に、自身の研究分野の関連論文を効率的に探すようにしましょう。当該研究に関する「キーワード」をGoogle Scholarなどの論文専用サイトを使用してあらかじめ検索して、関連の参考文献を網羅しておく必要があります。
このように論文執筆において、参考文献の選定やその記載は、脇役とはいえ必要不可欠なプロセスともいえます。
なお参考文献の記載とは、他者の研究成果や著作物等を利用する行為にも該当します。もし適切な方法で行わなければ、著作権法違反にあたる可能性もあります。どこまでが他者の研究成果で、どこからが自分の考えや研究成果なのかを、明確に区別して書かなければなりません。
特に研究論文の考察部分においては、自他を明確に区別して論考することが求められます。この明確性がなければ、原著論文などの学術誌に掲載されるような論文での査読基準には合致しません。他者の研究成果を用いて、あらたな考察をしても砂上の楼閣ということになります。
論文の中でも、文献を網羅的に収集し、その内容を科学的に再検討する総説論文といわれるものもあります。
総説論文は、ある特定の分野に関して、先行する研究を徹底的に調査し、結果を比較検討したものを述べる論文の一種です。過去の研究に基づくこと、新たな研究データは含まないこと、そして未発表の文献を対象としないことが特徴となっています。なお総説論文は、それ単独で著作物となります。このため先ほど記載しましたように、著作権にも関連する場合には特に留意することが大切です。
参考文献の選定は、自身の論文作成とも大きく関係しています。
従来のこれまでの研究をふまえて、自身の研究が成り立っており、その研究成果が自身の論文となっています。これまでの先行研究をふまえることと、自身の研究がそれらのなかにどのように位置づけられるのか、を明確にすることが大切です。このためにも、参考論文の選定・記載作業があるといえます。
参考文献の選定にあたっては、今後自身の論文をみる他の研究者、すなわち読者がすぐ当該の文献を特定できるようにしなければなりません。論文の読者としては、著者がどのような研究や文献を根拠として用いているのか、を確かめる必要があります。自然科学分野でいえば、自身の論文をみた読者が同じような研究をする場合、すぐに再現ができるものでなくてはなりません。
なぜなら自身の研究は、自分だけの成果というのではなく、広く当該の研究分野に共有されるべき成果だからです。このため、他者が自分と同じ実験をおこない同様な実験結果を得ること(再現性)は、科学では特に重視されます。
論文作成自体の目的が、新規性を追及するものであったとしても、新しい発見は既存の研究成果を前提に成立するものです。まして、従来の研究からの改善点を訴求するような論文の場合は、既存の参考文献からの考察と参照が欠かせないものとなります。
なお論文の作成にあたっては、参考文献の内容をそのまま取り入れるのは不十分です。
先行研究である文献を論文作成に利用するには、場合によっては、批判的に検討することも必要です。

参考文献の選定後には、論文の中への記載作業もあります。
通常、参考文献の記載は、論文の最後の部分に当該の項目を設けて記述されます。なお実験方法の項目で参照される場合、その内容を再度記載したり、一部の手順が修正されたりした場合は、それをさらに追記することもあります。このような場合、当該文献も参照箇所を中心に、自身の論文の本文中へ記載されます。
実験データ以外に、実験方法ではよく既存論文の手法を参考にしたり、そのまま使用して新たなデータを得る場合もあります。このようなときには、既存論文のデータは使用していませんが、その実験手法は使用していることになります。
このため、自然科学系の論文の場合、研究方法の項目には、実験法の紹介をかねて参考文献が引用されているのです。また、参考文献の手法そのままで、このデータを得たとして記載されているときもかなりあります。医学やバイオ分野からはじめ、化学や物理分野でも同様な記載で論文が執筆されています。
参考文献には、研究背景や本論で引用した資料が必ず含まれることが重要です(引用時には、資料の記載先に番号をふっておき、その順番により参考文献を記載します)。
書籍の場合は(著者、本の名前、出版社、発行年)、 論文や雑誌などの記事の場合は、(著者、論文名、出典、ページ、発行年)を記載します。外国語から翻訳された文献を参照した場合は、まず文献の原題を示し、著者名、出版社や出版年などを示します。
Webページの場合でも、ページのタイトルとURLは必ず引用しておきます(下記、引用例を参照してください)。また著者名や発行年なども記載することも大切です。
なお具体的な参考文献の書き方としては、以下のとおりです。
◆ 参考文献は原則として、論文の末尾に一括して載せ、本文中の脚注には載せません。
◆ もし論文本文の中で、参照のために文献を挙げるときは、著者名、発行年、ページ数を括弧内として、論文中に入れます(著者名、発行年のみ記載の場合もあり)。
この書き方を当方の博士論文例でみると、DISCUSSION(考察)の項目にて、本文中の〇頁にたとえば、
{Settle, 1991]と記載されています(Settle博士の研究論文であることがわかります)。
さらに、当方論文末尾のREFERENCES(参考文献)の欄にて、
42. Settle, R.(1991) Smell and Taste in Health and Disease. Raven Press, New York, pp.829-844
と詳述されております。
当方博士論文は、ヒトの味覚に関する研究論文ですが、当該部分には、キニーネ(苦味)などの味覚閾値に関する考察が記載されています。Settle博士の研究論文と当方の研究結果を比較検討して、考察している箇所となります。
参考文献は、論文の「参考文献欄」にまとめて記載することになります。
ここではよく使用される、番号順方式と著者・出版年を併用する方式について紹介します。
番号順方式として、かなり古く恐縮ですが、当方の修士論文の例を下記にあげてみます。
1. 〇〇、固定化酵素(1975)△△出版
2. □□、Immobilized enzyme technology(1975)▽▽ Press
゜
27. 〇〇、Enzymologia, 38,39(1970)
主に論文の記載になりますが、関連書籍も引用される場合があるので、その場合は出版社名も記載しておきます。
次に、出展記載が、著者・出版年併用方式の場合も、当方の博士論文例にて記載します。英語論文にて、「REFERENCES」の項目に下記のように記載しています。
1. 〇〇、・・・(1990)Clinical pharmacology of caffeine.
Annu. Rev. Med., 41:277-288
2. 〇〇、・・・(1976)Acquired sensory control of satisfaction in man.
Br. J. Psychol., 67:137-147
゜
56. 〇〇、・・・(1984) Relationship between caffeine concentrations in plasma
and saliva. Clin. Pharmacol. Ther., 36:133-137

参考文献の記載を適切に行うことは、論文を書く際に守らなければならない注意点のひとつです。このような論文作成における参考文献の記載ポイントとしては、どのようなものがあるのでしょうか。
論文作成に取り掛かる前に、自身の研究テーマに関する文献や資料を収集して読み込んでおく必要があります。実験系の論文でも実験だけをするわけではなく、関連研究論文の紹介が必要で、自身の実験の背景となる関連資料を正確に把握していなければなりません。
参考文献であるので、アブストラクト部分だけを読んで、自身の論文の参考文献欄に記載しておけばよいというものではありません。関連研究、特に最先端の研究成果などの論文を複数収集することが大切です。
先行研究の論文収集と精読が、論文作成では重要な作業となります。まず図書館や専門の検索サイトから、自身の研究に関連する文献を収集します。収集した先行研究論文はじっくり読みこむことが大切です。検索結果の概要だけみて記載するなどの対応はなるべく避けるようにします。
なお先行研究で把握した関連資料は、論文作成の準備作業として、手元に書き留めておくようにします。関連研究の論文や、もし外部の研究会などで関連研究者が研究発表したものを自分用にリスト化していると、次の論文作成にも役立ちます。
参考文献の記載を適切に行うためには、自身と他者の研究成果の区別をすることも欠かせません。
文献の記載とは、他者の著作物、ときには他者が作成した既存論文における文章や図表を、自身の論文のなかで用いることです。また記載をするときには、どの論文から引用してきたのか、その出典を明示しなければなりません。
他者の著作物に書かれていることを、自身の論文の中でそのまま使用する場合だけでなく、既存論文が提示している考え方や理論や、さらにはその論文中で掲載されている図表などのデータを用いる場合も同様ですが、このような場合は、参考文献というより「引用文献」といえるものです。
自他の成果を区別するとは、他者の研究に敬意を払うためです。このため自身の論文が出版後に、どの読者でもどこまでが既存研究で、どこからが新たな研究成果なのか明確にわかるようにしなければなりません。
このためにいろいろな引用ルールが慣習法として、従来設定されているのです。なお学術雑誌では、特に論文の「投稿規定」として、参照ルールを細かく記載している場合もあります。学会誌や、各大学でも同様な論文作成規定があるところもあり、これらの規定やルールにはしたがい、受理してもらえる研究論文を作成することが大切です。
論文にほんとうに必要な既存文献を検索などで抽出するプロセスも重要です。参考文献は、実験方法や考察に関連する研究論文を、自身及び他の研究者を含めて、網羅的に検索して明記します。論文検索の手法で、関連の参考文献を適切に過不足なく、記載する必要があります。なおネットでの論文検索についても、科学系サイトなら大丈夫ですが、いわゆる一般サイトからの文献引用は避けるようにします。
過度に参考文献数をふやしても、自身の研究論文の内容が充実する効果は期待できません。引用が主体で、既存文献を網羅して紹介するレビュー形式の総説論文などもありますが、通常の学術論文とは異なります。
論文執筆において、参考文献の選定やその記載は、脇役とはいえ重要な作業です。
参考文献の選定にあたっては、今後自身の論文をみる他の研究者、すなわち読者がすぐ当該の文献を特定できるようにしなければなりません。逆に論文を読む側では、著者がどのような研究や文献を根拠として用いているのかを確かめる必要があります。
自然科学分野でいえば、研究論文をみた読者が同じような研究をする場合、すぐに再現ができるものでなくてはなりません。他者が同じ実験をおこない、同様な実験結果うるという再現性は、科学では特に重視されています。
論文中の参考文献の記載方法は、大切な作業のひとつです。本記事が、参考文献を選定・記載しようとしているみなさまのお役に立てば幸いです。

研究や論文執筆にはたくさんの英語論文を読む必要がありますが、英語の苦手な方にとっては大変な作業ですよね。
そんな時に役立つのが、PDFをそのまま翻訳してくれるサービス「Readable」です。
Readableは、PDFのレイアウトを崩さずに翻訳することができるので、図表や数式も見やすいまま理解することができます。
翻訳スピードも速く、約30秒でファイルの翻訳が完了。しかも、翻訳前と翻訳後のファイルを並べて表示できるので、英語の表現と日本語訳を比較しながら読み進められます。
「専門外の論文を読むのに便利」「文章の多い論文を読む際に重宝している」と、研究者や学生から高い評価を得ています。
Readableを使えば、英語論文読みのハードルが下がり、研究効率が格段にアップ。今なら1週間の無料トライアルを実施中です。 研究に役立つReadableを、ぜひ一度お試しください!
Readable公式ページから無料で試してみる
都内国立大学にて、研究・産学連携コーディネーターを9年間にわたり担当。
大学の知財関連の研究支援を担当し、特にバイオ関連技術(有機化学から微生物、植物、バイオ医薬品など広範囲に担当)について、国内外多数の特許出願を支援した。大学の先生や関連企業によりそった研究評価をモットーとして、研究計画の構成から始まり、研究論文や公募研究への展開などを担当した。また日本医療研究開発機構AMEDや科学技術振興機構JSTやNEDOなどの各種大型公募研究を獲得している。
名古屋大学大学院(食品工業化学専攻)終了後、大手食品メーカーにて31年間勤務した経験もあり、自身の専門範囲である発酵・培養技術において、国家資格の技術士(生物工学)資格を取得している。国産初の大規模バイオエタノール工場の基本設計などの経験もあり、バイオ分野の研究・技術開発を得意としている。
学位・資格
博士(生物科学):筑波大学にて1994年取得
技術士(生物工学部門);1996年取得