
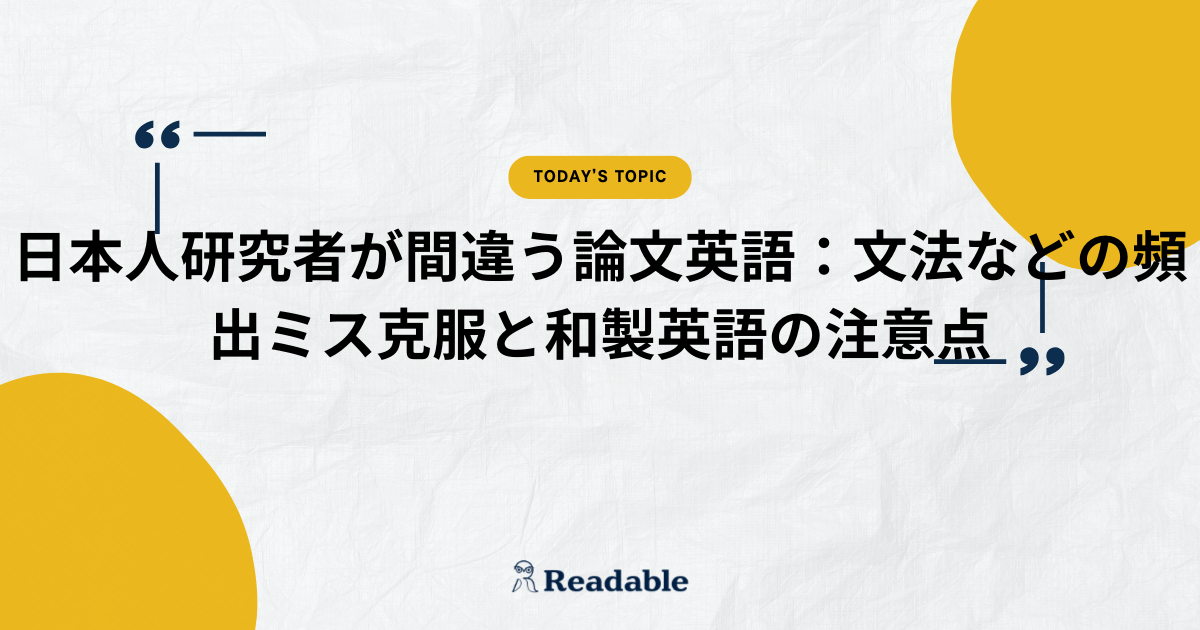
論文執筆は、研究者にとって重要なアウトプットの一つですが、特に英語で執筆する場合、多くの課題に直面します。文法や語彙のミスはもちろんのこと、日本人特有の英語表現である「和製英語」の使用は、査読者に誤解を与え、論文の評価を大きく左右する可能性があります。
本記事では、日本人研究者が陥りやすい論文英語の頻出ミスとその克服法、そして和製英語の落とし穴について詳しく解説します。これらのポイントを押さえ、より質の高い論文作成を目指しましょう。
目次
論文英語において常に意識すべきは、主語と動詞の数を一致させることです。しかし、複雑な文構造や複数形の扱いに迷うことで、この基本的なルールが疎かになるケースが見受けられます。
例えば、「気候変動の影響に関する最近の研究は、地球の気温の著しい上昇を示している」と述べたい場合に、“A recent study on the effects of climate change show a significant increase in global temperatures.”と書いてしまうことがあります。正しくは、主語である “study” が単数であるため、動詞も単数形の “shows” を用いるべきです。主語と動詞の不一致は、以下のような場合に特に起こりやすいです。
例えば、「委員会は会議の延期を決定した」と言う場合、“The committee have decided to postpone the meeting.” となりがちですが、委員会全体としての決定を示す場合は単数扱いとし、“The committee has decided to postpone the meeting.” とします。
一方で、「委員会のメンバーは、その件について異なる意見を表明した」のように、個々の構成員に焦点を当てる場合は、“The committee members have expressed different opinions on the matter.” と複数形を用いるのが適切です。
冠詞の使い分けは、英語学習者にとって長年の課題であり、論文英語においても例外ではありません。
「我々は水質汚染を観察した」と述べたい場合に、“We observed a water pollution.” と書いてしまうのは誤りです。物質名詞である “water pollution” は通常無冠詞で用います。冠詞の使い分けのポイントは以下の通りです。
具体的な誤用例と修正例は以下の表の通りです。
| 誤用例 | 修正例 | 説明 |
| We observed a water pollution. | We observed water pollution. | 物質名詞である “water pollution” は通常無冠詞です。 |
| This study investigates the new method. | This study investigates a new method. | ここでは特定の手法ではなく、新しい手法の一つを指しているため “a” が適切です。 |
| The Tokyo is a big city. | Tokyo is a big city. | 固有名詞である都市名には通常冠詞は付きません。 |
| We need to conduct a further research. | We need to conduct further research. | “research” は通常、特定の場合を除き無冠詞で用いられます。 |
例えば、データの複数形である “data” の扱いにも注意が必要です。「データは明確な傾向を示している」と言う場合、一般的には “Data show a clear trend.” と複数扱いにしますが、特定のデータを指す場合は “The data shows a clear trend.” となります。
名詞の単数形と複数形の使い分けも、論文英語で頻繁に見られるミスの一つです。特に、数えられる名詞(可算名詞)と数えられない名詞(不可算名詞)の区別が曖昧だと、誤りが生じやすくなります。
「我々はいくつかのデータを分析した」と述べたい場合、“We analyzed several data.” とするよりも、“We analyzed several datasets.” とする方が学術論文としては適切です。
単数形と複数形の混同は、以下のような場合に起こりがちです。
具体的な誤用例と修正例は以下の表の通りです。
| 誤用例 | 修正例 | 説明 |
| We analyzed several data. | We analyzed several datasets. | 学術論文においては、”data” の複数形として “datasets” がより適切です。 |
| The equipment are very expensive. | The equipment is very expensive. | “equipment” は不可算名詞のため、複数形はなく、単数扱いとなります。 |
| We need more informations about this. | We need more information about this. | “information” は不可算名詞のため、複数形はありません。 |
| The result shows two phenomenons. | The result shows two phenomena. | “phenomenon” の複数形は “phenomena” です。 |
例えば、「我々の研究はいくつかの魚の種に焦点を当てた」と言う場合、“Our research focused on several species of fish.” が正しいです。”species” は単数形も複数形も同じ形である点に注意が必要です。
論文執筆において、文法チェッカーは非常に有用なツールです。スペルミスや基本的な文法ミスを自動的に検出してくれるため、最終的なクオリティを高める上で役立ちます。
市販の英文校正ソフトやオンラインの文法チェックツールを活用することで、自分では気づきにくいミスを発見できる可能性があります。例えば、あるオンライン文法チェッカーで “The result were significant.” という文をチェックしたところ、主語である “result” が単数であるため、動詞を “was” に修正する提案がされました。
文法チェッカーを活用する際の注意点としては、以下の点が挙げられます。
より質の高い論文を作成するためには、ネイティブスピーカーによる校正を依頼することが非常に有効です。文法や語彙の誤りだけでなく、自然で適切な英語表現を学ぶ絶好の機会となります。特に学術論文の場合、専門分野の知識を持つ校正者に依頼することで、内容の正確性に対する信頼性も高まります。
校正を依頼する手段としては、以下のようなものが考えられます。
校正を依頼する際には、論文の目的やターゲット読者層を明確に伝えることが重要です。校正結果を受け取った際は、なぜ修正されたのかをしっかりと理解するように努めましょう。指摘された点を学ぶことで、自身の英語力向上にも繋がります。
例えば、ある日本人研究者が自身の論文原稿を英文校正サービスに依頼したところ、文法ミスだけでなく、不自然な単語の選択や回りくどい表現が多数指摘され、より簡潔で専門的な語彙を用いた代替案が提案されたことで、論文全体の明瞭性が大幅に向上した例が報告されています。
自身の研究分野における質の高い英語論文を精読することは、論文英語の質を高めるための重要なステップです。適切な単語の選択、自然な表現、さらには論文全体の構成まで、多くのことを学べます。
類似論文を読む際には、以下の点に注意しましょう。
また、ネイティブスピーカーが書いた論文だけでなく、英語を母語としない研究者が書いた論文も参考にすることで、自身と同じような間違いを避けるヒントが得られることもあります。
例えば、自身の研究テーマに関する主要な学術雑誌に掲載されている論文をいくつか選び、そこで頻繁に使われている専門用語や表現をリストアップし、自身の論文執筆時にそれらを積極的に用いるように心がけるといった方法が有効です。
普段私たちが日常的に使っているカタカナ語の中には、英語圏では意味が通じない、あるいは全く異なる意味を持つ「和製英語」が数多く存在します。論文という学術的な文脈でこれらの和製英語を安易に使用すると、査読者や読者に誤解を与え、研究内容の正確な伝達を妨げる可能性があります。
以下に、論文や会話でそのまま使うべきではない和製英語の例とその英語での一般的な表現を示します。
| 和製英語 | 英語での一般的な表現 |
| パソコン | PC, personal computer, laptop (ノートパソコンの場合) |
| コンセント | outlet (アメリカ英語), socket (イギリス英語) |
| ガソリンスタンド | gas station (アメリカ英語), petrol station (イギリス英語) |
| モーニングサービス | breakfast special |
| サラリーマン | office worker, businessperson |
| ナイーブ | naive (英語にもありますが、ネガティブな意味合いが強い) |
| ドクターストップ | doctor’s orders |
例えば、データを分析するために「パソコン」を使ったと記述したい場合、“We used a PC to analyze the data.” と書くのが適切です。
「デバイスをコンセントに繋いでください」と言いたい場合は、“Please plug the device into the outlet.” となります。
ある日本の研究チームが海外の研究者と共同で研究を行っていた際、報告書の中で参加者の育児状況について言及する際に「ベビーカー(baby car)」という言葉を使用しました。英語を母語とする研究者は「baby car」という言葉から、乳幼児用の自動車のようなものを想像してしまい、実際の意味である「stroller」や「pram」をすぐに理解することができませんでした。この和製英語の使用が原因で、一時的にコミュニケーションに齟齬が生じ、内容の確認に時間を要する事態となりました。。
和製英語の中には、英語にも存在するものの、日本語で使われている意味合いと英語本来の意味が大きく異なる単語も少なくありません。これらの単語を論文や会話で誤って使用すると、意図しない意味が伝わってしまう危険性があります。以下に、意味が異なる和製英語の例をまとめました。
| 和製英語 | 日本語での意味 | 英語本来の意味 |
| バイキング | 食べ放題 | Viking (ノルマン人のこと) |
| リサイクル | 再利用 | recycle (資源を再資源化すること。日本語の「リサイクルショップ」は “second-hand shop” や “thrift store”) |
| イメージ | 印象、雰囲気 | image (画像、映像、比喩) |
| クレーム | 苦情、異議申し立て | claim (主張、要求) |
| オーダー | 注文 | order (命令、順序) |
| ストップ | 中止、停止 | stop (止まる) |
| エネルギー | 活力、元気 (英語の “energy” もありますが…) | energy (エネルギー、活力。ただし、物理的なエネルギーや活動力を指すことが多い) |
例えば、「食べ放題」という意味で「バイキング」を使いたい場合は、英語では “buffet” と表現します。
研究発表のスライドで、「この研究のイメージ」を伝えたいと考え、「The image of this research is…」と記述したところ、英語を母語とする参加者には具体的な画像や比喩の話だと誤解されてしまいました。ここでは、「The main finding of this research is…」のように、研究の主要な発見や意義を伝えるべきでした。
論文では、口語的あるいは曖昧な和製英語を避け、よりフォーマルで正確な英語表現を用いることが求められます。
以下に、論文で推奨される英語表現への言い換え例を示します。
| 和製英語 | 論文での推奨される英語表現 |
| 〜について、〜に関して | regarding, concerning, with respect to, in relation to |
| 〜という風に | in this way, thus, hence, consequently |
| 〜だと思います | We believe that …, We consider that …, It is suggested that … |
| 要するに | In summary, In conclusion, To summarize |
| 〜してみてください | Please refer to …, It is recommended to …, We suggest that … |
| 結構です | sufficient, adequate, satisfactory |
| 頑張ります | We will endeavor to …, We will strive to …, We will attempt to … |
例えば、論文の考察部分で、「この結果について、私は重要だと思います」と書きたい場合に、「About this result, I think it is important.」と直訳してしまうのは不自然です。より適切な表現としては、「Regarding this result, we consider it significant due to…」のように、客観的な根拠と共に述べるべきです。
論文は、読者がその内容をスムーズに理解できるよう、論理的で一貫した構成で記述することが不可欠です。各段落が明確な主張を持ち、それらの主張が自然な流れで繋がっていることが重要となります。
一般的な論文の構成要素は以下の通りです。
各セクションの目的を明確にし、必要な情報を過不足なく記述する必要があります。段落間は適切な接続詞や指示語を用いて繋ぎ、図や表を効果的に活用しましょう。
客観的な事実と研究者の解釈を明確に区別することも重要です。例えば、ある研究論文では、結果のセクションで客観的なデータを詳細に示し、続く考察のセクションでそのデータが意味することや、既存の研究とどのように関連するのかを深く議論することで、読者の理解を深めています。
論文は、情報を簡潔かつ明確に伝えることを目的としています。そのため、以下のような冗長な表現は避けましょう。
可能な限り能動態を用い、句読点を適切に用いて文の構造を明確にすることも重要です。
抽象的な表現は避け、具体的な数値やデータを用いることで、説得力のある記述を心がけましょう。例えば、「〜というような状況が見られた」は「〜という状況が見られた」に、「非常に重要な役割を果たしていると考えられる」は「重要な役割を果たしている」とそれぞれ簡潔にできます。
論文を書き終えたら、必ず客観的な視点で読み返すことが重要です。時間を置いてから読み返したり、声に出して読んでみたり、他人に読んでもらったりすることで、自分では気づかなかったミスや改善点を発見できることがあります。
推敲の際には、以下のような点に注意してチェックリストを作成し、確認していくと効果的です。
また、印刷して読むことで、画面上では見過ごしがちなミスを発見できることがあります。例えば、自分が書いた論文を数日後に読み返したところ、同じ単語が近い距離で何度も使われていることに気づき、類義語辞典を活用して表現を多様化することで、文章がより洗練されました。
本記事では、日本人研究者が論文英語で陥りやすい頻出ミス、その克服方法、そして特に注意すべき和製英語について詳しく解説しました。論文執筆は決して容易ではありませんが、今回ご紹介したポイントを常に意識し、日々の研究活動の中で英語に触れる機会を増やしていくことで、必ず質の高い論文を作成できるようになります。
自身の研究成果を世界に発信するためには、論文の質を高めることが不可欠です。正確な文法や語彙の知識はもちろんのこと、和製英語の誤用を避け、論理的で分かりやすい文章を心がけることが、査読者や読者からの信頼を得るための重要な一歩となります。
困難に感じることもあるかもしれませんが、諦めずに一つ一つの課題と向き合い、自信を持って論文作成に取り組んでください。

研究や論文執筆にはたくさんの英語論文を読む必要がありますが、英語の苦手な方にとっては大変な作業ですよね。
そんな時に役立つのが、PDFをそのまま翻訳してくれるサービス「Readable」です。
Readableは、PDFのレイアウトを崩さずに翻訳することができるので、図表や数式も見やすいまま理解することができます。
翻訳スピードも速く、約30秒でファイルの翻訳が完了。しかも、翻訳前と翻訳後のファイルを並べて表示できるので、英語の表現と日本語訳を比較しながら読み進められます。
「専門外の論文を読むのに便利」「文章の多い論文を読む際に重宝している」と、研究者や学生から高い評価を得ています。
Readableを使えば、英語論文読みのハードルが下がり、研究効率が格段にアップ。今なら1週間の無料トライアルを実施中です。 研究に役立つReadableを、ぜひ一度お試しください!
Readable公式ページから無料で試してみる

東大応用物理学科卒業後、ソニー情報処理研究所にて、CD、AI、スペクトラム拡散などの研究開発に従事。
MIT電子工学・コンピュータサイエンスPh.D取得。光通信分野。
ノーテルネットワークス VP、VLSI Technology 日本法人社長、シーメンスKK VPなどを歴任。最近はハイテク・スタートアップの経営支援のかたわら、web3xAI分野を自ら研究。
元金沢大学客員教授。著書2冊。