
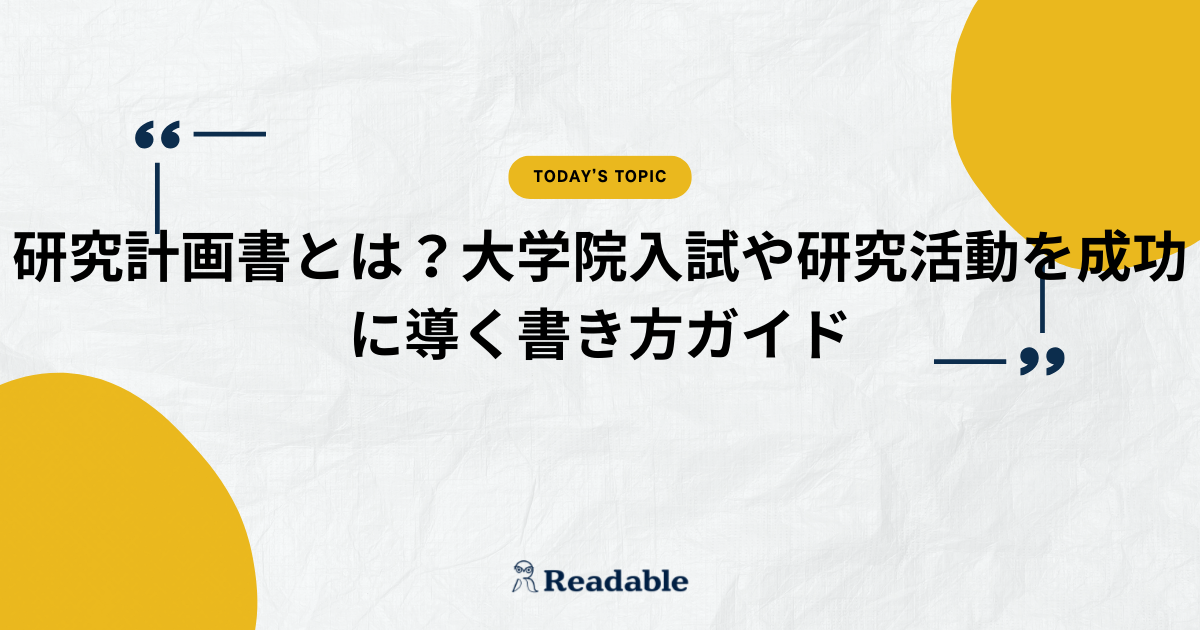
大学院入試や研究活動で「研究計画書」の提出を求められ、「そもそも何を書けばいいの?」「なぜ必要なの?」「どうすれば評価される計画書が書けるの?」と悩んでいませんか?
研究計画書は、あなたの研究者としての未来を左右する重要な書類です。この記事では、研究計画書の基本から、具体的な書き方、そして評価を高めるための秘訣まで、網羅的に解説します。これを読めば、自信を持って研究計画書作成に取り組めるようになるでしょう。

研究計画書とは、一言で言えば「大学院入学後に行いたい研究内容と、その研究を行うための計画をまとめた書類」です。具体的には、自身が取り組みたい研究テーマについて、その背景や目的、具体的な研究方法、期待される成果などを体系的に記述した文書を指します。これは単なるアイデアメモではなく、研究プロジェクト全体の「設計図」や「企画書」に相当するものです。
研究計画書は主に以下の要素で構成されます:
提出先の大学院や研究科によっては指定のフォーマットがある場合もあるため、事前に確認が必要です。この計画書を通じて、あなたがどのような研究に関心を持ち、それをどのように進めようとしているのかを、大学院側に明確に伝える役割を果たします。企業活動における「事業計画書」に例えられることもあり、研究の方向性と戦略を示す重要な文書と位置づけられています。
研究計画書が求められる主な理由は、それが評価の重要な判断材料となるからです。特に大学院入試においては、合否に大きく関わる書類とされています。大学院側は提出された研究計画書を通して、以下の点を確認しています。
また、研究計画書は大学院入試だけでなく、科学研究費補助金(科研費)のような研究資金を獲得するためにも不可欠です。研究資金の申請においては、研究計画書が研究の独創性、重要性、計画の妥当性を審査員に示し、資金提供を受けるに値することを納得させるための根拠となります。このように、研究計画書は、あなたの研究能力と研究の価値を外部に示し、入学許可や研究資金といった具体的な機会を得るために必要不可欠な文書なのです。
研究計画書は、単に大学院入試や研究資金申請のためだけに存在するわけではありません。作成プロセス自体が、研究者自身の思考を整理し、研究活動を円滑に進める上で重要な役割を果たします。
まず、研究計画書は自己整理のためのツールとして機能します。研究の目的、意義、具体的な手順を文書化する過程で、研究者は自身の考えを客観的に見つめ直し、研究の焦点を明確にできます。漠然としたアイデアを具体的な計画に落とし込むことで、研究期間中に方向性を見失うことなく、効率的に研究を進めるための指針(羅針盤)となるのです。つまり、「提出するため」だけでなく、「自分の研究をスムーズに進めるため」のツールでもあるわけです。
次に、研究計画書はコミュニケーションツールとしての役割も担います。作成した計画書は、指導教員や研究室のメンバー、学会関係者などに対して、自身の研究構想を効果的に伝え、理解や協力を得るための媒体となります。研究の面白さや重要性を他者に的確に伝える能力は、研究者にとって不可欠なスキルであり、研究計画書の作成はその訓練の場ともなります。
このように、研究計画書は外部評価のためだけでなく、研究者自身の思考整理や他者との円滑なコミュニケーションを促進するという、多面的な役割を持っているのです。
代替テキスト 研究計画書の重要性:なぜ評価されるのか?
研究計画書が重要視される最大の理由の一つは、それが作成者の「研究遂行能力」を証明する指標となるからです。大学院側は、提出された計画書の内容を通じて、志願者が大学院レベルの研究を主体的に進めるために必要な資質や能力を持っているかを評価します。
具体的には、以下の点がチェックされます。
質の高い研究計画書は、単に研究アイデアが面白いというだけでなく、作成者が研究プロセス全体を理解し、それを計画通りに遂行できる見込みが高いことを示唆します。大学院での研究活動は、多くの場合、自律性が求められます。そのため、計画書を通じて示されるこれらの能力は、入学後の研究活動の成否を予測する上で非常に重要な要素となるのです。したがって、研究計画書は、あなたの研究者としてのポテンシャルを示すための、いわば「能力証明書」のような役割を果たすと言えるでしょう。
研究計画書において、研究アイデアの独創性や意義を示すことは重要ですが、それと同等、あるいはそれ以上に重視されるのが「研究の実現可能性」と「計画の妥当性」です。どんなに魅力的な研究テーマであっても、それが絵に描いた餅であっては意味がありません。大学院や研究資金提供機関は、提案された研究が限られた時間やリソースの中で、実際に遂行可能かどうかを厳しく評価します。
実現可能性とは、文字通り「その研究計画が現実的に実行できるか」という点です。評価者は以下の点をチェックします。
妥当性とは、「選択された研究方法が、設定された研究目的を達成するために適切であるか」という点です。例えば、特定の仮説を検証したいのに、その検証に適さないデータ収集方法や分析手法を選んでいては、研究目的の達成は困難です。
研究計画書では、これらの実現可能性と妥当性を、具体的な研究方法やスケジュールを示すことによって、客観的に示す必要があります。曖昧な記述ではなく、「どのようなデータを」「どのように収集し」「どのように分析するのか」を具体的に記述することで、計画が現実的かつ適切であることをアピールすることが求められます。
大学院での研究活動は、多くの場合、指導教員との緊密な連携のもとで進められます。そのため、研究計画書は、志願者の研究関心や計画が、指導を希望する教員の専門分野や研究テーマ、指導可能な範囲と合致しているか(マッチング)を判断するための重要な材料となります。
大学院側は、研究計画書を通じて以下の点を確認します。
もし、研究計画書の内容と指導教員の専門性が大きく異なっていたり、指導教員が持っていない特殊な設備や技術が必要だったりする場合、入学できたとしても、その後の研究指導が円滑に進まない可能性があります。これは、学生にとっても大学院にとっても不幸な状況です。
したがって、研究計画書を作成する際には、事前に志望する大学院や研究室のウェブサイト、教員の業績リストなどを確認し、自身の研究テーマがその環境に適しているかを十分に検討することが重要です。研究計画書は、単に自分のやりたいことを書くだけでなく、受け入れ側の環境との適合性を示すことで、入学後の円滑な研究生活の可能性を高める役割も担っているのです。
研究計画書を作成するプロセス、そしてその成果物である計画書自体は、あなたが将来研究者として活躍するために必要な基礎的なスキルセットを持っていることを示す機会でもあります。研究計画を立案し、それを論理的かつ説得力のある文書にまとめる能力は、研究キャリアを通じて様々な場面で求められるからです。
研究計画書の作成を通じて、以下のような研究者としての基礎スキルが試され、また、アピールできます。
これらのスキルは、大学院での研究活動はもちろん、将来、研究費申請、学会発表、論文執筆・投稿、共同研究提案など、研究者キャリアのあらゆる段階で必要不可欠です。研究計画書の作成に真摯に取り組むことは、単に入試や審査を突破するためだけでなく、あなた自身の研究者としての基盤を築くための重要な訓練となるのです。
研究計画書の「顔」とも言えるのが、研究テーマとそれを具体化したタイトルです。タイトルは、読者(審査員や指導教員)が最初に目にする部分であり、研究内容全体を簡潔かつ的確に伝える重要な役割を担います。魅力的で分かりやすいタイトルは、読者の興味を引きつけ、計画書全体への期待感を高める効果があります。
タイトルを設定する際のポイントは以下の通りです。
研究テーマの設定自体は、研究計画書作成の出発点です。自身の興味関心だけでなく、先行研究の状況や社会的な意義、指導教員の専門性などを考慮しながら、大学院で取り組むに値する、焦点を絞ったテーマを見つけることが重要です。良いタイトルは、明確な研究テーマ設定があってこそ生まれるものです。まずは研究内容をしっかりと固め、その核心を最もよく表す言葉を探してタイトルを練り上げましょう。
研究計画書における「研究の背景」は、なぜその研究を行う必要があるのか、その文脈と根拠を示す重要なセクションです。読者を納得させるためには、客観的な視点から研究の必要性を論証する必要があります。一般的に、「社会的背景」と「学術的背景(先行研究)」の二つの側面から記述します。
1. 社会的背景:
研究テーマが現代社会のどのような課題やニーズと関連しているのかを説明します。統計データや公的な報告書などを引用し、課題の重要性を客観的に示しましょう。主観的な意見や伝聞に基づく記述は避けるべきです。
2. 学術的背景(先行研究):
これまでにどのような研究が行われ、何が明らかになり、どのような課題が未解決なのか(リサーチギャップ)を明確にします。
この「研究の背景」セクションで、研究が取り組むべき問題(問題意識)が明確に提示され、続く「研究目的」へと自然につながる論理的な流れを作ることが重要です。
研究計画書の中核をなすのが「研究目的」です。これは、その研究を通じて「何を明らかにしたいのか」「何を達成したいのか」を具体的かつ明確に宣言する部分です。研究の背景で提示された問題意識やリサーチギャップに直接応える形で設定される必要があり、研究全体の方向性を決定づける羅針盤の役割を果たします。
研究目的を記述する際のポイントは以下の通りです。
研究目的が明確であればあるほど、その後の研究方法の選択や、期待される成果の予測も具体的に行うことができます。逆に、目的が曖昧だと、研究計画全体の説得力が低下し、評価も低くなる可能性があります。
「研究内容」のセクションでは、設定した研究目的を達成するために、具体的にどのような活動や分析を行うのかを記述します。研究対象や検証したい仮説などを明確に示すことが重要です。曖昧な表現を避け、研究で明らかにしたい点を具体的に記載しましょう。
さらに、このセクションでは、自身の研究が持つ「特色(独自性、オリジナリティ)」と「意義(重要性)」を明確にアピールすることが求められます。数ある研究提案の中から、なぜあなたの研究が注目に値するのかを説得力をもって示す必要があります。
研究の特色(独自性)のアピールポイント例:
研究の意義(重要性)のアピールポイント例:
これらの特色や意義を記述する際は、単に主張するだけでなく、研究の背景や目的と関連付けながら、具体的にどのような点がユニークで、どのような貢献が期待できるのかを論理的に説明することが重要です。他の研究との違いを明確にすることで、あなたの研究の価値を際立たせることができます。
「研究方法」のセクションは、研究目的を達成するための具体的な手段と手順を詳細に記述する、研究計画書の心臓部です。ここで重要なのは、なぜその方法を選択したのか(妥当性)、そしてその方法で計画を実行できるのか(実現可能性)を明確に示すことです。
具体的に記述すべき項目例は以下の通りです。
記述する際の注意点は以下の通りです。
研究方法のセクションが具体的で説得力に欠ける場合、研究全体の信頼性が揺らぎ、計画の実現可能性が低いと判断される可能性があります。
「期待される成果と効果」のセクションでは、提案している研究が完了した際に、どのような結果が得られると予想されるか、そしてその成果が学術分野や社会に対してどのような貢献(インパクト)をもたらす可能性があるのかを記述します。これは、研究の価値と将来性を示す上で重要な部分です。
記述する際のポイントは以下の通りです。
このセクションは、研究計画全体の締めくくりとして、読者(審査員)に研究の将来性や投資価値を感じてもらうための重要なアピールの場となります。研究目的と方法に基づき、説得力のある成果予測を示すことを心がけましょう。
研究計画書には、研究をどのように段階分けし、それぞれの段階にどれくらいの期間をかけて進めていくのかを示す具体的な「研究計画・スケジュール(タイムライン)」を含めることが一般的です。これは、研究全体の流れを俯瞰的に示すとともに、計画が現実的で実行可能であることをアピールするために重要です。
スケジュールを作成する際のポイントは以下の通りです。
研究計画・スケジュールは、単なる予定表ではなく、研究を計画的に進めるための「戦略」を示すものです。所属ゼミや履修科目なども考慮に入れながら、具体的で実現可能な計画を立てることで、研究遂行能力と計画性を効果的にアピールできます。
研究計画書の最後に必ず含めるべきなのが「参考文献リスト」です。これは、計画書内で引用または参照した文献(論文、書籍など)を、定められた形式に従って正確にリスト化したものです。このリストは、研究計画書全体の信頼性と学術的な質を担保する上で、極めて重要な役割を果たします。
参考文献リストの重要性は以下の点にあります。
作成方法のポイントは以下の通りです。
参考文献リストの作成は、学術文書としての体裁を整え、研究者としての信頼性を示す上で欠かせないプロセスです。細部まで注意を払い、正確なリストを作成しましょう。
評価される研究計画書を作成するための最も基本的な秘訣の一つが、「明確性」と「具体性」を徹底することです。研究計画書は、あなたの研究アイデアとその実行計画を、第三者に正確に伝え、理解してもらうための文書です。曖昧な表現や抽象的な記述が多いと、計画の意図が伝わらず、評価が著しく低下する可能性があります。
明確性(Clarity):
具体性(Specificity):
例えば、「持続可能な社会作りに関心がある」だけでは不十分です。それを実現するために、「〇〇地域における再生可能エネルギー導入の社会的受容性に関する要因分析」のように、具体的な研究課題に落とし込む必要があります。明確性と具体性を追求することは、あなたの思考の深さと計画の緻密さを示すことにもつながります。
評価される研究計画書は、単に各構成要素が揃っているだけでなく、全体を通して「論理的な一貫性」が保たれている必要があります。研究の背景で提示された問題意識、それを受けて設定された研究目的、その目的を達成するために選択された研究方法、そしてその結果として期待される成果、これら全てが矛盾なく、一つのストーリーとして繋がっていなければなりません。
論理的な一貫性が欠如している例としては、以下のようなケースが考えられます。
このような論理的な矛盾や飛躍があると、計画全体の説得力が著しく損なわれ、審査員は計画の妥当性や作成者の思考能力に疑問を抱くことになります。
論理的な一貫性を保つためには、以下の点を意識すると良いでしょう。
研究計画書は、あなたの論理的思考能力を示す場でもあります。細部に至るまで一貫性を追求し、説得力のあるストーリーを構築しましょう。
研究計画書において、研究アイデアの魅力や学術的な意義をアピールすることは重要ですが、それ以上に審査員が重視するのが「実現可能性(Feasibility)」です。提案されている研究が、絵に描いた餅ではなく、実際に計画通りに遂行できる見込みがあることを、客観的な根拠に基づいて示す必要があります。
実現可能性を客観的に示すためのポイントは以下の通りです。
実現可能性を示す上で重要なのは、単に「できる」と主張するのではなく、その根拠となる具体的な情報(利用可能なリソース、詳細な手順、現実的なスケジュールなど)を提示することです。自身の能力や環境を客観的に評価し、現実的な計画を立てることが鍵となります。
質の高い研究計画書を作成するための根幹をなすのが、「先行研究の調査」です。自身の研究テーマに関連する分野で、これまでにどのような研究が行われ、何が明らかになり、どのような課題が残されているのかを徹底的に把握することが、研究計画全体の質を大きく左右します。先行研究の調査が不十分だと、研究の新規性・独創性が示せず、研究の位置づけが不明確になり、議論の深みが欠け、研究者としての資質を疑われる可能性があります。
先行研究の調査を徹底するためには、以下のようなステップを踏むことが推奨されます。
先行研究の調査は時間と労力がかかる作業ですが、これを丁寧に行うことが、研究計画書の質を高め、説得力を持たせるための最も確実な方法です。計画書の「研究の背景」セクションで、調査結果を適切に引用しながら記述することで、あなたの研究分野への深い理解を示すことができます。
研究計画書は、単に研究の計画を示すだけでなく、その研究が持つ「独自性(オリジナリティ)」と「意義(重要性)」を審査員に効果的に伝え、納得してもらうための「企画書」でもあります。特に、競争的な環境においては、数多くの提案の中からあなたの研究を選んでもらうために、そのユニークな価値を明確にアピールすることが不可欠です。
独自性(Originality)のアピール:
あなたの研究が既存の研究と比べて「新しい」点は何かを強調します。
意義(Significance)のアピール:
その研究を行うことが「なぜ重要なのか」「どのような価値があるのか」を強調します。
これらの独自性や意義をアピールする際には、単に主張するだけでなく、先行研究との比較や具体的な根拠を示しながら、論理的に説明することが重要です。「なぜこの研究が今、ここで行われるべきなのか」を説得力をもって語ることで、審査員の興味と関心を引きつけ、高い評価を得ることが期待できます。
質の高い研究計画書を完成させるためには、十分な時間を確保し、繰り返し見直し(推敲)を行うこと、そして客観的な視点を取り入れることが不可欠です。
早期着手:
研究計画書の作成は、テーマ設定から修正まで多くのステップを含み、予想以上に時間がかかります。特に先行研究調査には時間がかかります。提出期限の4〜6ヶ月前には準備に取り掛かるのが賢明です。早期に着手すれば、じっくり取り組み、余裕を持って推敲できます。
推敲:
一度書き上げた計画書は完成ではありません。時間を置いて読み返したり、印刷して客観的に見直したりすることで、論理の飛躍、説明不足、表現の分かりにくさ、誤字脱字など、自分では気づきにくい問題点を発見できます。推敲を重ねることで完成度は向上します。
第三者の意見の活用:
自分一人では主観的な視点から抜け出せないことがあります。指導教員、先輩、同僚など、信頼できる第三者に草稿を読んでもらい、客観的な意見やアドバイスを求めることは非常に有効です。内容の妥当性、表現の分かりやすさ、誤字脱字など、多角的なフィードバックを得ましょう。予備校などの専門サービスを利用するのも選択肢です。第三者の視点を取り入れることで、計画書の質を飛躍的に高めることができます。
研究計画書を作成する際には、評価を下げる可能性のあるいくつかの「落とし穴」を避けるよう注意する必要があります。以下に、大学院などから敬遠されがちな研究計画書の特徴を挙げます。
これらの落とし穴を避け、明確で、具体的、論理的、かつ実現可能な研究計画を、先行研究を踏まえて記述することが、評価される研究計画書を作成するための鍵となります。
この記事を通して、研究計画書に関する疑問や、「何を書けばいいのか」「なぜ重要なのか」といった不安は解消されたでしょうか。
研究計画書とは、単なる提出書類ではなく、あなたの研究への情熱と能力を示す「企画書」であり、研究活動を成功に導くための「設計図」です。その重要性は、研究遂行能力の証明、計画の実現可能性と妥当性の提示、指導教員とのマッチング、そして研究者としての基礎スキルを示す点にあります。
質の高い研究計画書を作成するには、明確な目的設定、徹底した先行研究調査に基づいた背景記述、具体的で実現可能な研究方法、そして論理一貫性のある構成が不可欠です。さらに、研究の独自性と意義を効果的にアピールし、早期に着手して推敲を重ね、第三者の意見を取り入れることが、完成度を高める秘訣となります。
研究計画書の作成は、確かに骨の折れる作業かもしれません。しかし、このプロセスに真摯に取り組むこと自体が、あなたの研究者としての成長の糧となります。本稿で解説したポイントを参考に、自信を持って、あなたの研究への第一歩となる研究計画書を作成してください。
あなたの研究活動が実り多いものになることを願っています。

研究や論文執筆にはたくさんの英語論文を読む必要がありますが、英語の苦手な方にとっては大変な作業ですよね。
そんな時に役立つのが、PDFをそのまま翻訳してくれるサービス「Readable」です。
Readableは、PDFのレイアウトを崩さずに翻訳することができるので、図表や数式も見やすいまま理解することができます。
翻訳スピードも速く、約30秒でファイルの翻訳が完了。しかも、翻訳前と翻訳後のファイルを並べて表示できるので、英語の表現と日本語訳を比較しながら読み進められます。
「専門外の論文を読むのに便利」「文章の多い論文を読む際に重宝している」と、研究者や学生から高い評価を得ています。
Readableを使えば、英語論文読みのハードルが下がり、研究効率が格段にアップ。今なら1週間の無料トライアルを実施中です。 研究に役立つReadableを、ぜひ一度お試しください!
Readable公式ページから無料で試してみる

東大応用物理学科卒業後、ソニー情報処理研究所にて、CD、AI、スペクトラム拡散などの研究開発に従事。
MIT電子工学・コンピュータサイエンスPh.D取得。光通信分野。
ノーテルネットワークス VP、VLSI Technology 日本法人社長、シーメンスKK VPなどを歴任。最近はハイテク・スタートアップの経営支援のかたわら、web3xAI分野を自ら研究。
元金沢大学客員教授。著書2冊。