
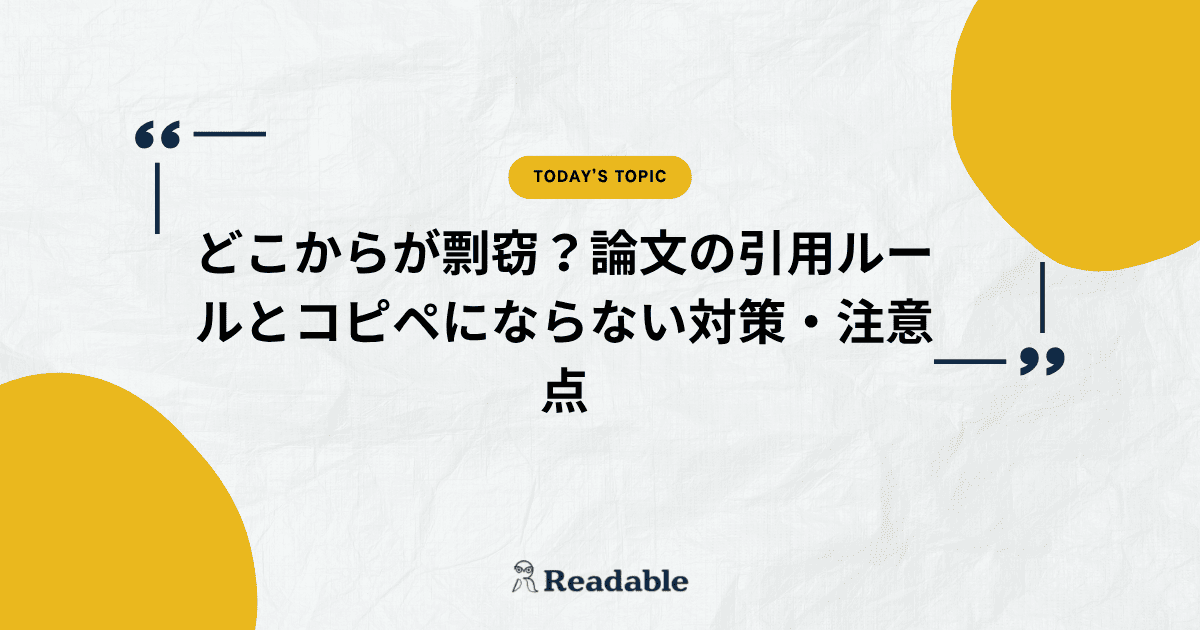
論文やレポートを作成する中で、「この書き方は剽窃にならないだろうか?」と不安に感じた経験はありませんか。引用のルールは理解しているつもりでも、どこまでが許容範囲で、どこからが不正と見なされるのか、その境界線は曖昧に感じられがちです。
意図せずに行ったコピペや安易な言い換えが、将来を左右する大きな問題に発展する可能性もゼロではありません。この記事では、そんなあなたの不安を解消します。
目次
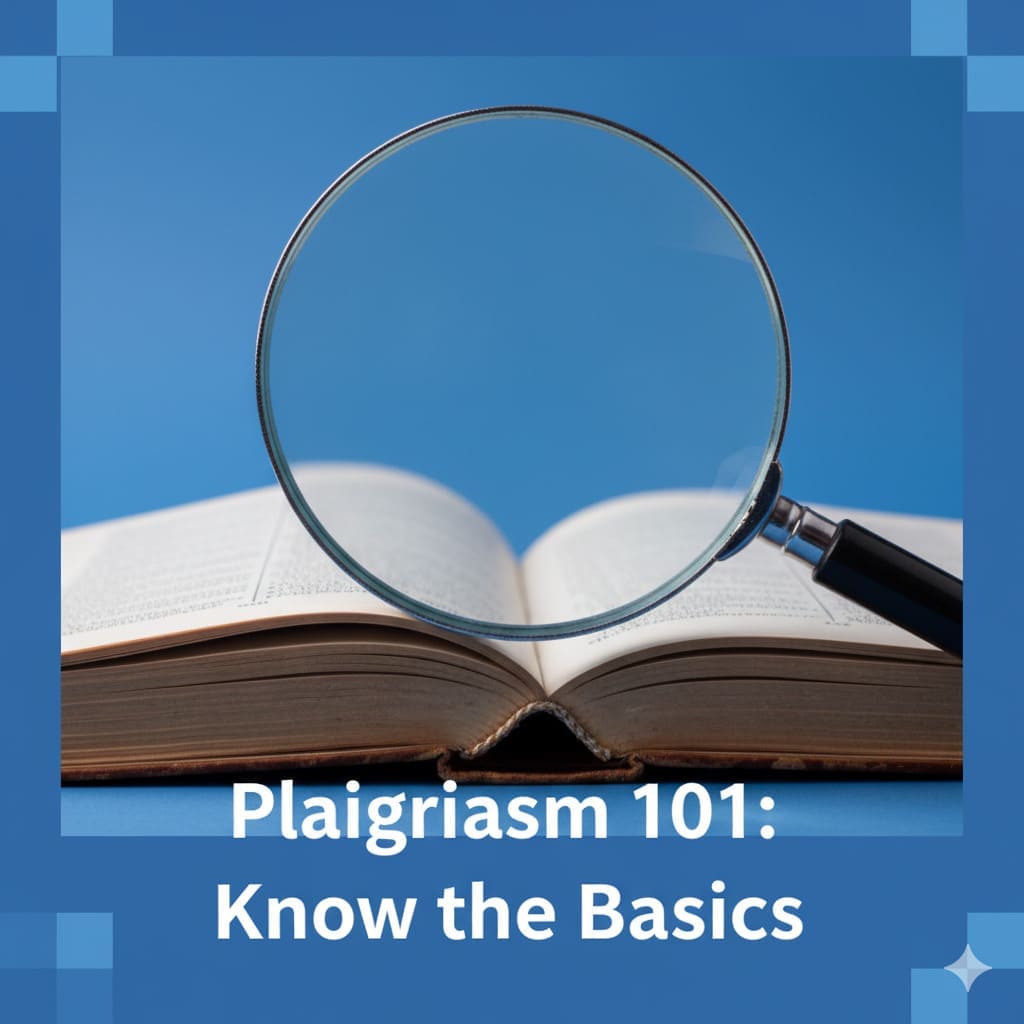
剽窃とは、他人の著作物(文章、アイデア、データなど)を、あたかも自分のものとして無断で使用する行為を指します。学術の世界では研究倫理に反する重大な不正行為と見なされます。
この剽窃としばしば混同される言葉に「盗用」と「盗作」がありますが、それぞれのニュアンスは少しずつ異なります。基本的にはほぼ同義で使われますが、文脈によって使い分けられることがあります。
これらの言葉の意味を理解することは、不正行為を避けるための第一歩です。特に学術論文においては、先行研究への敬意を払い、自身のオリジナリティを明確に示すことが不可欠であり、そのためにこれらの違いを正確に把握しておく必要があります。
| 用語 | 主な意味と使われる文脈 |
| 剽窃(ひょうせつ) | 他人の文章や学説、アイデアなどを自説であるかのように発表する行為。主に学術・研究分野で使われる不正行為を指す。 |
| 盗用(とうよう) | 他人のものを盗んで自分のものとして用いること。文章だけでなく、デザインやデータなど、より広範な対象に使われる。 |
| 盗作(とうさく) | 他人の作品をそのまま、または少しだけ手を入れて自分の名で発表すること。特に小説や音楽、美術などの芸術分野で使われることが多い。 |
例えば、小保方晴子氏は、理化学研究所でSTAP細胞論文の筆頭著者として一躍注目を浴びました。2014年、彼女の博士論文に対し、序論の約20ページが米国の公的な幹細胞説明サイトから無断で転載されていることや、実験画像に提供元以外のものが含まれていたこと、参考文献に不適切な引用や文字化けが多数含まれていたことが指摘されました。これを受けて早稲田大学は調査を実施し、不正行為を認定。2014年に博士号の取り消しを猶予付きで決定しましたが、猶予期間終了後の2015年に正式に博士号を取り消しました。この事件は日本の学術倫理問題に大きな影響を与えました。
このように、他者の知的財産を無断で流用する行為は、分野を問わず厳しく批判されます。結論として、論文執筆においては、剽窃・盗用・盗作、いずれの疑いも持たれないよう、情報源の扱いに細心の注意を払うことが求められます。
剽窃が他人の功績を盗む行為である一方、「引用」は先行研究に敬意を払い、自説の根拠を明確にするための正当な行為です。この二つを分ける決定的な違いは、「出典を明記し、自分の著作物と明確に区別しているか」という点にあります。適切な引用は、論文の信頼性を高め、議論を深めるために不可欠な要素です。
文化庁が示す引用のルールを満たさない場合、それは引用ではなく剽窃と見なされる可能性が高まります。具体的には、以下のルールが定められています。
例えば、ある学生がレポートで他者の論文の一節をかぎ括弧で囲み、出典も記載したとします。しかし、レポートの半分以上がその引用で占められていた場合、「主従関係」のルールに反し、剽窃と判断される可能性があります。あくまで議論の主体は自身の考察でなければなりません。
| 行為 | 目的 | 出典表記 | 評価 |
| 剽窃 | 他人の著作物を自分のものとして見せる | しない | 不正行為 |
| 引用 | 自説の補強や典拠を示す | する | 正当な学術行為 |
引用はルールを守って初めて成立する行為です。出典を明記していても、その方法やバランスを間違えれば、意図せず剽窃になってしまう危険性があることを常に意識する必要があります。
剽窃は研究倫理上の不正行為ですが、それが直ちに「著作権侵害」という法的な問題になるわけではありません。著作権法は、思想や感情を創作的に表現した「表現物」を保護する法律であり、単なる事実やデータ、アイデアそのものは保護の対象外です。この違いを理解することは、法的なリスクを避ける上で非常に重要です。
剽窃が著作権侵害にあたるのは、保護対象である「表現物」を無断でコピー(複製権の侵害)したり、インターネットで公開(公衆送信権の侵害)したりした場合です。一方で、他人の論文から「アイデア」だけを拝借し、全く新しい文章で表現した場合、それは倫理的には剽窃ですが、著作権侵害にはあたらない可能性があります。
例えば、大学の教員が自身の学術書で、他の研究者の論文から無断で文章を転載し、著作権侵害として訴えられた事例があります。東京地裁は2012年、転載行為を著作権侵害(複製権侵害)と認定し、教員に対して損害賠償の支払いを命じました。このケースでは、保護された「表現」を無断で利用したことが法的な問題となりました。
| 剽窃の種類 | 著作権侵害の可能性 | 理由 |
| 文章の丸写し | 高い | 他人の「表現」をそのまま複製しているため |
| アイデアの借用 | 低い | アイデア自体は著作権の保護対象外であるため |
| データの参照 | 低い | 事実・データは著作権の保護対象外であるため |
以上のように、全ての剽窃が著作権侵害となるわけではありません。しかし、学術の世界では、著作権侵害であるか否かに関わらず、剽窃行為そのものが研究者としての信頼を失う重大な不正行為であると認識しておく必要があります。
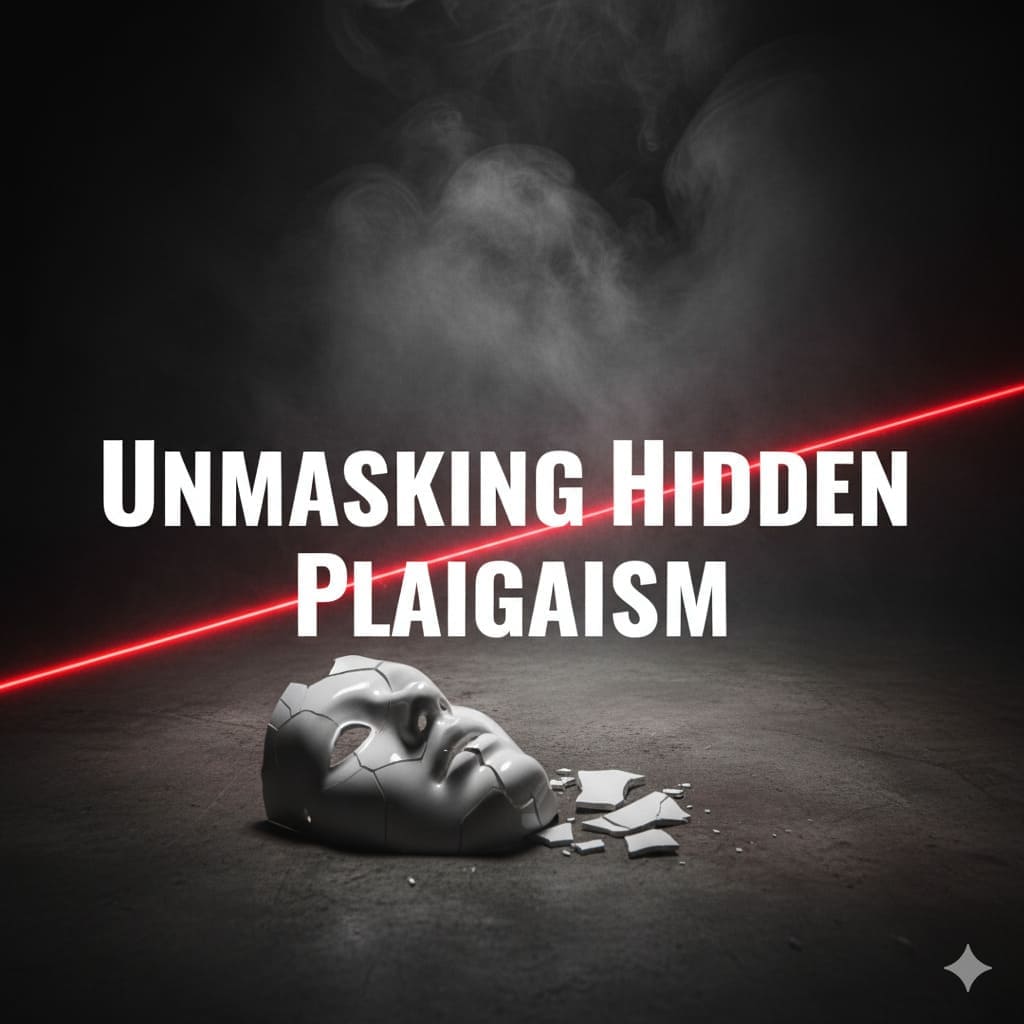
言うまでもなく、他人の文章を出典を示さずに丸写し(コピー&ペースト)する行為は、最も典型的で悪質な剽窃です。近年、高性能な剽窃検知ツールが大学などの教育機関で広く導入されており、「少しぐらいならバレないだろう」という安易な考えは通用しません。これらのツールは、インターネット上の膨大な情報や学術データベースと提出物を瞬時に照合し、類似箇所を数パーセント単位で検出します。
検知ツールは、単語の一致だけでなく、文章の構造やシソーラス(類義語)による言い換えまで見抜くアルゴリズムを備えています。そのため、数文字変えたり、語順を入れ替えたりする程度の小手先の修正は、ほぼ確実に見破られてしまいます。
例えば、早稲田大学は日本で大規模に剽窃検知ツール「Turnitin」を導入した大学の一つです。このツールの主な目的は、教員がレポートをチェックする際の負担を軽減し、不正行為の抑止力とすることです。そのため、学生が提出前に自由に類似度を確認できるわけではありませんが、大学として剽窃問題を重視し、ツールを活用している先進的な事例と言えます。
結論として、文章の丸写しは、たとえ短い一文であっても、極めて高い確率で発覚すると考えるべきです。剽窃が発覚した場合のリスクは計り知れません。自身のオリジナリティで文章を構成することが、論文やレポート作成における大原則です。
出典を示さずに他人の文章の単語や語順を少し変えて作り替える「巧妙な言い換え(パラフレーズ)」も、剽窃の一種と見なされます。これは「モザイク剽窃」とも呼ばれ、元の文章の骨格や論理展開が維持されている場合に該当します。単語を類義語に置き換えただけで、あたかも自分の文章であるかのように見せかける行為は、丸写し同様に不正行為です。
適切なパラフレーズは、元の文章のアイデアを完全に理解し、自分の言葉で再構築し、その上で出典を明記する必要があります。元の文章の構造に引きずられたまま単語だけを入れ替える作業は、適切なパラフレーズとは言えません。
実際に、海外の主要大学では、他者の論文の文章構造を維持したまま、いくつかのキーワードを類義語に置き換える行為(モザイク剽窃)は、剽窃として厳しく扱われます。例えば、米国のパデュー大学やマサチューセッツ工科大学(MIT)では、このような行為が学術不正にあたることが明確に規定されており、発覚した場合は処分の対象となります。
文章だけでなく、他人の論文に掲載されている図表やデータを無断で流用する行為も、重大な剽窃にあたります。特に、自身で実験や調査を行っていないにもかかわらず、他者のデータをあたかも自分で得た結果のように見せかけることは、剽窃であると同時に「捏造」や「改ざん」にも該当しうる、極めて悪質な研究不正です。図や表は、一目で分かりやすく情報を伝えられる強力なツールですが、その出典も文章と同様に厳密に管理しなければなりません。
図表を引用する場合は、文章の引用ルールとは別に、定められた手続きを踏む必要があります。
記憶に新しいSTAP細胞論文の問題では、主要な実験データ画像の一つが、執筆者自身の博士論文の画像と酷似しており、不適切な流用であると指摘されました。理化学研究所の調査報告書は、これを研究不正(捏造・盗用)と認定しました(出典:理化学研究所 調査報告書)。
この事例は、画像データ一つであっても、その取扱いが論文全体の信頼性を根底から覆しかねないことを示しています。結論として、図表やデータは論文の重要な構成要素であり、その出所は文章以上に厳格に明示する必要があります。他者の成果物を利用する際は、必ず定められたルールに従い、敬意を払って扱うことが鉄則です。
「自己剽窃(Self-Plagiarism)」とは、過去に自分が発表した著作物(論文や文章)の一部または全部を、適切な引用手続きなしに、新しい別の著作物で再利用する行為を指します。
自分の文章なのだから問題ないだろう、と考えるかもしれませんが、学術界ではこれも研究倫理に反する行為と見なされる場合があります。特に、研究の新規性や独創性が重視される学術論文において、過去の業績を新しいものとして見せかけることは読者を欺く行為と判断されます。
自己剽窃が問題となる主な理由は以下の通りです。
実際に、2017年に九州大学で、男性教授が自身の過去の論文や書籍などから適切な引用表記をせずに多数の文章を流用し、新たな論文として発表していたことが発覚しました。大学の調査委員会はこの行為を剽窃(自己剽窃を含む)と認定し、同教授を停職3か月の懲戒処分としました。
この事例は、たとえ自分の文章であっても、安易な再利用は重大な倫理違反となることを示しています。結論として、過去の自分の研究に言及する場合は、他人の著作物と同様に、必ず出典を明記して適切に引用する必要があります。自身の研究であっても、発表された時点ですでに公の資産であるという認識を持つことが重要です。

引用符(” ”)を使う直接引用の基本ルール
直接引用とは、他人の文章を一字一句変えずにそのまま抜き出して用いる方法です。原文の表現が特に重要であったり、正確に伝える必要があったりする場合に用います。直接引用を行う際は、その部分が引用であることを明確に示すために、厳格なルールに従わなければなりません。最も基本的なルールは、引用部分を引用符(日本語では通常「」や『』)で囲むことです。
引用符で囲むことに加えて、誰の、どの著作物から引用したのかを出典として正確に記載する必要があります。これにより、読者は元の文脈を確認でき、あなたの論文の信頼性も向上します。
例えば、「イノベーションとは、…新しい結合の遂行である」というヨーゼフ・シュンペーターの著名な定義を正確に示したい場合、直接引用は非常に効果的です。この一節は彼の主著『経済発展の理論』からのものであり、このように表記することで、読者はこの定義がシュンペーターの著作からの正確な引用であることを瞬時に理解できます。(※引用する際は、自身が参照した版の年号とページ番号を正確に記載する必要があります。)
結論として、直接引用は、原文の力を借りる強力な手法ですが、その分、厳密な形式ルールが求められます。引用符と出典表記はセットであると覚え、常に正確な記述を心がけることが剽窃を防ぐ鍵となります。
間接引用とは、他人の著作物の内容やアイデアを、自分自身の言葉で要約したり、説明し直したりして記述する方法です。論文やレポートでは、他者の議論を整理して紹介する際に多用され、文章の流れをスムーズに保つ効果があります。ただし、自分の言葉で書くからといって、出典表記が不要になるわけではありません。アイデアの出所を明記しなければ、それは剽窃となります。
間接引用を適切に行うには、元の文章を完全に理解し、そのエッセンスを損なうことなく、自分の表現で再構築する能力が求められます。単語を数個入れ替えるだけの安易なパラフレーズは、剽窃と見なされるため注意が必要です。
例えば、ある研究者が行った調査結果を紹介する場合、「山田(2025)は、都内の大学生を対象とした調査から、SNSの利用時間が長い学生ほど、自己肯定感が低い傾向にあることを明らかにした」というように記述します。このように、内容を要約して示すことで、文章の表現を統一し、読者の理解を助けることができます。結論として、間接引用は論文執筆において非常に有用なテクニックですが、必ず「自分の言葉で再構築する」ことと「出典を明記する」ことの2点を徹底する必要があります。このルールを守ることが、アイデアの盗用を防ぎ、誠実な学術態度を示すことにつながります。
参考文献リストは、論文やレポートの末尾に記載される、本文中で引用・参照したすべての文献の一覧です。このリストは、あなたの議論の根拠を読者に示し、さらなる調査への道筋を提供するという重要な役割を担っています。リストの記載方法には、分野や投稿先の学術雑誌によって定められた様々なスタイル(書式)があり、そのルールに正確に従うことが求められます。不正確な、あるいは不完全なリストは、論文全体の評価を下げるだけでなく、剽窃を疑われる一因にもなりかねません。
代表的な引用スタイルには、以下のようなものがあります。指導教員や投稿規定を必ず確認し、指定されたスタイルで統一することが鉄則です。
例えば、書籍を参考文献として記載する場合でも、スタイルによって表記順序や句読点の使い方が異なります。
| スタイル | 書籍の記載例(著者名、発行年、書名、出版社) |
| APA | 山田, 太郎. (2025). 『剽窃の社会学』. 東京: 学術出版. |
| SIST | 山田太郎. 剽窃の社会学. 学術出版, 2025, 215p. |
このように、細かなルールが定められているため、自己流で記載することは絶対に避けるべきです。
最近では、文献管理ツール(例:EndNote, Mendeley)を使えば、引用スタイルを選択するだけで自動的にリストを作成でき、間違いを大幅に減らすことができます。
結論として、参考文献リストは、論文の信頼性と誠実さを示すための最終的なチェックポイントです。指定されたスタイルを正確に守り、本文中の引用とリストに過不足がないか、細心の注意を払って作成することが、剽窃を完全に回避するために不可欠です。
剽窃チェックツールは、意図しない剽窃を防ぎ、レポートや論文の品質を向上させるための強力な味方です。これらのツールは、提出された文章をインターネット上の膨大なデータベースと照合し、類似性の高い箇所をハイライト表示してくれます。
多くの大学では、学生や教員が利用できる公式ツールを導入しており、提出前に自己チェックすることが推奨されています。ツールを正しく活用することで、引用漏れや不適切なパラフレーズといった、うっかりミスによる剽窃を未然に防ぐことができます。
ツールを選ぶ際は、その機能や対象とするデータベースを理解することが重要です。
これらのツールは、類似度をパーセンテージで示してくれますが、その数値が独り歩きしないよう注意が必要です。例えば、法学の論文で条文を多数引用した場合、類似度は必然的に高くなります。
重要なのは、ツールが示した類似箇所を一つひとつ自分の目で確認し、それが適切な「引用」なのか、修正が必要な「剽窃の疑いがある箇所」なのかを主体的に判断することです。ツールはあくまで判断材料を提供する補助的な存在であり、最終的な責任は執筆者自身にあります。
結論として、剽窃チェックツールは、執筆プロセスの最終段階で非常に有効な手段です。自身の文章を客観的に見直す機会として積極的に活用し、論文の誠実性と信頼性を確保することが、剽窃を回避する上で賢明な方法と言えるでしょう。

単位の不認定や学位の剥奪といった学業上の処分
学生にとって、レポートや論文での剽窃が発覚した場合の代償は極めて大きいものとなります。多くの大学では、剽窃をカンニングと同様の不正行為(試験における不正行為)とみなし、学則に基づいて厳格な処分を下します。
最も軽い処分でも当該科目の単位不認定、重い場合には、その学期の全履修科目の単位が無効となることや、停学処分に至るケースもあります。そして、最も重い処分が、学位の剥奪です。
卒業論文や修士論文、博士論文で剽窃が発覚した場合、一度授与された学位が取り消されることがあります。これは学歴そのものを失うことを意味し、就職先や社会的な信用にも深刻な影響を及ぼす可能性があります。
実際に、2014年に東京大学で、中国人留学生の博士論文に広範囲な盗用があったとして、一度授与した博士号を取り消すという事例がありました。大学の調査では、論文の約3分の1にあたる部分で、他者の論文からの盗用が認められました。
学位取得という大きな目標の達成間近で、あるいは達成した後に、たった一度の不正がすべてを無に帰すことになりかねないのです。
結論として、学生にとって剽窃は、単位や卒業といった将来に直結する問題です。軽い気持ちで行ったコピペが、取り返しのつかない事態を招くリスクがあることを、常に肝に銘じておく必要があります。
研究者にとって、論文における剽窃は、そのキャリアを根底から揺るがす致命的な行為です。不正が発覚した場合、当該論文は学術雑誌から「撤回(Retraction)」されます。論文撤回は、その研究成果が科学的に無効であることを公に宣言するものであり、研究者としての信用の失墜に直結します。一度失った信用を回復することは極めて困難であり、その後の研究活動に深刻な支障をきたします。
さらに、不正行為が行われた研究が、国からの競争的資金(科学研究費助成事業など)によって行われていた場合、研究費の返還が命じられることがあります。また、一定期間、競争的資金への申請資格が停止されるという重いペナルティも科せられます。
例えば、東京大学の分子細胞生物学研究所の元教授らの研究室で、大規模な論文の捏造・改ざんが発覚し、最終的に40報以上の論文が撤回されるという深刻な事態に至りました。東京大学の調査委員会は2014年に最終報告書を公表し、元教授に対して研究費約2,570万円の返還勧告を行うなど、厳格な対応を取りました。
これは、研究不正がいかに重大な結果を招くかを示す象徴的な事例です。結論として、研究者にとって剽窃は、単なる倫理違反にとどまらず、自身のキャリア、経済的基盤、そして研究者コミュニティ全体の信頼を損なう行為です。誠実な研究活動こそが、自身のキャリアを守る唯一の道なのです。
剽窃は、学術的な倫理違反や所属機関での処分に加えて、法的な責任、特に民事上の責任を問われる可能性があります。前述の通り、剽窃が著作権で保護された「表現」の盗用にあたる場合、著作権侵害として、元の著作物の権利者から訴訟を起こされるリスクがあります。
その場合、裁判所から以下のような請求が認められる可能性があります。
刑事罰については、著作権侵害は「親告罪」であり、権利者が告訴しない限りは罪に問われないのが原則ですが、悪質なケースでは懲役刑や罰金刑が科される可能性もゼロではありません。
| 責任の種類 | 内容 | 根拠となる法律など |
| 民事責任 | 差止請求、損害賠償請求、名誉回復措置 | 著作権法、民法 |
| 刑事責任 | 懲役刑、罰金刑(親告罪が原則) | 著作権法 |
| 学術的責任 | 論文撤回、学位剥奪、懲戒処分 | 各大学・研究機関の規則 |
実際に、ウェブサイトの文章を無断で丸ごとコピー(転載)された運営者が、転載した側に対して損害賠償を求めた訴訟は数多く起こされています。裁判所は、このような行為を著作権侵害と認定し、賠償を命じた判例を積み重ねています。個別の判例を挙げるまでもなく、ウェブコンテンツの無断転載が法的なリスクを伴うことは、弁護士や法律事務所のウェブサイトでも広く注意喚起されています。
学術論文に限定された判例は多くありませんが、基本的な法的構造は同じです。結論として、剽窃は単に「怒られる」といったレベルの問題ではなく、金銭的な賠償責任や法的な措置につながる現実的なリスクを伴う行為です。法的なトラブルを避けるためにも、著作権への正しい理解と、引用ルールの遵守が不可欠です。
この記事を通して、「どこからが剽窃になるのか」というあなたの疑問や不安は解消されたでしょうか。
本記事では、まず剽窃の基本的な定義や引用との違いを解説しました。次に、コピペや安易な言い換えなど、剽窃と見なされる具体的なボーダーラインと事例を確認し、それを防ぐための正しい引用ルールと対策を具体的に示しました。最後に、万が一剽窃が発覚した場合の学業上・研究上の重大なリスクについても触れました。
論文執筆は、先行研究という巨人の肩の上に立ち、新たな知見というレンガを一つ積み上げる誠実な作業です。正しい知識を武器にすれば、剽窃を恐れる必要は決してありません。自信を持って、あなたの研究を世界に示してください。

研究や論文執筆にはたくさんの英語論文を読む必要がありますが、英語の苦手な方にとっては大変な作業ですよね。
そんな時に役立つのが、PDFをそのまま翻訳してくれるサービス「Readable」です。
Readableは、PDFのレイアウトを崩さずに翻訳することができるので、図表や数式も見やすいまま理解することができます。
翻訳スピードも速く、約30秒でファイルの翻訳が完了。しかも、翻訳前と翻訳後のファイルを並べて表示できるので、英語の表現と日本語訳を比較しながら読み進められます。
「専門外の論文を読むのに便利」「文章の多い論文を読む際に重宝している」と、研究者や学生から高い評価を得ています。
Readableを使えば、英語論文読みのハードルが下がり、研究効率が格段にアップ。今なら1週間の無料トライアルを実施中です。 研究に役立つReadableを、ぜひ一度お試しください!
Readable公式ページから無料で試してみる

東大応用物理学科卒業後、ソニー情報処理研究所にて、CD、AI、スペクトラム拡散などの研究開発に従事。
MIT電子工学・コンピュータサイエンスPh.D取得。光通信分野。
ノーテルネットワークス VP、VLSI Technology 日本法人社長、シーメンスKK VPなどを歴任。最近はハイテク・スタートアップの経営支援のかたわら、web3xAI分野を自ら研究。
元金沢大学客員教授。著書2冊。