
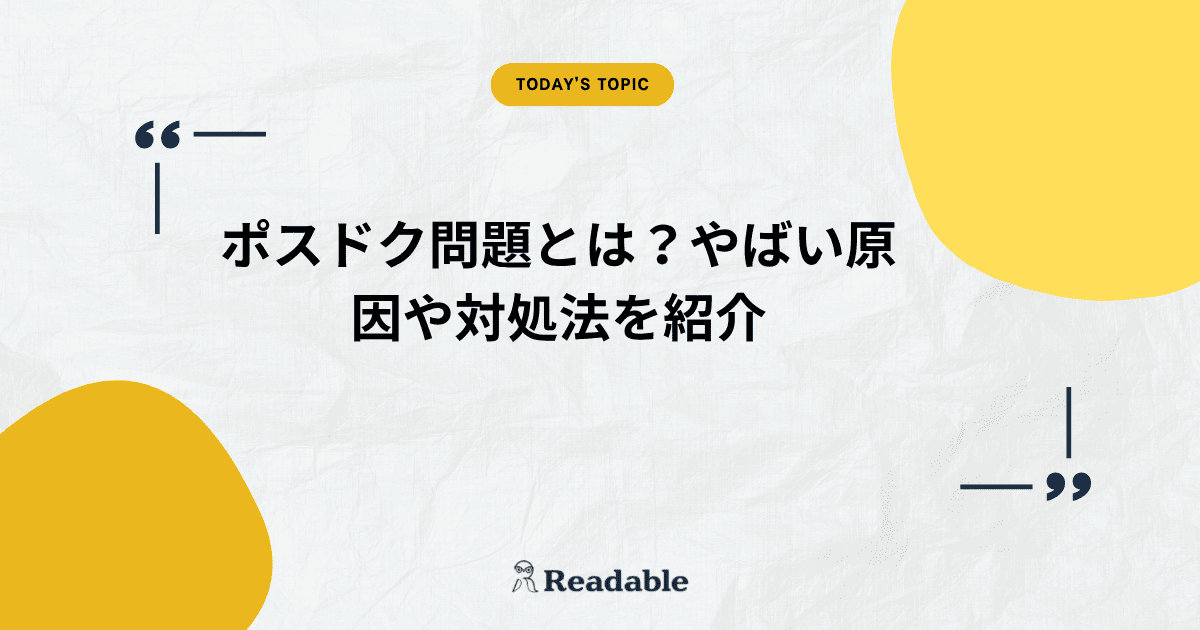
ポスドク問題とは、日本の大学がかかえる構造的な課題のひとつです。
ながらく大学の問題として、文科省のみで検討されてきましたが、少子高齢化の昨今、国家的な課題としても検討する時期に来ています。
本記事ではポスドクの問題について、その問題が発生する原因から、注意すべきポイントや対処法まで検討します。

ポスドクとも呼ばれるポストドクターは、博士号を取得した人が、大学や研究機関などの正規の職員や研究員として採用される前の、任期付きの大学研究員のことです。
ポスドク問題とは、特に国内でよく使われる用語で、正規就職前の博士号取得者が滞留している状況から生じています。不安定な雇用状況、低い給与やキャリアの確立が難しいという、いわゆるポスドクから起因する問題が現在でも指摘されているのです。
ポスドクは、欧米各国では一種のトレーニング期間として浸透しており、任期を終えた後は正規の研究員として研究を進めていくのがふつうで、それほど深刻な問題とはなっていません。
欧米と日本の違いの要因のひとつが、国内では博士号取得者があまり重要視されないという状況や風潮によるものとなっています。もちろん大学内に限っていえば、博士号取得はいわば入門資格のようなもので、ないと致命的ですが、社会や国内企業では以前はそれほど重視されていませんでした。
これに対して、欧米では博士号を持っていないと、研究者や開発技術者としては認められません。当方もバブルの時期にアイビーリーグの大学に留学したことがありますが、最初はまったく当該分野の研究員としても認められず苦労した経験があります(その後、国内で論文博士号を取得しましたが)。国内企業の研究所での実績等を話して理解してもらったこともあります。
米国での大学付属研究所での話ですが、実は国内企業、特に大手企業でも同様なものでした。80年代後半に国内企業から社外留学したのですが、留学時には関係先の大手企業をかなり訪問する機会がありました。
先方企業の中央研究所のみならず、本社や主力工場なども訪問したのですが、研究所と本社ではほとんどがドクターの称号を持っていました。名刺交換するわけですが、ほとんどの方がドクターとかかれているのでうらやましく思ったこともあります。
さらに重要なのは先方は、ドクターでもないものを日本では派遣していると思われてしまったことです。ほとんどが技術系ですが、本社では技術系以外でも、法務部門などドクターが多かった印象があります。
なにがいいたかったかというと、ドクターでないと独立の専門家として米国では認められないということです(米国では、この辺の弊害が最近はあるのかもですが・・・)。日本では2000年代以降になって徐々にようやく浸透してきた感があります。
最近は、修士課程修了者ではないと大手企業でも、技術系としては採用されないという状況がでてきましたが、博士号についてはあまり理解が浸透したとはいえません。昨今になって、ようやく博士号取得者を採用しようという気運が、AI研究やIT開発などを中心として広がりつつあるのは歓迎すべきことです。
ポスドクとは、いわば院生と正規の助教の中間に位置づけられた任期付きのポジションであり、そこから正規の大学職員になれるのはひとにぎりの人になります。
文科省系の研究所では、実はこれらの問題を把握するため「ポストドクター等の雇用・進路に関する調査」を定期的に実施しており、「ポスドク」を次のように定義しています。
引用元:「ポストドクター等の雇用・進路に関する調査(2021年度実績)」[調査資料-337]を公表しました(3/22) | 科学技術・学術政策研究所 (NISTEP)
※博士の学位を取得した者又は所定の単位を修得の上博士課程を退学した者(いわゆる「満期退学者」)のうち、任期付で採用されている者で、①大学や大学共同利用機関で研究業務に従事している者であって、教授・准教授・助教・助手等の学校教育法第92条に基づく教育・研究に従事する職にない者、又は、②研究開発法人等の公的研究機関(国立試験研究機関、公設試験研究機関を含む。)において研究業務に従事している者のうち、所属する研究グループのリーダー・主任研究員等の管理的な職にない者をいう。
このようなポスドクの問題は、かなり以前から国内では発生していました。ポスドクは、研究者としてキャリアを築くための重要なステップですが、現在もその状況は課題が山積みの状態です。このため現状を理解するのは当然ですが、適切な対応を講じることが望まれています。
以下の記事では、ポスドクについてより詳しく解説しています。

ポスドクがやばい原因としては、どのようなものがあるのでしょうか。
ポスドクには、欧米と違って安定したキャリアパスが確立されていないのが、国内の現状ともなっています。博士課程修了者の数に対して、そもそも就職先である大学や研究機関、民間企業の研究員のポストにはかなり限りがあります。このため、就職が困難な博士課程修了者が当面の進路として、したかたなくポスドクを選択する傾向にあるといえます。
先ほどの研究所の調査によれば、ポスドクでは、特に30代前半の男性が多いことが伺えます(下記のグラフ参照)。
引用元:ポストドクター等の雇用・進路に関する調査 (2021 年度実績)
これは、大学院を修了し博士号をとった直後の人がかなり多いことによります。ただ問題なのは、40代前半以降も一定の人数があり、これらの方々が滞留しているという課題もあります。
2019年度でポスドクを継続している人は約7割であり、大学で教授やそのほかの研究開発職などに就職できたのは約1割強となっており、依然厳しい状況であるといえます。またポスドクが専攻する分野においてもかたよりがあり、工学系と比べて理学系などの基礎的分野の方が、その割合も高くなっているようです。
ポスドク問題には、まず雇用とその給与に関する課題があります。生活費を含めた経済的な課題や社会保障などの課題もあり、さらにはそれらに起因する精神的なストレスも生じてしまいます。
年収については、同じ文科省研究所での調査によると、
2021 年度におけるポストドクター等の月額給与水準は、35 万円以上 40 万円未満の者が最も多く 2,293 人(16.8%)、次いで 30 万円以上 35 万円未満が 2,241 人(16.4%)であった。一方、20 万円未満の者は 2,085 人(15.2%)であった。
となっており、大学卒業後に正規の就職をした人たちと比べて低い金額です。昨今は新卒者の給与が、売り手市場などの要因により大きく増加しています。このためポスドクとの差はかなりの程度となっていると推定されます。このようにポスドクには、大学が現在おかれている状況、特にひずみの部分を写しだす、課題が集中しているともいえます。国としても現状調査だけではなく、なんらかの効果的な施策を打ち出す必要性があるといえるのではないでしょうか。
このようなポスドクが抱える課題として、雇用が不安定であることが一番の問題となっています。
たとえば継続雇用が前提ではない大学での募集もあり、更新されない可能性もあります。さらには国からの研究費用には、長期継続という形式のものが極端に少なくなっています。非常勤的な職種がそのほとんどを占めているのです。
学術振興会からの研究員制度も毎年募集はありますが、数年以内の短期が中心で、またかならず採用されるとも限りません。給与としては毎月一定の金額がもらえますが、全員ではなく、研究者の養成が主眼となっており、必ずしも正規採用に結びつくものではありません。
このような学術振興会の制度は、ポスドクにとっても有益な制度であり、大学院修了者は現在もお世話になっていますが、あくまで短期的な支援策といえます。大学院の国内出身者に、国家的な支援があるとはいえない状態が続いているのです。
大学での研究費用から、ポスドクの一部に支援が実施されていますが、それも低額で不定期という課題も生じています。文科省や内閣府などの研究費用に大学側が応募することがあり、かなりの高額の研究開発費用が数年にわたって提供されることはあります。
このような制度も大学側にとっては、研究遂行上、大切な予算となっています。このような予算で、一部のポスドクの雇用も可能な場合がありますが、これも短期であり、予算の都合で雇用が途切れる可能性もあります。またこのように大学等に採用されても給与が低いという欠点があります。
最近、米国からの研究員などを招聘するという計画がかなりの大学で持ち上がっています。
ただ人件費はかなりの高額となっており、助手クラスの研究員でもかなりの高額で、国内とはまったく違います。たとえば、日本の国立大学とは一概には比較できませんが、米国の大学における共同研究先の企業から支出される研究費用は、国内大学に対するものとおおよそ一桁、金額が違います。
当然、研究に従事する人件費でも一桁ではないですが、かなりの数倍以上の開きがあります。また実は、国内企業も米国ではかなりの研究費を大学に投資していますが、国内の国立大学あてにはまだまだといえるレベルです。
当方も工学系のある国立大学に9年間勤務しましたが、国内大手企業からたいがい一桁以上違う金額が、米国の大学などに投資されるのを見てきました。同等な金額までとはいいませんが、少なくとも数倍の研究費を投資する方が、国内での技術開発力を維持することにもつながるのではないでしょうか。
卵が先か、鶏が先かという議論はありますが、国内企業からの大学への研究費増額により、結果的に大学の博士人材への投資にもつながります。研究開発費の税額控除も既にありますが、国内大学あての支出をさらに国でも税額を優遇するとかも考えるべきです。
国力がすでに衰退してきている今、このような省庁を超えた支援を検討すべきです。財務省も税金をとるばかりではなく、これから活力ある人材への投資を加速しないと、将来、国内で税金を徴収できる余地がだんだん少なくなってしまいます(結果的に税金収入も含めてジリ貧になります)。この辺の全体をみた国家戦略は、以前の米国の力の源泉でしたが、アジアの国でも国家的に推進している国が複数あります。
昨今、国際卓越研究大学では、このような高額の費用を招聘に利用してもよい、ということになっているようですが、もとは税金から支出されたものであり考えものです(卓越大学ではファンドを運用することになっているので、その運用益なら、わからない訳ではありません)。
ただ文科省が推進する卓越大学の制度は今年はじまったばかりで、ファンド運用益はまだないはずです。極端にいえば、国内人材を採用するならかなりの多数が雇用できることになり、教授級だけではなく、優秀なポスドクなら非常に多数ということにもなります。
もちろん海外人材を招聘して、研究を加速あるいはノーベル賞級の成果につなげるという目標もあるのかもしれませんが(なおノーベル賞受賞の先生でも、いろいろな基礎研究分野を幅広く支援するべきというご意見の方もかなりおられます)。

ポスドクの現状と課題について、国の調査などをもとにみてきましたが、いかがでしょうか。ここでは、ポスドク問題に関する注意点と、その対処法についてもふれてみます。
昨今は新卒者の給与水準も高くなっているので、大学院にはいかずそのまま就職する若者も多くなっていると推測されます。
就活せずに大学院に進んだとしても、酷なようですが、将来的に就活かポスドクかの選択を迫られるときが訪れることになります。自分がほんとうにやりたい研究は何か、自身の問題としても考えておくことが大切です。もう少しいわせてもらえば、研究というものは安易なものではありません。本コラムでも、修士に加えて、課程博士の問題や、さらには論文博士についても問題点を指摘してきました。
(これらの問題については、本コラム関連記事も参考にしてください)
その中で指摘している一部の課題としては、研究遂行に対する研究者自身のこころ構えがあります。自身がどうしても研究していきたいという意思がなければ、大学卒業は別として、大学院への進学から考えていくことも必要です。
研究に対する熱意と将来的な研究計画がなければ、安易にポスドクへの道を選択することは、避けたほうがいいでしょう。まずは今続けようとしている研究に誠実に向き合い、自分が本当にやりたいことなのかどうかを吟味することが大切です。
昨今、大学院生でも留学生ではありますが、社会的な問題が生じている例も多くなっています。性善説だけでは、以前は聖域とされた大学や大学院と、その中で研究したり働いている、大学院生やポスドクの問題は解決できません。
文科省系の研究所では、ポスドク問題に関する論文で、次のように指摘しています。
日本では、1996年に策定された「第1期科学技術基本計画」においてポストドクター等1万人支援計画が策定された後、任期制の導入や流動化政策の推進によりポスドクの人数は増加した。ポスドクの総数自体は2008年以降減少傾向にあるが、現在でも1万人を超える水準で推移している(図表1)。
引用元:ポストドクター等の雇用・進路に関する調査 (2021 年度実績)
当該調査では、ポスドク支援計画の不備についても指摘しています。国内のポスドクは、2004年以降、右肩上がりで増加していますが、忘れてはならないのが、2004年時点ですでに1万人以上のポスドクが存在しているという事実です。
このグラフでは、1996年以前のデータがありませんが、90年代前半にもすでに1万人はいたものと推定されます。これに輪をかけて、出口問題を考えなかった「ポストドクター等1万人支援計画」が問題を複雑化させたといえるでしょう。この計画は、国内でよくある戦略の失敗例ともいえるかもしれません。経産省などがかなり以前に推進した、出口を考えていなかった太陽光発電などでも同様な例があり、現在は日本は太陽光発電の後進国となっています。
科学技術基本計画というのは、国家戦略の一貫を担っていますが、我が国ではこれが不十分なことがあります。国家戦略の策定が上手な国は、従来の米国以外にも、アジアでも複数あります。共通しているのは、入口から出口まで、すなわち研究開発から生産技術確立まで一気通貫して、いわばサプライチェーンのように、すべてを国家が支援していることです。補助金などももちろん入ります。
とかく補助金というと、国内では国内企業以外の海外企業に影響がないように、なるべく穏便にという雰囲気がありますが、米国などでもかなり違います。最近の脱炭素分野まで含めて、エネルギー省DOEが、桁違いの開発予算を付けている場合が多いのです。
当方も大学で知財関連の仕事をしていたため、その予算規模を調査してびっくりしたことがあります。太陽光発電を研究から生産まで含めて、国家的に推進し成功した国も既にあります。
最近はやりのいろいろな農業分野でも、農業関連の基本計画は、EU農業戦略と比較しても実施予定項目はそれほど劣っていません。但しEUからは、全体工程の達成水準が20年~30年遅れの計画となっているようで、まったなしの状況です。
ポストドクター等1万人支援計画も、戦術としては間違っていませんでした。ただ出口の問題、すなわちポスドクの就職問題を考えていなかったので、国家戦略として成功しなかったともいえます(日本では、国家戦略として成功したものがほとんどないのが実情です)。
ポスドク問題には、どのように対処したらよいでしょうか。このような日本のひとつの縮図ともいえるポスドク問題には、解決策があるのでしょうか。
文科省では、ポスドクの現状について、以下のような調査レポートも公開しています。
「ポストドクターのキャリアと課題-全国調査から読み解く日本のポスドクの現状-」
引用元:
「科学技術の進展に伴い、イノベーションの担い手となる人材の養成は先進諸国における喫緊の課題となっている。
我が国においても、内閣府総合科学技術・イノベーション会議(CSTI)や文部科学省の科学技術・学術審議会を通じて、博士人材や若手研究者に対する処遇改善や研究環境整備に向けた様々な施策が進められている。
しかしながら、博士課程を修了し、大学や研究機関等で任期付きの研究員として働くいわゆるポストドクター(ポスドク)に関しては、雇用形態の多様さや実態把握が困難であることもあり、施策や支援が十全とは言えない状況が続いている。
また、先進諸国においても、2000年以降博士号取得者の増加やプロジェクトベースの研究の増加に伴い、アカデミアにおける有期雇用職が増大し、任期付きで研究職を転々とする「リサーチ・プレカリアート」の問題が顕在化している。」
さらには、「若手、中堅の研究者が長期に亘って不安定な雇用を余儀なくされ、アカデミアのキャリアパスにボトルネックが生じたことで、才能ある研究人材は条件の良い産業界でのキャリアを選択するようになり、アカデミアから良質な研究人材が流出した。
また有期雇用の研究者が限られた雇用期間中に成果をあげるためにリスクの高い研究を回避することは、斬新な発想やイノベーティブな研究を妨げることにもつながる。」
として、アカデミアでの研究成果の維持の問題もあげています。むしろ研究人材が産業界において、活躍することは望ましいことといってもよいでしょう。
一国の経済や科学技術が興隆するためには、大学のみならず産業界での展開が求められています。アカデミアの中に優秀な人材を閉じ込めておくのではなく、産業界を通じて活用していくことが、たとえば従来の米国産業の力の源泉ともいえます。
現在のデジタル大国としての基盤を築いたのは、大学からスピンアウトした、古くはビル・ゲイツ氏などを初めとした優れた人材があったからといえます。たとえばバイオ分野でも、コロナワクチンの開発などは米国の大学と医薬ベンチャーやメーカーの協力があったから、米国ではじめて実用化ができたともいえます。
どのような経緯か詳細はわかりませんが、mRNAワクチンに集中して投資するという戦略を採用したのはさすがといえます(これによりコロナウイルスへの対応が日本を含め、世界で加速されました。
なおRNAに特に注目するのは、生物学的にも理屈が通っています)。日本ではこの頃、DNAワクチンも含めて、国内では総花的な研究開発を実施していただけでした。大学発のベンチャー、いわゆるスタートアップが米国産業界の実力をささえているともいえます。
文科省研究所での調査では、欧米での問題点をも指摘していますが、日本ではまだまだといった状態ではないでしょうか。国内企業においては、博士号取得者が活躍されるような状況となったのはつい最近ともいえるかもしれません。
当方が在籍した国内企業は大手でしたが、博士号取得者を採用するようになったのは、それほど古いことではありません(通常の修士課程出身者採用でさえ2000年代以降です)。
最近は、IT人材という用語が産業界でも盛んに使われるようになっており、AI応用や深層学習法の実用化なども実施されるようになっています。むしろ国の施策としても、文科省とか経産省ごとにまとまるのではなく、有用な人材をいかに活用するかという観点から考えてもらいたいものです。
IT人材分野以外の分野でも、産業界と協力できる分野はその振興をすすめるべきです。IT X 〇〇人材のような複合人材への展開も考えられます。もちろん純粋な基礎的分野での博士号取得も必要でさらに推進すべきですが、このような分野では大学や国の研究機関での採用に限定されることが多く、人数をそれほどかけるのは難しくなっています。
このような分野に博士号取得者が集中するのは、大学側でもポスドク側にとっても好ましいことではありません。出口戦略を含めた、それなりの国家戦略をそろそろ策定する時期にあるのかもしれません。
国内では少子高齢化により、若年層がだんだん減少していく段階に既に入っています。せっかくの人材がミスマッチなどにより活用されないのは、ポスドク自身だけではなく日本の不幸ともいえます。少子高齢化や地方創生など、いろいろな課題が山積していますが、そろそろ国家ビジョンにそったちゃんとした戦略が必要とされているともいえます。
文科省だけなど、それぞれの省庁だけの施策ではなく、総合的な解決策を考えるべき時期にあるともいえます。たとえばの例ですが、IT人材、特に博士課程の人材を奨学金などで支援するとかも考えるべきです(以前の本コラムでは、奨学金ではなく、投資といえると指摘しました)。このような方々に一定期間、地方で働いてもらうとか、何らかの支援を考えてもよいのではないでしょうか。
先ほど述べた経産省での研究開発費税額控除ですが、国内大学あての支出をさらに優遇するとかしてもらうことも考えられます。経産省も財務省も、大学への支援は文科省任せになっています。ポスドク問題の解決だけではなく、大学全体の底上げが、ほんとうの意味での少子高齢化対策やさらには地方創成の課題でも有効です。
たとえばの例ですが、農業分野では最近は特にデジタル化や高度技術の導入が求められています。オランダが農業大国になったのは、高度技術の導入とスケールアップ(栽培規模の大規模化など)に成功したからです。昨今は、宇宙からの赤外線センサーなどの衛星監視により、農業分野、特に畑作などの収穫予測や害虫対策も実施可能です(稲作でも利用できるのではないでしょうか)。
地方だからIT化がすすまないのではなく、大学IT人材の活用範囲もあるのではないでしょうか。単に地方でのリモートワークに、ITを利用しているような段階ではありません。ひとつの例ではありますが、地方創生にも是非、大学の人材を活かしてもらいたいと思います。国内における、少子高齢化対応や地方創生のみならず、東京一極集中の解消にも役立ちます。
ポスドク問題について、ポスドクの現状のみならず、大学の将来課題との関連からも解説しました。
最近(本年6月12日)、日本経済研究センターは向こう50年間の日本の長期経済予測を公表しました。日本がAIなどを活用して生産性の向上や人材の適正配置を進めれば、50年後、2075年でのGDPが世界4位を維持できるという試算です。
想定を超える少子化により、このままの状態では経済は縮小し50年後にはGDPは世界45位と大幅ダウンとなる予測となっています。もう遅いのではと当方も考えていましたが、スタートアップの育成や、海外資金を含む、対内直接投資等を増やすことにより改善をはかるべきという提言です。
特にIT情報技術や医療、再生可能エネルギーなどのハイテク産業の育成が遅れていることが指摘されています。学校教育でも変革が必須で、教育支出比率をふやすことにより、大学院への進学者数が増加すると予測されています。
もし大学院進学者が増えれば、このままではさらにポスドクの問題が増加することにもつながります。またポスドク問題だけなく、その背景にある大学自体の課題も解決しなければなりません。文科省だけではなく、根本的な国の施策、ほんとうの意味での国家戦略を検討すべき時期に来ていると考えます。

研究や論文執筆にはたくさんの英語論文を読む必要がありますが、英語の苦手な方にとっては大変な作業ですよね。
そんな時に役立つのが、PDFをそのまま翻訳してくれるサービス「Readable」です。
Readableは、PDFのレイアウトを崩さずに翻訳することができるので、図表や数式も見やすいまま理解することができます。
翻訳スピードも速く、約30秒でファイルの翻訳が完了。しかも、翻訳前と翻訳後のファイルを並べて表示できるので、英語の表現と日本語訳を比較しながら読み進められます。
「専門外の論文を読むのに便利」「文章の多い論文を読む際に重宝している」と、研究者や学生から高い評価を得ています。
Readableを使えば、英語論文読みのハードルが下がり、研究効率が格段にアップ。今なら1週間の無料トライアルを実施中です。 研究に役立つReadableを、ぜひ一度お試しください!
Readable公式ページから無料で試してみる
都内国立大学にて、研究・産学連携コーディネーターを9年間にわたり担当。
大学の知財関連の研究支援を担当し、特にバイオ関連技術(有機化学から微生物、植物、バイオ医薬品など広範囲に担当)について、国内外多数の特許出願を支援した。大学の先生や関連企業によりそった研究評価をモットーとして、研究計画の構成から始まり、研究論文や公募研究への展開などを担当した。また日本医療研究開発機構AMEDや科学技術振興機構JSTやNEDOなどの各種大型公募研究を獲得している。
名古屋大学大学院(食品工業化学専攻)終了後、大手食品メーカーにて31年間勤務した経験もあり、自身の専門範囲である発酵・培養技術において、国家資格の技術士(生物工学)資格を取得している。国産初の大規模バイオエタノール工場の基本設計などの経験もあり、バイオ分野の研究・技術開発を得意としている。
学位・資格
博士(生物科学):筑波大学にて1994年取得
技術士(生物工学部門);1996年取得