
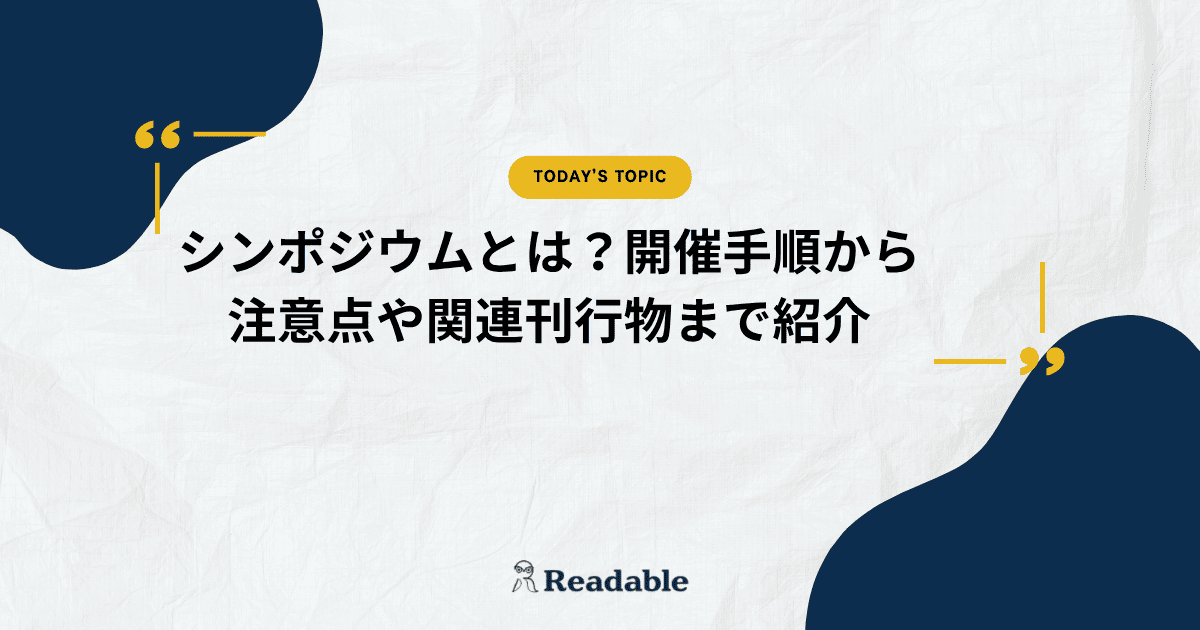
シンポジウムの開催は、当該分野の科学技術の発展と理解において、重要なシーンです。
大学でも企業でも、自身の研究領域に関するシンポジウムに出席して、最新の研究情報を入手しなければ、当該研究テーマの推進自体があやうくなります。
また各種展示会などと同様に、企業などの研究機関でも、積極的に専門のシンポジウムを自ら開催することもよくあります。
本記事では、シンポジウムを開催した実際例などを含め、開催手順からそのメリットや注意点まで広範囲に解説します。
目次
シンポジウムとは、古代ギリシア語から由来する言葉で、討論会やそれに関連する論文集などを示す用語です。
古代ギリシア時代において、夕食後などのお酒を飲んで交流する宴会を意味する、酒宴のこととされています。お酒を飲みかわしながら行うわけですから、酒宴での討論テーマに対して、自由にいろいろな観点から自分の考えを主張しあうものだったのではないでしょうか。
このように、シンポジウムのテーマに対して複数の論者が異なる視点から聴衆の前で発表や報告を行い、議論を重ね、質疑応答を行う開催形式となります。
視点が異なる複数の論者が参加することなど、シンポジウムの主な目的といえます。学会などでの通常の講演会では、演者が一方的にではないですが、講演を行い、後は簡単な質疑応答だけということもなくはないですが、これとは違うものがシンポジウムといえます。
シンポジウムと講演会の違いは、このようにひとつのテーマに対して、いろいろな側面から自由に討論してもらうことにあります。またさまざまな側面から討論をおこなうので、必然的にひとつのテーマに対する論者の数は、シンポジウムの方が多くなります。逆に、講演会では多数のテーマを扱うことで、最終的な講演者の数を増やしている側面もあります。
シンポジウムの開催手順について、下記に順番に解説していきます。
まずシンポジウムのテーマを設定する必要があります。このテーマがきっちりと設定されていないと、当該シンポジウムの方向性がさだまりません。
主催者が責任を持って実施できるシンポジウムのテーマにすることにより、海外からの参加者も増えるという効果が期待できます。テーマが決まったら、当該シンポジウムの背丈にあった講演者を内外から募集します。できれば募集というより、既に当該研究分野での自身が交流のある海外研究者などがよいと思います。
というのは、講演者もシンポジウムの背景を理解したうえで、講演して頂かないと、場合によっては著名人であってもテーマにそぐわない講演にならないとも限りません。講演者の招聘は、主催者が実施するもので、コンサルや別の団体などに依頼するなどの場合は、結果的に失敗することもあります。
主催者は、当該分野の研究を実施している企業の研究機関だったり、大学だったりします。大学の場合はあまり予算がありませんから、学会開催に付属するシンポジウムのこともあります。
また少なくとも半年以上前から、テーマなどの事前準備を開始してから、最終テーマも設定するようにします。学会などで、関連分野の研究者があつまる場合は、あらかじめ学会の日時や概要が決まっているので、それを積極的に利用することも可能です。
テーマが決まったら、それに合わせて当該シンポジウムの概要や形式も設定します。
テーマの内容や方針にそって、オープン形式かクローズド形式での開催を選びます。たいがいの場合は、オープン形式でよいですが、特殊なテーマなどクローズド形式の方がよい場合もあります。特に研究者同志のディスカッションをメインとしている場合は、利点があります。
なぜなら、当該研究課題の加速の側面もあるからです。公的機関が開催する場合はオープン形式が多いかと思いますが、学会などで付属したシンポジウムでは、学会参加の段階ですでにクローズド形式に類似したものとなっています。なお最近は、市民参加を主体としたオープン形式のシンポジウムも増えています。
同時並行的に、シンポジウムの場所と開催期間を設定することも大切です。
というのは、大都市ではシンポジウム会場を確保するのは、だんだん難しくなっているからです。当方も、次の「シンポジウムの開催例」に記載した、クローズド形式のシンポジウムの事務局長を担当したことがあります。海外参加者が多いので、都内で開催したのですが、テーマ設定と同時にあるホテルを予約することが出来ました。
上記シンポジウムは百名以内でしたが、数百名規模のものもかなりあります。このような場所は、数年前から設定されている場合が多く、十分時間を持って開催場所を設定することが大切です。なおシンポジウムも開催されるような定期的な学会開催では、3年以上前から、次の開催都市と開催場所が設定されていることが多くなっています。
シンポジウムのプログラムと講演者は、おのずとシンポジウムのテーマと概要から決定できます。
たとえば、バイオ分野でも化学系、生理学系、心理学などの各種分野の研究者がそろって、当該テーマについて、それぞれの立場から講演を行い、さらに各分野の研究者とディスカッションをおこなうことが目的の場合もあります。このような場合は、それぞれの分野の研究者を講演者として招く必要があります。たいていの場合は、シンポジウムテーマを設定する領域において、すでに学会などで交流のある研究者などですので、連絡先も把握済みが多いようです。
最近は、企業の決算説明会もオンラインによるライブ配信などがある場合があります。シンポジウムでも、オープン形式で開催する場合は、同様な形式も取ってよいでしょう。
実際にコロナ渦では、会場には聴衆はいませんが、学会などでもライブ配信実施例も多数ありました。また、決算説明会と同様ですが、会場開催とライブ開催での、いわゆるハイブリッド形式の場合もあります。
このような場合は、両方の形式による会場機材とライブ配信機材の両方をそろえる必要があります。かなりハードルが高い方法ともいえ、シンポジウムの目的を考えて実施すべきです。ただ海外からの講演者や聴衆に、時間的余裕(来日に伴う時間など)がない場合は、有効な方法となりえます。
会場開催のみの場合でも、機材の管理と習熟があらかじめ必要です。また会場にあらかじめ機材がない場合は、主宰者が持ち込むなどの事前準備が大切です。なおシンポジウム会場、たとえばホテルとか学会開催に対応できる施設などで、既に関連機材や資材をそろえているときもあります。できれば、そのような施設を利用することをおすすめします。というのは当該機材の操作などで、施設の関係者の支援が期待できる場合もありメリットが大きくなります。
忘れてはならないのが、講演者と聴衆や関連団体への封書などでの開催連絡です。
最近はメールのみの場合も多いと思いますが、講演者に加えて、聴衆にも必要十分な開催情報をあらかじめ連絡します。最初に余裕を持ってまず連絡して、直前にも確認をするなど、画竜点睛を欠かさないようにしましょう。
シンポジウムの開催手順についてみてきましたが、それでは実際のシンポジウム開催はどのようにすればよいでしょうか。ここでは当方が関連した企業の研究開発部門での開催例について、紹介します。
やや古くなりますが、食品系企業の研究部門において、味覚に関するシンポジウムを開催したことがあります。食品企業では、現在もそうですが、いろいろな商品開発を日夜実施しています。ただ技術オリエンテッドのみで、新商品を開発するわけにはいきません。
というのは、実際に食品を最終的に食べるのは一般の消費者の方だからです。このため現在もそうですが、人が実際に接種する場合の反応を心理学的な方法などで解析して、これを商品開発に活かすことが求められます。
特に、コーヒーやビールなどの商品の場合、商品に含有されるカフェインなどの一定の苦味を測定し解析する必要があります。その当時、甘味や酸味などの味覚については、研究がすすんでいたのですが、苦味についてはごく一部の研究者しか検討がなされていませんでした。
これは国内だけでなく、その当時、欧米でもほとんど同じ状況でした。なお最近は欧米以外のアジアなどでも味覚研究は実施されていますが、その当時は欧米と日本のみで研究実施されているという状況でした。
このような場合、世界の研究者を一同に集めて、苦味に関するシンポジウムを開催するのは非常に理にかなったことになります。
最先端の研究者にシンポジウムで自身の研究成果を講演してもらい、複数の研究者の間でディスカッションしてもらうことにより、当該分野の研究の加速とアップデートが可能となります。「シンポジウム」としての趣旨にも合致しており、このため当該シンポジウムが、主に研究者間の交流を目的としてクローズド形式で開催されました。
開催されたシンポジウムのタイトル:
International Symposium on Bitter Taste
当該シンポジウムは、以下の7つのセッションから成っています。
・Structure-Activity Relationships for Bitterness
・Perireceptor Events and Taste Bud Density
・Receptor Mechanism for Bitter Taste
・Bitterness Information carried by Peripheral Gustatory Neurons
・Brainstem Responses to Bitter Taste Stimuli
・Bitter Taste as a Signal of Toxic or Therapeutic Substances
・Expression of Human Responses to Potential Bitter Stimuli
簡単にいいますと、苦味物質の化学的構造とは何かという課題からはじまり、味覚細胞(甘味の苦味は感知する細胞と神経が異なります)での受容性の問題や、マウスなどの神経系を用いた神経生理学研究や、ヒトにおける苦味の感受性研究、さらにはヒトの個体毎での苦味物質接種量との関係など、実験心理学的研究なども含む、総合的なシンポジウムです。
7つのセッションに対して、合計20の演題があり、ディスカッションでは、化学者、細胞生物学者、神経生理学者、心理学者などが欧米などからあつまって開催されています。特に米国では、ヒトの感受性を研究する心理学者(実験心理学)が従来から一定の勢力を得ており、当該シンポジウムでも半分以上の演者や聴講者を占めています。
現代におけるシンポジウムは、一つのテーマに対して、数人以上の講演者が異なる視点からの報告や意見を発表した後、聴衆からの質問に答える形式で行われるイベントを意味しているケースが一般的です。
1つの議題に対して、さまざまな切り口からの研究報告や意見を聞くことができるのがシンポジウムの特徴であり、研究主体のシンポジウムでのメリットともいえます。
また企業によるシンポジウム開催では、自社のブランド関連でのいわゆる企業ブランディングにも効果がある場合があります。もちろん、自社商品に関連するシンポジウムの場合は、直接的な効果が見込めますが、研究目的のシンポジウムでも一定の効果があります。
たとえば健康食品の開発などの分野では、国内でも企業や大学研究者などが参加するシンポジウムが開催されています。最近は特に大手を中心として、ブランドイメージを大事にする傾向がありますが、有益なシンポジウムであれば、それにも資することができます。
当方もシンポジウム開催例で述べた、企業主催のシンポジウムを実施したことがあります。この場合、都内のあるホテルを開催場所として設定しました。
ホテル付きの会場であれば、シンポジウム後にそのまま宿泊をすることができるだけではなく、ホテル内のレストランなどで懇親会や食事を行うことも可能です。特にシンポジウムが2日間など日数がある場合は有効となります。全員が同じホテルに宿泊しなくとも、シンポジウムの目的である当該分野の交流をさらに促進することができます。
直接的なメリットではないですが、後日講演者や聴衆から非常に好評で、ある著名な海外学術雑誌から、当該シンポジウムを、まるごと「出版刊行物」として発行したいという申し出がありました。結果的に当該学術雑誌から、その当時の最新研究成果を集めた国際レビューとして、ペーパーバック版ですが発刊されています。
(Special Issue: Intenational Symposium on Bitter Taste)
出版物の刊行では、たいがいの場合かなりのコストがかかりますが、無償で公式刊行物として出版されています。もちろん当該出版物を購入する場合は、購入者には料金がかかります。なお当然、講演者は無料配布で、自社には、確か数十部以上の印刷物を無償で頂いております。
企業や官公庁などが主催する場合、最後に刊行物が発行される場合もあり、かなりのコストとなっていることがあります。できれば、学術雑誌側から申し出があるようなレベルのシンポジウムとするのが望ましいでしょう。
シンポジウム開催には、注意すべき点もあります。
開催前の準備には十分時間をかけて、いろいろな角度から検討しておくことが大切です。
シンポジウム開催のテーマ、すなわちタイトルは、シンポジウムの特徴と性格などにも影響します。
最近はないと思いますが、以前はまず海外から著名な講演者をよべばよい、というようなシンポジウム開催もありました。著名な講演者も、いろいろな国で講演していることも多く、当該シンポジウムに「熱意」を持って参加してくれるとは限りません。講演料なども出るので、当然来日してくれますが、そのシンポジウムが成功(と呼べる状態で、単に開催すればよいというものではありません)するかどうかとは、別の問題となります。
テーマ、すなわちシンポジウムのタイトルということになりますが、開催者が責任を持って設定することが大切です。もちろんテーマ設定にあたって、当該研究分野の海外著名研究者の意見を聞くのは有用ですが、最後は主宰者が決めるべきです。
従来、地方などでのシンポジウム開催に対して、開催することだけが決まっており、テーマは呼べる著名人次第などという例がないわけではありません。シンポジウムの概要は、主催者がみずから決めるべきで、官公庁などでもある、コンサル提案が主体のシンポジウム開催では失敗する場合があります。
シンポジウムは会場によっても雰囲気を変えてしまうため、会場選びは慎重に行う必要があるでしょう。また会場によっては、数年前からの事前予約をすすめているところなどもあり、早めに開催期間を設定しなければなりません。
ライブ配信では、撮影機材や録音機材などが必要で、さらにはそれを操作する人員も必要です。外部から応援がある場合は別ですが、開催団体や自社などで習熟しておかなければなりません。またライブ配信の欠点は、当日なんらかの不具合が生じることがあります。不具合には、最近多いネット環境の不安定性からくるものと、撮影機材などの当日の不具合などがあり、それぞれ、もしあった場合の手順も決めておくのがよいでしょう。
当方がいた企業の開催例では、都内で開催したのですが、テーマ設定と同時にあるホテルを予約することが出来ました。当該のホテルでは、以前からシンポジウムの類の開催経験が複数あり、開催場所としてある程度の広さと、開催のための機材もそろっていることが魅力でした。シンポジウムの概要や規模に合わせた会議室が確保できるかがカギとなります。
遠方からの参加者が多いシンポジウムでは、開催会場だけではなく、ホテルの手配も必要となってきます。たとえばホテルが持つ会場も、シンポジウム開催に利用可能です。当方も以前、都内でのシンポジウム会場としてホテルを利用しましたが、付属機材などの準備もあり、結果的にも支障なく開催することができました。
シンポジウムを開催した実際例などを含め、開催手順からそのメリットや注意点まで広範囲に解説しました。
シンポジウムの開催は、当該分野の科学技術の発展と理解において、特別なエポックとなることもあります。
本記事がこれからシンポジウム開催を計画している方々のお役に立てば幸いです。

研究や論文執筆にはたくさんの英語論文を読む必要がありますが、英語の苦手な方にとっては大変な作業ですよね。
そんな時に役立つのが、PDFをそのまま翻訳してくれるサービス「Readable」です。
Readableは、PDFのレイアウトを崩さずに翻訳することができるので、図表や数式も見やすいまま理解することができます。
翻訳スピードも速く、約30秒でファイルの翻訳が完了。しかも、翻訳前と翻訳後のファイルを並べて表示できるので、英語の表現と日本語訳を比較しながら読み進められます。
「専門外の論文を読むのに便利」「文章の多い論文を読む際に重宝している」と、研究者や学生から高い評価を得ています。
Readableを使えば、英語論文読みのハードルが下がり、研究効率が格段にアップ。今なら1週間の無料トライアルを実施中です。 研究に役立つReadableを、ぜひ一度お試しください!
Readable公式ページから無料で試してみる
都内国立大学にて、研究・産学連携コーディネーターを9年間にわたり担当。
大学の知財関連の研究支援を担当し、特にバイオ関連技術(有機化学から微生物、植物、バイオ医薬品など広範囲に担当)について、国内外多数の特許出願を支援した。大学の先生や関連企業によりそった研究評価をモットーとして、研究計画の構成から始まり、研究論文や公募研究への展開などを担当した。また日本医療研究開発機構AMEDや科学技術振興機構JSTやNEDOなどの各種大型公募研究を獲得している。
名古屋大学大学院(食品工業化学専攻)終了後、大手食品メーカーにて31年間勤務した経験もあり、自身の専門範囲である発酵・培養技術において、国家資格の技術士(生物工学)資格を取得している。国産初の大規模バイオエタノール工場の基本設計などの経験もあり、バイオ分野の研究・技術開発を得意としている。
学位・資格
博士(生物科学):筑波大学にて1994年取得
技術士(生物工学部門);1996年取得