
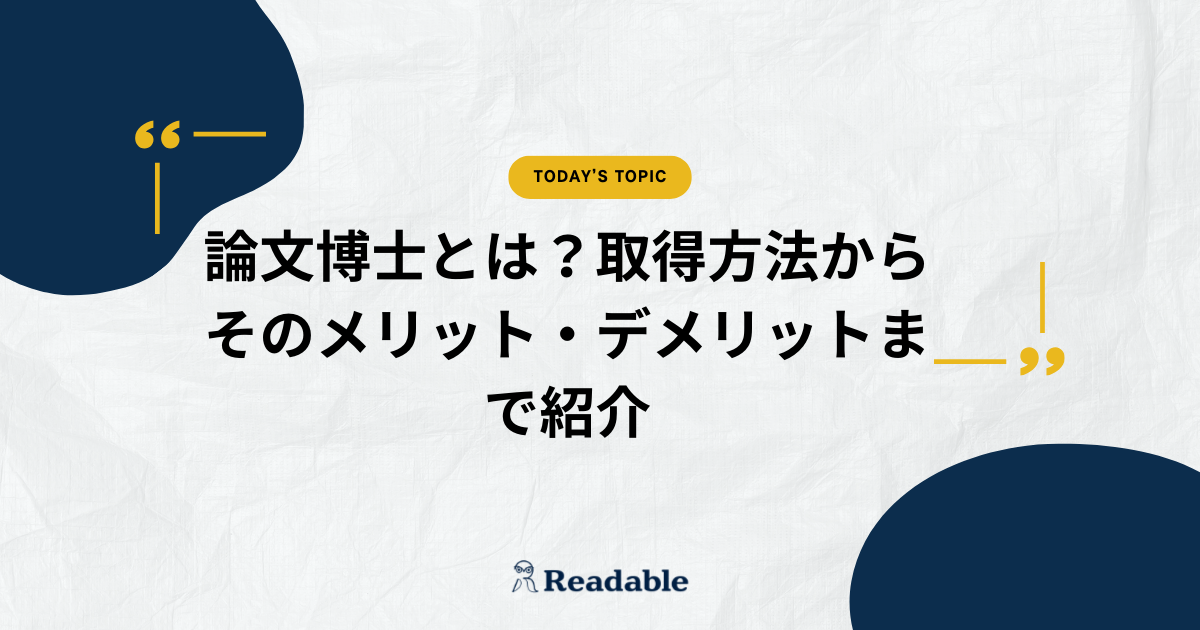
博士号は昔から研究者として評価されるための、最初の一歩となっています。
博士号には、実は「課程博士」と「論文博士」があります。正規の博士課程を終了していなくても、大学院に博士論文を提出することにより取れる資格が、論文博士なのです。
本記事では、論文博士の定義からその取得方法や、メリット・デメリットまで詳細に解説します。
博士号には、博士課程により博士号を取得する「課程博士」と、博士課程終了後や、あるいは同課程を終了していなくとも、企業などに就職後に取得する「論文博士」という資格があります。
論文博士をとるには、まず大学院のある大学に申請する必要があります。また大学院であれば、どこでも良い訳ではなく、自身の研究テーマに沿った研究課程を有する大学院でなくてはなりません。また研究テーマが類似していても、大学院の先生との関係性がそもそもなければなりません。というのは、大学院の先生方にとって、課程博士ではなく論文博士は、あくまで博士号として、本来の大学院教育とは異なるものだからです。いわゆる手弁当で当該の論文博士の審査をしてもらう、というのが従来のスタンスだからです。
申請条件としては、学校教育法で定められており、「博士論文の審査に合格し、かつ、その大学院の博士課程の修了者と同等以上の学力がある」ことが最低条件となります。
学校教育法による「学位規則」として、下記のように規定されています。
(博士の学位授与の要件)
第四条 法第百四条第三項の規定による博士の学位の授与は、大学院を置く大学が、当該大学院の博士課程を修了した者に対し行うものとする。
2 法第百四条第四項の規定による博士の学位の授与は、前項の大学が、当該大学の定めるところにより、大学院の行う博士論文の審査に合格し、かつ、大学院の博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認された者に対し行うことができる。
通常の博士課程を修了した者には、博士の学位授与を「行うものとする」なのに対して、それ以外の者では、学位授与を「行うことができる」なのであり、あくまで、正規の学位授与に、付随した事項ということになります。
なお実際の規則は、各大学によって細かな条件が異なり、より詳細な条件が課されている大学もあるため、事前に確認・相談をする必要があります。少なくとも、査読付き論文発表の質と数については、博士課程学生よりも高いレベルが求められる傾向があります。
当方も以前、論文博士号をある国立大学大学院より頂いていますが、その際の条件として、自身がファーストオーサーである、査読付き学術論文が3報以上あることが最低限となっていました。
課程博士では、大学院の博士課程に在籍し、授業や研究活動に参加し、卒業論文を提出して博士号を取得します。
博士課程に入学し、定められた期間で所定のカリキュラムを履修しながら研究を進め、在学中に、博士論文の審査承認を得ることで学位を取得します。
所定の単位を取得したうえで、博士論文の審査に合格した場合に授与されるのが、課程博士なのです。課程博士は、4年制学部を卒業したのか、6年制学部を卒業したのかによって一部異なりますが、博士号としては同様に授与されます。
課程博士については以下の記事で詳しくご紹介しています。
課程博士とは?博士号の取得方法からそのメリットや注意点まで紹介
論文博士とは、大学院の博士課程には在籍せずに、提出した博士論文の審査に合格することで、博士号を授与される制度です。課程博士とは異なり、博士論文の審査会で評価されることで博士号を得る、日本特有の制度です。
論文博士制度は、大学院に在籍することが難しい場合や、すでに一定の研究実績を持つ人が、博士号を取得するための制度として設けられています。論文博士を取得するためには、大学院の博士課程を修了した者と同等以上の学力がある、と認められることが必要です。
論文博士号の取得には、以下のようなプロセスを経ることとなります。
博士号の審査では、いわゆる原著論文の質と同様な内容が少なくとも求められます。新規性且つ、有用性の高い研究テーマを持つ論文でなくてはなりません。このため、自身の研究テーマに関して、当該分野を持つ大学院での審査ということになります。
当該大学院での研究分野と異なるテーマでも問題ないところがない訳ではありませんが、あくまで論文博士は課程博士に付随しているものになります。このため、まず関連研究のある大学院を選ぶ必要があります。
どの大学院で論文博士を取得できるのか、その条件を確認します。出身大学では、論文博士制度を扱っていない場合もあります。大学院によって申請の流れや必要条件は異なるため、問い合わせてみることが大切です。
大学院の選定と同じくらい、指導教員の先生の選択が重要です。できれば学会やその他の交流などで、事前に知っている先生ですと大変助かります。なぜなら教官の先生方はいつも非常に忙しく、特に日本の大学では雑用の方が多いといわれており、論文博士などに時間をさく余裕は少なくなっています。海外で取得するのはどうかと思われるかもしれませんが、実は論文博士は、制度的には日本独特のものなのです。
このように申請する大学院で指導教員を探しますが、当方の例のようにいろいろであり、自身の努力だけではどうにもならないこともあります。
指導教員は、当然、論文審査の主査となります。当方が論文博士を取得したときは、主査は当該のお願いした先生で、同じ生物領域の助教授と同大学院の心理学領域の教授の先生に副査になっていただきました。
出身大学を選ぶ場合、以前の指導教員に依頼することが一般的ですが、別の大学院にお願いする場合もあります。このような場合は、自身にとって必然的にあらたな先生を選ぶことになります。この段階では、教員側はまったくのボランティアとして論文審査を引き受ける形になるため、この辺を留意することが大切です。
このようにまず大学院と指導教官の選択が一番大切ですが、それらが決まったら当該の大学院での論文博士の申請条件を調べます。出身大学とは別の大学院にお願いする場合は、指導教官に聞くのもよいでしょう。というのは申請条件が規則で設定されている以外にも、慣例などいろいろな条件のようなものがある場合もあります。
指導教員が決まったら、必要な書類を準備して大学に提出します。予備審査を受けるために当該の「博士論文(まだ未承認段階ですが)」を作成するとともに、「履歴書」「学位申請書」「業績目録」などの書類を揃えましょう。なお必要書類は大学によって異なることが多いので、注意が必要です。
博士論文の本格審査の前に、当該の論文をまず仕上げる必要があります。卒業論文や修士論文などと違い、論文博士にふさわしい内容があることが大切です。通常は指導教官の先生と事前に十分構成をまず練ってから、肝心の論文作成をはじめます。
どのような研究内容を盛り込めばよいかは、論文博士号の成否に大きく影響します。研究内容の量が多ければよいというものではなく、それぞれが関連して当該の研究テーマを構成しています。なんでも盛り込めばよいのではなく、ときには取捨選択も必要です。博士論文の構成に基づき、たいがいの場合、主査や副査を含む審査員に対して、口頭発表することになります。いわゆる実験データなどの研究成果が多いから良いということではなく、それなりの研究構成と妥当性が必要です。妥当性と書きましたが、妥当性の前に、当然「新規性」は必須です。新規性のない研究成果は、博士論文審査以前の問題です。
提出された「博士論文(まだ未承認段階ですが)」を基に審査が行われます。主査などによる書類審査に続いて、審査員の前で口頭発表します。提出した論文について細かく質疑応答がなされ、自身の研究が精査されます。大学によっては、課程博士と同様、予備審査と本審査が二段階で用意されているケースもあります。
大学院での審査に合格したら、まず「(合格後の)博士論文」を製本することになります。現在でもあると思いますが、たとえば東大近くの本郷には、博士論文などを製本してくれる業者が複数あります。指導教官の先生にも聞くとよいでしょう。
製本の本数は、大学院によって前後しますが、少なくとも10冊程度は製本しておくことが大切です。専用の用紙にコピーした論文を複数持ち込む場合や、電子データから製本業者ですべて製本まで対応してくれるところもあります。
博士論文は、主査や副査の先生に提出する以外に、当該大学院で保管されて閲覧されます。またさらには、「国会図書館」において正式な蔵書となる権利があることです。このため自身の博士論文でも、国会図書館に保存されています。
なお別途、学位授与に伴う申請書類をそろえます。書類と共に、大学ごとに規定されている論文審査手数料が必要になります。またその後、博士号授与式がある大学も多いようです。当方の例では、ノーベル賞を受賞された当時の学長から、課程博士の学生と一緒に論文博士合格者にも、大学講堂にて当該の学位記が直接授与されました。このように、論文博士でも課程博士と同様に「博士号」の授与者となる栄誉があります。
博士論文の申請が条件となっている論文博士ですが、実際の博士論文はどのように記載されるべきでしょうか。
一例として、当方がある大学院に申請し、結果的に博士号を授与された当該論文を紹介します。
国内では、かなり先進的な先生もおられる大学院もあり、当該の大学院の既存研究分野だけが対象ではありません。特に学際的な研究領域は、従来の研究領域にさらに新たに視点がプラスされるという効果が、大学にとっても期待できます。学際的な研究テーマを持つ場合は、むしろ課程博士より論文博士での研究の方がむいているかもしれません。
当方もある大学の生物系大学院で博士号を取得したことがあります。自身の研究テーマは、動物実験などによる生理学的研究とヒトを用いる実験心理学的研究の融合が目標となっていました。この大学では、生物学領域と心理学領域の研究ポジションが近くなっており、教官の先生の間の交流があったことに救われました。
当時の博士論文を例にとって説明しますと、下記のようになります。
その大学院では、要約部分だけではなく、論文全文が「英語」指定でしたので、論文作成の最終段階でもかなりの時間がかかりました。また論文の構成においても、ヒトを扱う実験心理学の手法により味覚感受性に関する実験データを得る項目と、動物実験(マウス・ラット)で味覚神経データを得る項目からなっています(下記黄色部分が、英語論文の構成となります)。
1.INTRODUCTIN
2. METHODS AND MATERIALS
2.1. Bitter taste sensitivity determined by human sensory assessment
2.2. Bitter taste sensitivity determined by nuero-physiological measurement
2.3. Analysis of salivary levels of caffeine and iso-alpha acids
3. RESULTS
3.1. Relationship between ingestion of and bitter taste responsiveness to caffeine
3.1.1. Caffeine taste thresholds in caffeine users and non-users
3.1.2. Relationship between caffeine ingestion and caffeine threshold
3.2. Effect of acute and chronic dosing on caffeine to bitter taste sensitivity
3.2.1. Detection of salivary caffeine in users and non-users of caffeinated products under free-living conditions
3.2.2. Effect of acute caffeine ingestion on taste sensitivity
3.2.3. Effect of chronic caffeine ingestion on taste sensitivity
3.3. Effect of consumption of bitter substances to bitter taste sensitivity and individual differences of taste sensitivity
3.4. Neuro-physiological analysis of bitter taste sensitivity in mice
4. DISCUSSION
5. SUMMARY
6. ACKNOWLEDGEMENTS
7. REFFERENCES
8. FIGURES AND TABLES
論文構成としては、実験手法の部分と実験結果の部分にまず大きく分かれます。研究分野としては、実験心理学の分野と、動物を用いた神経生理学の分野にわかれています。具体的には、上記論文構成での2.1と3.1や3.2、3.3は、ヒトを用いる実験心理学研究となっており、2.2と3.4は神経生理学における実験とその結果を記載する部分にあたります。
当方がお願いした大学院では、味覚や嗅覚の神経生理学が専門の研究を実施されていましたが、当時はマウス・ラットの生理学実験系を持っていませんでした。そのため国内の別の経験豊富な大学に、マウス・ラットの神経生理学実験をまず習いにいくことからはじめました。
なお博士論文以外に、研究テーマに関連するファーストオーサーの原著論文が3報以上という同大学院の審査基準でした。このため実験心理学の分野で1報、神経生理学の分野で1報、さらに苦味物質の分析手法を検討した分野で1報を作成しています。またセカンドオーサーでも2報を含め、合計5報以上を用意しました(下記に、博士論文構成との関連性を記載します)。
ファーストオーサーの論文3報:
・実験心理学の論文:実験系2.1にて、実験結果3.1、3.2、3.3
・神経生理学の論文:実験系2.2にて、実験結果3.4
・物質分析系の論文:実験系2.3にて、実験結果3.1、3.2、3.3
文科省では、論文博士制度の在り方について、下記のような総括的な課題があることを認めています。
引用先:https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/gijiroku/attach/1412776.htm
現在の学校教育法において、大学は、博士の学位を授与された者と同等以上の学力があると認める者に対し、博士の学位を授与することができるとされている。これにより、博士の学位を授与された者をいわゆる「論文博士」と呼んでいるが、専攻分野によっては、この制度について見直すべきとの指摘がある。
博士学位授与数に占める論文博士の割合は減少傾向にあるものの、他方で、企業、公的研究機関の研究所等で経験を積み、その研究成果をもとに、博士の学位を取得したいと希望する者も未だ多いことも事実である。
学位の制度的趣旨を踏まえると、「論文博士」の見直しを行うにあたっては、大学院博士課程の教育機能の一層の向上が前提であると考えられる。このため、今後、大学院教育の実質化の検討を深化させていく中で、併せて議論していく必要がある。
このような総括的な課題以外にも、実際に取得申請する立場になると、いろいろなことが起こるのがふつうです。このため気長に構えるといったスタンスも大切です。
当方の場合は、修士課程を修了した大学と、その後論文博士を授与された大学は異なっており、申請条件なども違っていた経験があります。むしろなかなかうまくは行かないとして、論文博士の取得には時間をかける方がよいでしょう。1年後にすぐ申請などとは思わず、時間をかけて十分に準備して、博士号審査に望むことが求められます。
修士課程を修了した学生にとって、出身大学の教官や修士課程時代の研究テーマは非常に魅力的です。ただ自身の研究テーマが、いつまでも未完成のままになっているとは限りません。たいがいの場合は、教官はさらにその研究を発展させて研究を進展させており、修士課程修了者の味方ではない場合もあります。
実は、当方も発酵食品の研究を修了して、卒業後就職した食品企業の研究所でも関連研究を実施していました。このため卒業5年後ぐらいだったかと思いますが、教官に博士論文を作成すれば、博士号をもらうことができるか聞いたことがあります。
その後大学に海外からの留学生があり、当方の研究テーマを発展させて博士号(課程博士)をとったとのことで、当時の指導教官から断られてしまいました。同様な研究を発展させても、博士号で必要な「新規性が確保できない」からとのことでした。
その留学生の方は、当方より年齢も高く、出身国に帰って大学助教授になった(その後、教授)とのことでした。30年以上前のことですが、現在は、海外留学生がどの国立大学にも多数であり、このような事態は今後もあるかもしれません。
結果的に、当方は別の研究テーマで別の大学となりましたが、論文博士号を頂くことができ幸運であったと考えているところです。
大学院に在籍している場合、博士課程修了には、少なくとも5年の時間がかかります。
最近は特急で取得する制度も一部の博士課程ではあるようですが、論文博士の場合、大学院に在籍しないので授業料等は掛からず、5年間という時間は必要ありません。ただ博士論文の審査に関して、審査料などの費用は必要です。ただしデメリットのところでも述べますが、大学院に在籍していないからといっても、研究生などで受け入れてもらうこともあり、それなりの時間と費用はかかります。
またたいがいの場合は、企業や公的研究機関から論文博士号を目指すことになるので、勤務先の理解や休暇制度などがうまく合致していることも大切です。最近は企業でも副業なども認められているので、論文博士取得にも理解があるのではないでしょうか。
大学の学部と異なり、地方大学でも大学院では学際的な研究や、異分野を融合した研究が推進されている場合があります。さらに既存の学科でも、学際研究を推進していることがあり、特にあらたな研究視点のあるテーマだと有利です。
課程博士でも学際研究に特に力を要れている場合もありますが、企業などで大学では実施していないような視点の研究を行っており、その研究テーマを自身が担当しているときは、トライしてみる価値はあります。
当方の論文博士の研究テーマは、心理学と生理学の融合分野であったため、新しい視点として審査会にて審査していただくことができました。当該大学では、融合分野に感心があったようですが、実際に研究テーマに落とし込んで研究された課題はその当時は少なかったようです。
これは当然ともいえるもので、論文博士号は大学院の本来の教育とは別個のものです。このため論文博士の場合、指定される論文数もかなりの数となります。
少なくとも2~3報となっている大学院もあるようですが、当方がお願いした大学院では、「ファーストオーサー且つ、査読付き論文」にて計3報以上で、セカンドオーサーを含めて合計5報以上となっていました。ファーストオーサーの論文が3報に達しない場合は、論文博士の申請条件に合致しないことになります。また全て英語論文での投稿が求められており、日本語論文は、ファーストオーサーであってもカウントされませんでした。
ファーストオーサーである査読付き論文については、博士論文の「作成前」に、それぞれの学術誌の査読委員会で投稿・受理されなければなりません。これらが受理されていないと、肝心の博士論文が完成しても、論文博士の審査委員会では審査自体が実施されないことになります。
なお博士論文自体も、同大学院では英文での作成となっていました。現在も同大学院の博士後期課程の評価基準には、「問題設定から結論にいたる論旨が、英文で実証的かつ論理的に展開されているか。」となっているので、英文を重視していることが伺えます。
研究指導を受けるための指導教官をまずみつけることが大切ですが、いろいろな条件があり、簡単に決まるものではありません。
もし博士前期課程(修士課程のこと)を修了して、企業の研究所などに就職した場合、当該の研究分野に配属されることがあります。このような場合は企業の研究であらたな視点が加わることになり、論文博士の取得は容易になります。さらには、ふつう論文博士の指導教官も修士課程と同じですから、かなりラッキーな研究テーマともいえます。
ただし先ほど記載したように、大学院でも自身の卒業後にあらたな研究生や留学生を受け入れているので、そのテーマがいつまでも保持されるのは難しくなっています。当該研究テーマをさらに発展させるのが、大学院の使命でもあり、修士の研究テーマがそのまま残っているのは、かなり珍しいともいえます。またそもそも博士課程に在籍していなかった人が、論文博士を目指す場合もあります。
このように当該の大学院ではなく、別の大学院を探すことになる可能性もかなりあるのです。また別の大学で指導教官をみつけたとしても、自身の本来の研究テーマと当該の指導教官の希望テーマがかならずしも合致しないことも考えられます。たとえ企業の研究所に所属していたとしても、休暇などを活用して当該の大学院に出入りしたり、さらには実際の研究を手伝うなど、指導教官との距離を縮める工夫も必要です。
当方も企業の研究室などに所属していましたが、幸い40歳に到達すると2週間の長期休暇がもらえる制度があったので、その制度を最大限使用し大学院で動物実験を実施しました。文科系やコンピューターサイエンスなどでは、そこまで実験系は重視されませんが、理工学分野では、たいてい大学院での実地の研究が必要になり、それなりの時間がかかるといえます。
論文博士をとるには、大学院のある大学に、申請する必要があります。
大学院であれば、どこでも良い訳ではなく、自身の研究テーマに沿った研究課程を有する大学院でなくてはなりません。また大学院の先生方にとって、課程博士ではなく論文博士は、あくまで教育上は別途の資格にあたるものです。従来は、いわゆる手弁当で当該の論文博士の審査をしてもらう、というのがスタンスとなっている場合もありました。
またファーストオーサー且つ査読付き論文が、博士論文作成の前に複数必要です。これらは、それぞれの学術雑誌の査読委員会で投稿・受理されなければなりません。このため、博士論文の執筆前には十分に時間をとって望まれることをおすすめします。
本記事が、これから論文博士の取得を目指しているみなさまのお役に立てば幸いです。

研究や論文執筆にはたくさんの英語論文を読む必要がありますが、英語の苦手な方にとっては大変な作業ですよね。
そんな時に役立つのが、PDFをそのまま翻訳してくれるサービス「Readable」です。
Readableは、PDFのレイアウトを崩さずに翻訳することができるので、図表や数式も見やすいまま理解することができます。
翻訳スピードも速く、約30秒でファイルの翻訳が完了。しかも、翻訳前と翻訳後のファイルを並べて表示できるので、英語の表現と日本語訳を比較しながら読み進められます。
「専門外の論文を読むのに便利」「文章の多い論文を読む際に重宝している」と、研究者や学生から高い評価を得ています。
Readableを使えば、英語論文読みのハードルが下がり、研究効率が格段にアップ。今なら1週間の無料トライアルを実施中です。 研究に役立つReadableを、ぜひ一度お試しください!
Readable公式ページから無料で試してみる
都内国立大学にて、研究・産学連携コーディネーターを9年間にわたり担当。
大学の知財関連の研究支援を担当し、特にバイオ関連技術(有機化学から微生物、植物、バイオ医薬品など広範囲に担当)について、国内外多数の特許出願を支援した。大学の先生や関連企業によりそった研究評価をモットーとして、研究計画の構成から始まり、研究論文や公募研究への展開などを担当した。また日本医療研究開発機構AMEDや科学技術振興機構JSTやNEDOなどの各種大型公募研究を獲得している。
名古屋大学大学院(食品工業化学専攻)終了後、大手食品メーカーにて31年間勤務した経験もあり、自身の専門範囲である発酵・培養技術において、国家資格の技術士(生物工学)資格を取得している。国産初の大規模バイオエタノール工場の基本設計などの経験もあり、バイオ分野の研究・技術開発を得意としている。
学位・資格
博士(生物科学):筑波大学にて1994年取得
技術士(生物工学部門);1996年取得