
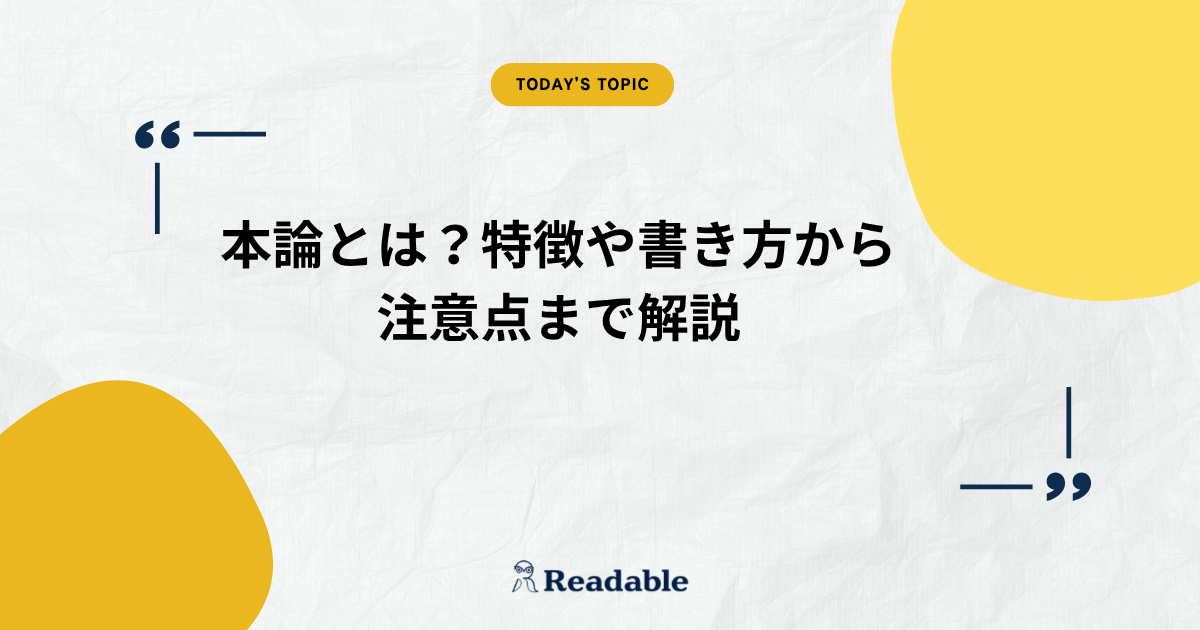
本論とは、レポートや論文などを作成する場合に、その核となる部分です。
本論は、最初の序論や、本論のあとに作成される結論とともに構成されています。また序論の部分で紹介した他の参照論文との整合性や、自身の研究目的がどのように達成できたのか、具体的に説明することも必要です。
本記事では本論について、その特徴や書き方から注意点まで解説します。
目次
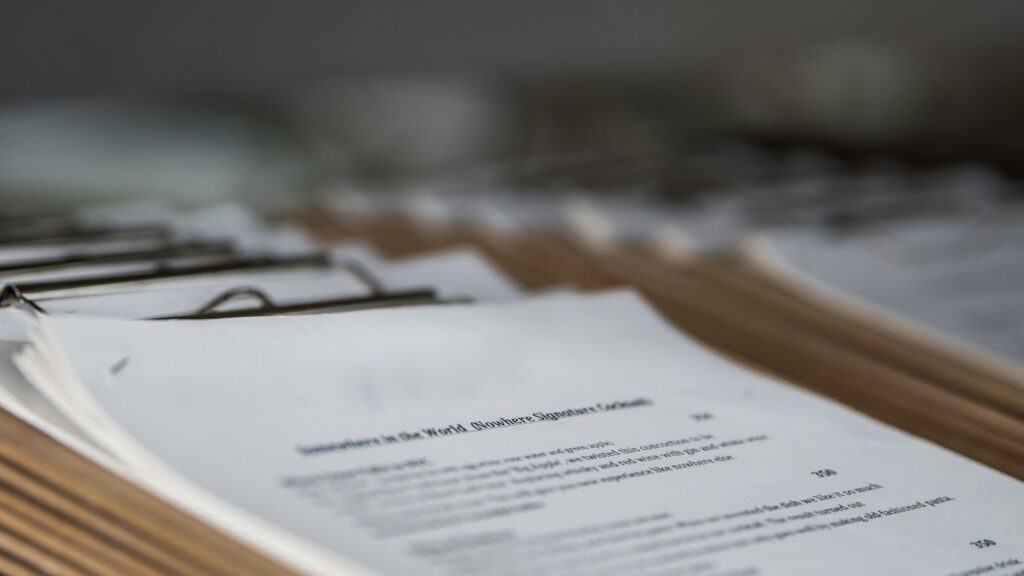
本論とは、レポートや論文などを作成する場合にその核となる部分であり、一番重要な部分ともいえます。
本論では、単に主張することではなく、なぜそういう主張になるのか証明することが求められます。研究論文の場合、本論は研究の内容について述べる核心のところです。研究背景などで判明した、従来の研究からみえてきた問題や、自身が提起するあたらしい主題について、どう問題を検討し結果をえたのか具体的に詳しく書いていきます。
本論は、論文などでは、研究結果の部分からなり、自然科学系と人文科学系では記載方法がやや異なります。
自然科学系では、研究結果とその比較検討を含む、論文のカギとなる部分です。実験等を実施後に、実験ノートなどを参照しながら、過不足なく箇条書きで記載します。実際の実験データや、データを記載したグラフや表なども適切に掲載することが必要です。考察部分は、実験結果を記載したのちに分けて書きます。結果と考察ははっきりとわかるように記載します。実験結果の部分では類推が難しい内容を含む考察部分の記載は、さけるようにします。
人文科学系でも、主題を記載するのに必要なデータや図表がある場合もあります。この場合は、適切にその出展なども含めて記載しておくことが大切です。経済学のレポートなど、どのデータを使用するのか、それにより結論が違う場合もありうるからです。たとえば市場金利や賃金、失業率など、適切にデータを使用します。なお失業率などでも、国によっては実情を反映していない場合もあり、経済学分野などでは特に注意が必要です。
主題の中で、当該データに関する自身の解釈とその解釈に対する今後の方向性などに類する項目も併せて記載すればよいでしょう。
研究論文においては、序論部分では、研究背景や従来の研究の紹介を記載します。
技法的には、先行研究を網羅的に調べ、それらに批判を加えて新しい知見を付け加えることを目的としています。このため同じテーマを扱った先行研究などは、網羅的に調べ上げる必要があり、当然先行論文のアブストラクトだけではなく、全文を自身で講読しておくことが大切です。先行文献研究は、AI要約などでよいとする向きもありますが、これでは先行研究からのイノベーションは望めません。なにより同じような要約検討では、研究論文の序論としては適当ではありません。
序論部分についても、自然科学系と人文科学系の研究論文ではやや書き方が異なります。
自然科学系については、当該研究の背景や従来の研究の紹介を記載します。研究背景に必要なキーワードについても、できるだけ指定したり記載しておくようにします。さらには、実験方法についても述べておく必要があります。なお当該論文が、実験方法をともなわず、直接、実験結果を記載するようなショートレポートなど、記載しない場合もあります。このようなショートレポートでは、序論、本論、結論が端的に示されています。
人文科学系の序論については、本論の前の主題に関する解説などを記載します。当該論文の前提となるキーワード等についても、定義したり解説する必要があります。さらには、本論の背景となる命題部分を詳しく解説しておくことが大切です。
結論は、文献検索などでもよく使用される部分でもあり、過不足なくまとめることが大切です。
序論、本論で記載した事実、発見、考察を箇条書きで、論理性を保った状態で記載します。自然科学分野では、多数の論文を遅滞なく網羅検索する必要もあり、この結論部分が特に注目されています。研究背景や本論で記載した問題提起に対して、結論部分では、何を明らかにしたのかが明示されていなくてはなりません。また、今後の課題としてどのような問題が残されているのかなどのポイントも含まれます。
なお結論の記載方法については、論文の適用領域において慣例が異なっています。
自然科学分野では、英語ではSummaryといわれる部分とも一部重なります。序論、本論で記載した事実、発見、考察を箇条書きで、論理性を保った状態で記載します。自然科学分野では、多数の論文を遅滞なく網羅検索する必要もあり、この結論部分が特に注目されています。当然、結論部分の記載には、自身の研究に関連するキーワードなども含みます。検索はキーワード中心に実施されるからです。
人文科学分野では、最後に結論が記載されることが多いようです。この場合でも、必要なキーワードを含み、序論、本論で記載した事実、発見、考察を箇条書きで、論理性を保った状態で、箇条書きで結論を作成します。本論で記載した考察部分を深堀しておくことも必要でしょう。また単一の論文ではなく、自身の研究成果を次の論文でも発表する場合は、今後の展開にもつながるあらたな命題なども文章化しておくとよいでしょう。

それでは本論の書き方について、以下に紹介します。
レポートや論文の本論の前には、当然、その主題となるテーマが決まっていなければなりません。
とくに研究論文を作成する前には、当該の研究についてのあらたな課題、いわゆるリサーチクエスチョンを設定する必要があります。研究論文とは、創造活動の集大成でもあるわけですから、創造性のある新たな研究課題を準備しなければなりません。リサーチクエスチョンのよしあしが、その後の研究における方向性を左右することとなります。
参照先:「リサーチクエスチョンとは?その特徴・種類や作り方まで紹介」
リサーチクエスチョンは、科学研究においては重要な土台となるものです。
科学研究の発展に対して、適切なリサーチクエスチョンが大きく貢献してきたことは間違いありません。仮説とリサーチクエスチョンの両輪により、科学黎明期であるルネサンスの時代から継続して実施されてきており、現代でもその重要性は失われていません。研究課題の設定についても、十分に検討してから準備する必要があり、研究論文などの内容が特に重視される場合は、大切な視点となります。本年の国内ノーベル賞の受賞者が最近発表されましたが、生理学賞でも化学章でもイノベーションにつながる、研究の着眼点が注目を集めています。どの研究分野においても、本論の前に研究課題の設定が重要となります。
さらに本論を書くときの順序ですが、当該論文の主題を決めてから、できれば序論、本論、結論の順に書くことをおすすめします。さらには次に述べるように、全体構成とアウトラインを決めておいてから、本論を作成していくとよいでしょう。
本論に関する記事のなかには、本論を書いてから、序論を作成するというようなアドバイスもあるようです。ただ、これは当該論文の真のテーマが設定できていないときに、やむおえず取る手段ともいえます。真のテーマが設定されていないのに、やみくもに実施しても、主題の解決にはつながらないことになります。
レポートや論文を作成する場合に役立つのは、まず全体構成とアウトラインを決めることです。仮でもよいので、是非アウトラインを作成してから、本論を執筆するようにしましょう。
レポートや論文では、まずしっかりとした全体の構成があることが重要です。構成としては、いわゆる序論、本論、結論の基本的な3段階から構成され、本論の中の段落構成にも注意を払うことが大切です。
ライティングに取り組むときは、これらの段落構成に従って、この後で述べるパラグラフライティングを用いるようにします。是非、論文などのアウトライン構成をあらかじめ設定してから執筆に取り組むようにしましょう。アウトラインの書き方については、当方が本コラム内で紹介していますので、そちらを参考にしてください(下記)。
参照先:「研究論文のアウトラインとは?研究に役立つアウトラインの構成から書き方まで解説」
パラグラフライティングを使用することも、本論の執筆には有効な対策となります。
自然科学系の論文では、序論や、本論である実験方法、実験結果などについて、順をおって記載していきます。人文科学分野では、テーマとして、論文執筆前の問いに対して、著者の見解としての答えが記載されていればよい、とする考え方もありますが、自然科学分野の論文では、問いと答えの間の実験方法や実験結果が重要な要素となります。その中の段落であるパラグラフをふまえて記載していくことが大切です。
書かれた文章をより簡潔にわかりやすくするために、「パラグラフライティング」が推進されています。当方も米国に留学したとき、パラグラフライティングという技術に出会いました。日本では大学を卒業するまで、さらには企業に入っても、読み書きといえば、読むこと が中心であり、書き方を専門的に習得する機会はほとんどありませんでした。
しいていえば学習したわけではないですが、日本の大学での試験や大学院の入試などにおいて、この技術(パラグラフライティングという用語は知らないときですが)が有効であった覚えがあります。特に時間が限られてライティングする場合は、独学ではないですがかなり助けになりました。このようなライティング技術は、米国などでは高校からすでに習得しているようです。
なお蛇足ですが、これが最近の検索技術、グーグル検索などの開発にも影響している可能性もあります。当方も執筆業界で重宝されている、SEOライティングなるものを自己流で実践していますが、パラグラフライティングにそっくりともいえます。
最近は違うようですが、当方の時代では従来読むことや、暗記中心の教育が大学入学までは主体でした。適切なライティングに関する技術習得は、あとあとまで役に立つことになるので習得しておいて損はありません。

実際の本論に関しても、全体構成とアウトラインを作成しておくことや、パラグラフライティングについて留意するのは有効な対策です。科学系の論文などでは、本論部分の構成や内容は、従来から重要な課題となっています。
ここでは和文と英文の本論作成方法について検討するため、当方の修士論文と博士論文の構成例をとりあげて解説します。
和文の本論の例として、当方の研究論文(修士論文)をとりあげてみます。
(修士論文名:固定化プロテアーゼの調整とチーズ製造への利用)
まず序論部分に「本研究の目的とその背景」の記載があります。本論部分には、実験結果が含まれており、パラグラフライティングとして、いくつかの段落から構成されていることが特徴です(下記を参照)。
1. プロテアーゼの固定化
2. 固定化プロテアーゼの性質
3. 連続酵素反応における立ち上がり現象について
4. 反応器の連続酵素反応に対する影響
5. 固定化プロテアーゼによるチーズ製造
6. チーズ熟成に関する凝乳酵素と乳酸菌の寄与
6の段落は、固定化酵素(固定化プロテアーゼ)自体の研究とは異なっていますが、1~5までの段落(パラグラフ)は、すべて固定化酵素に関連する研究項目です。
記載内容の例として、各段落の部分の最初の内容を紹介します。
1.プロテアーゼの固定化
本研究では、酵素を固定化する方法として〇〇担体に吸着させたのち△△で架橋させる方法を採用した。固定化担体として用いた〇〇は、・・・
2.固定化プロテアーゼの性質
アルカリプロテアーゼおよびレンネット(凝乳酵素)の至適温度およびpHは、固定化によって変化しなかった。しかし所定の温度における固定化プロテアーゼの活性を37℃におけるそれを100として比較すると、高温(45~65℃)で著しく増加しアルカリプロテアーゼの場合、60℃での相対活性は200%をこえた。従って、溶液プロテアーゼに対する固定化プロテアーゼの熱変性に対する活性化エネルギーは数Kcalも増加したことになる。・・・
3.連続酵素反応における立ち上がり現象について
連続酵素反応中、活性が一時増加したのち減少し始めるという立ち上がり現象に関する実験的な解明を試みた。この結果、本固定化プロテアーゼのように担体として多孔質な樹脂を用いた場合、担体内部への基質の拡散効果が無視できないことが明らかとなった。・・・
4.反応器の連続酵素反応に対する影響
固定化酵素の担体粒径について、反応器の操作性との関係が調べられており、◇◇ら(46)によれば粒径が小さいものほど、固定化酵素を詰めたカラムの目詰まりがおこりやすい。本固定化酵素は通常よく用いられる多孔質ガラスビーズより、さらに粒径が大きい。・・・
(5および6は略)
完全なパラグラフライティングではないものの、段落パラグラフごとに記載するのはよく実施されています。また4の引用文献(46)のように、既存文献のデータと当該論文のデータを比較することも大切です。このように論文の本論に、必要不可欠な要素となっているのが、引用文献との照合です。
なお本論における、既存文献の引用方法については、下記の当コラムも参照してください。
今回紹介した当該の論文などを例にとって、文献の引用方法を詳しく解説しています。
参照先:「引用文献の書き方とは?その目的から引用方法や引用時のポイントまで解説」
英文の本論の例として、当方が作成した研究論文(博士論文)をとりあげてみます。
(博士論文名:PSYCHO-PHYSIOLOGICAL STUDIES ON BITTER TASTE SENSITIVITY)
この英文論文の本論には、研究結果の部分が含まれており、いくつかの段落から構成されています(下記を参照)。
1. Relationship between ingestion of and bitter taste responsiveness to caffeine
1.1. Caffeine taste thresholds in caffeine users and non-users
1.2. Relationship between caffeine ingestion and caffeine threshold
2. Effect of acute and chronic dosing on caffeine to bitter taste sensitivity
2.1. Detection of salivary caffeine in users and non-users of caffeinated products under free-living conditions
2.2. Effect of acute caffeine ingestion on taste sensitivity
2.3. Effect of chronic caffeine ingestion on taste sensitvity
3. Effect of consumption of bitter substances to bitter taste sensitivity and individual differences of taste sensitivity
4. Neuro-physiological analysis of bitter taste sensitivity in mice
以上の本論における、パラグラフ段落毎について、それぞれのまとめ部分(のみ)を参照してみます。
段落1. Relationship between ingestion of and bitter taste responsiveness to caffeine
As described in the Introduction, it has been proposed that functionally significant relationships exist between salivary constituents and gustatory perception of selected compounds.
The findings may be attributable to preexisting differences and self-selection among the caffeine user and non-user populations. Hence, differences in taste function might precede and contribute to the initiation and continued use of caffeine. Alternatively, intake and taste sensitivity may be manifestations of other characteristics of caffeine users and non-users, for example, level of arousal and extroversion (Rapport et al.,1984).
この段落では、ヒトにおけるカフェインユーザーとノンユーザーの味覚閾値の比較を調査しています。さらに、既存文献における他の生理学的データの比較結果も参照しています。
段落2. Effect of acute and chronic dosing on caffeine to bitter taste sensitivity
Salivary caffeine was detected in saliva of most caffeine users. In contrast, among non-users, only one subject showed salivary caffeine in one of the two testing sessions. Individuals who frequently consume caffeine in their saliva at almost all times. In this research, it was confirmed in most situations that the salivary caffeine level was lower than that the caffeine threshold (caffeine detection level) by 1 log order. Under such conditions, salivary caffeine is not expected to exert a significant influence on taste sensitivity at the threshold level.
Taken together, these data do not demonstrate a direct influence of dietary exposure to caffeine on taste. It is therefore suggested that the observed difference in gustatory function may not be causally related to caffeine use but perhaps reflective of some other individual (e.r. genetic, etc) or environmental characteristics associated with caffeine ingestion.
本段落では、段落1に続いてヒトにおけるカフェイン閾値をさらに詳細に検討したものとなります。カフェインの暴露による直接的効果ではなく、内在的な要因(遺伝的など)と環境要因(食事・飲用など)との相乗効果によるものではないかと推定されます。
段落3. Effect of consumption of bitter substances to bitter taste sensitivity and individual differences of taste sensitivity
Finally, the present data provide insights regarding the basic mechanism of bitter taste. The large number and diversity of compounds that taste bitter raise questions about the presence of unique receptors. While the existence of tasters and non-tasters for PTC is consistent with the involvement of a specific peripheral receptor or transduction mechanism, accumulating data indicate that a non-specific peripheral receptor or transduction mechanism, accumulating data indicate that a non-specific receptor mechanism may be involved (Teeter and Brand, 1987). In the present study, detection thresholds were determined for six bitter compounds and correlations were noted between only two of fifteen possible comparisons. This low order of association across compounds is not consistent with the existence of a single receptor and transduction process.
本段落では、カフェインを含む、苦味物質6種類について、ヒトにおける反応性を調べた部分となります。既存文献(Teeter and Brand, 1987)と本研究のデータとを比較して解析している段落となっています。このように学術論文では、とくに既存の引用文献のデータを参照して、比較することがよく実施されています。
段落4. Neuro-physiological analysis of bitter taste sensitivity in mice
The difference in taste sensitivity of the GL nerve in mice strains is hypothesized to be largely determined by genetic factors. The neural reaction level of the BALB/C strain to caffeine and iso-alpha-acids is significantly higher than that of C57BL strain (p<0.05, in Fig.25). And・・・
やや専門的になりすぎるので、And以下は省略しますが、本段落では、マウスの味覚神経を使用して、苦味物質への反応性を調べている段落になります。GL nerveとは、鼓索神経系と呼ばれる味覚神経のひとつです。また BALB/CとC57BLは、両方ともマウスのストレイン(遺伝学的系統)であり、後者が従来からの野生系統です。
BALB/CとC57BLの味覚閾値を比較すると、前者が後者に対して有意差を持って高くなっています(すなわち、逆に後者の方が味覚感受性が高くなっている)。
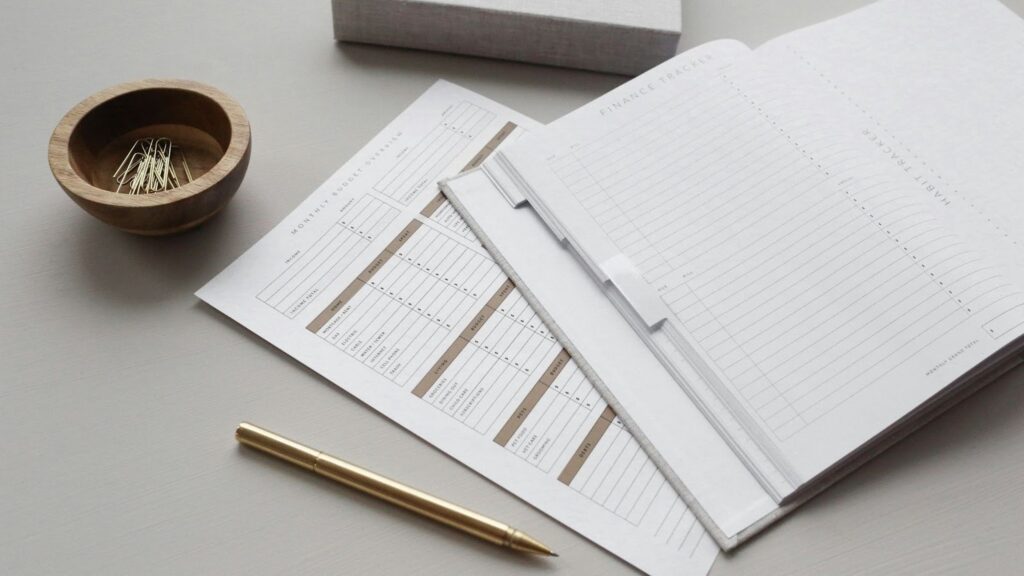
本論を書く時の注意点としては、まず信頼できるデータを記載することが重要です。さらには、既存文献を含めて分析・考察することも有効となります。
本論を書く時には、信頼できるデータとして、研究により得られた実験結果やさらにはその結果を裏付ける文献なども記載するようにします。
さらに研究結果について、できるだけ客観的な評価や考察をおこないます。本研究によって、どのような有効性が確かめられたか、 関連研究と比較してどのようなメリットがあるかなどの解説もつけます。またもし実験や解析などがうまくいかなかったときは、その内容をありのままに記載し、さらに自身の研究でいたらなかった点などにもふれて、問題点を明確にしておくことが必要です。
論文の本論では、事実を裏付けるデータや証拠などに基づいています。すなわち、科学実験であればそれなりの科学研究に必須とされる実験方法や観測方法、さらには得られたデータの統計的処理などが、すべて科学的に実証されるものでなければなりません。大学内の研究などでは、たとえば学部学生の実験研究でも、それなりの実験データが必要です。
本論を書くときは、自身が提示する情報に、適切な証拠を加味して論じていくことになります。ただ説明するだけの文章ではなく、書かれている内容について、情報を分析し評価することが必要です。
このため自身で自ら判断し、文章の中でどのように扱っていくかを考えなくてはいけません。提示すべき情報を深く理解していることが必要で、十分なリサーチをすることが求められます。また序論の段階で、本論の主題の背景を深堀しておくことも大切です。
人文科学系でも、主題を記載するのに必要なデータや図表がある場合もあります。この場合は、適切にその出展なども含めて記載しておくことが大切です。経済学の論文など、どのデータを使用するのか、それにより結論が違う場合もありうるからです。
たとえば市場金利や賃金、失業率など、適切にデータを使用します。なお失業率などでも、国によってはその実情を十分に反映していない場合もあり、経済学分野などでは特に注意が必要です。さらにこの中で、当該データに関する自身の解釈と、その解釈に対する今後の方向性なども併せて記載すればよいでしょう。
本論を書く時の注意点としては、既存文献を含めて分析・考察することも大切です。
既存文献との比較により、本論での主題の妥当性が明確となり、さらには自身のオリジナリティがどこにあるか主張することができるようになります。本論では、単に主張することではなく、なぜそういう主張になるのか証明することが求められます。このような作業には、既存文献との比較プロセスが必要不可欠です。
既存文献の記載にあたっては、自身と他者の研究成果の区別をすることも欠かせません。文献の記載とは、他者の著作物、ときには他者が作成した既存論文における文章や図表を、自身の論文のなかで用いることです。
また記載をするときには、どの論文から引用してきたのか、その出典を明示しなければなりません。他者の著作物に書かれていることを、自身の論文の中でそのまま使用する場合だけでなく、既存論文が提示している考え方や理論や、さらにはその論文中で掲載されている図表などのデータを用いる場合も同様ですが、このような場合は、参考文献というより「引用文献」ともいえるものです。
自他の成果を区別するとは、他者の研究に敬意を払うためです。このため自身の論文が出版後に、どの読者でもどこまでが既存研究で、どこからが新たな研究成果なのか明確にわかるようにしなければなりません。このためにいろいろな引用ルールが慣習法として、従来から設定されているのです。なお学術雑誌では、特に論文の「投稿規定」として、引用ルールを細かく記載している場合もあります。
本論について、論文などを例にとって、その特徴や書き方から注意点まで解説しました。
本論とは、レポートや論文を作成する場合にその核となる部分であり、一番重要な部分です。研究論文の場合、本論は自身の研究の内容について述べる核心部分となります。
序論の研究背景で判明した、従来の研究からみえてきた問題や、自身が提起するあたらしい主題について、既存文献をまじえて解明していくことが大切です。
「研究論文とは、創造活動の集大成でもあるわけですから、創造性のある新たな研究課題を準備しなければなりません。リサーチクエスチョンのよしあしが、その後の研究における方向性を左右することとなります。」
と記事内でも記載させて頂きましたが、この究極の例がノーベル賞級の研究ともいえます。
本年のノーベル賞では、久しぶりに生理学賞と化学賞のふたつの部門での受賞者がありました。ふたりの先生ともに、基礎研究の重要性を指摘されており、イノベーションの大切さを強調されています。本論である主題を長年かけて追及していく態度には、おふたりとも共通する姿勢があります。最初は論文公開や学会発表時に、既存文献などが少なく非常に苦労されたようですが、主題をあきらめることなく、とことん追及されています。
京都大学ではないですが、当方もある国立大学にて、化学賞の主題である金属有機構造体MOFを使用した医薬分野での特許申請を支援した経験があります。とくに自己組織化現象は、化学分野のみならず、細胞内などのバイオ分野でも重要な現象であり、ある種の構造体の形成原理でもあります。
本記事が、研究論文などの作成にこれから取り組むみなさまのお役に少しでも立てば幸いです。

研究や論文執筆にはたくさんの英語論文を読む必要がありますが、英語の苦手な方にとっては大変な作業ですよね。
そんな時に役立つのが、PDFをそのまま翻訳してくれるサービス「Readable」です。
Readableは、PDFのレイアウトを崩さずに翻訳することができるので、図表や数式も見やすいまま理解することができます。
翻訳スピードも速く、約30秒でファイルの翻訳が完了。しかも、翻訳前と翻訳後のファイルを並べて表示できるので、英語の表現と日本語訳を比較しながら読み進められます。
「専門外の論文を読むのに便利」「文章の多い論文を読む際に重宝している」と、研究者や学生から高い評価を得ています。
Readableを使えば、英語論文読みのハードルが下がり、研究効率が格段にアップ。今なら1週間の無料トライアルを実施中です。 研究に役立つReadableを、ぜひ一度お試しください!
Readable公式ページから無料で試してみる
都内国立大学にて、研究・産学連携コーディネーターを9年間にわたり担当。
大学の知財関連の研究支援を担当し、特にバイオ関連技術(有機化学から微生物、植物、バイオ医薬品など広範囲に担当)について、国内外多数の特許出願を支援した。大学の先生や関連企業によりそった研究評価をモットーとして、研究計画の構成から始まり、研究論文や公募研究への展開などを担当した。また日本医療研究開発機構AMEDや科学技術振興機構JSTやNEDOなどの各種大型公募研究を獲得している。
名古屋大学大学院(食品工業化学専攻)終了後、大手食品メーカーにて31年間勤務した経験もあり、自身の専門範囲である発酵・培養技術において、国家資格の技術士(生物工学)資格を取得している。国産初の大規模バイオエタノール工場の基本設計などの経験もあり、バイオ分野の研究・技術開発を得意としている。
学位・資格
博士(生物科学):筑波大学にて1994年取得
技術士(生物工学部門);1996年取得