
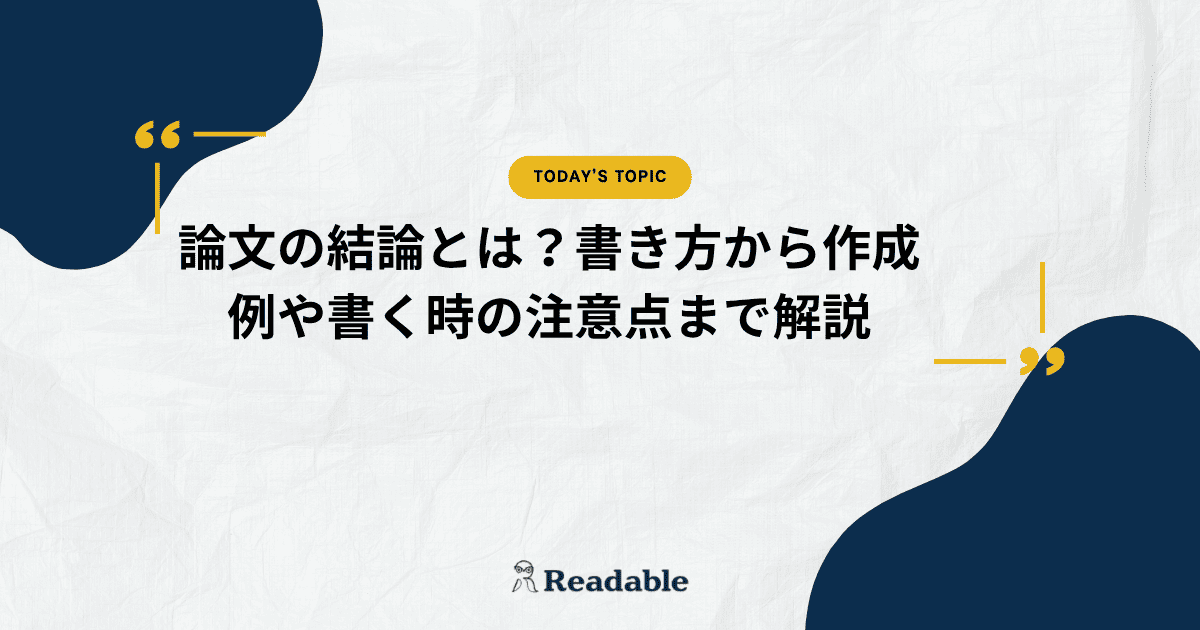
論文の結論とは、自身の研究成果を公表する上で欠かせない部分です。
論文を作成することは、研究をはじめて間もない研究者にとっては重要な作業といえます。また経験豊富な研究者にとっても、研究の完成には、論文作成自体が欠かせません。このように大切な論文において、その結論はどのように書いたらよいでしょうか。
本記事では、論文の結論の書き方について、その作成方法や作成例に加えて注意すべき点についても紹介します。

研究成果を公開するための論文の結論とはどのように書いたらよいでしょうか。
研究者にとっては、論文作成により、その研究を広く公開して認めてもらうことができます。研究開始して間もないときほど、自身の成果が掲載された学術雑誌をみることは研究者にとっても大切な瞬間です。このような論文の中で、結論は、その論文の内容を簡潔に示すとともに、執筆者の想いを載せた部分ともなりえます。
論文の結論とは、当該論文の概要を過不足なくまとめたものです。
自身の研究により得られた成果を、過不足なく簡潔に示されていることが大切です。
結論は、論文の内容全体をコンパクト化したものですので、キーワードや専門用語も必要十分な程度は、ふくまれていなければなりません。
わかりやすい用語とすることもときに推奨されていますが、学術雑誌では、当該分野の専門用語は、必ず使用されています。実験結果の一部を結論でも再度記載する場合は、専門用語は必然的に使用されることになります。
研究論文の構成は、大まかにわけると、目的、対象と方法、結果、考察、要約、謝辞・文献などの部分から成っています。このうち考察と要約部分が、当該論文の結論ということになります。
考察を含む結論部分は、論文で自身の考えも記載できる一番重要な部分です。自身の研究目的がどのように達成できたのか、具体的に説明します。執筆前には、記載したい考察結果を明確にしておき、箇条書きで記載しておくととくに役にたちます。実際の論文執筆時には、この箇条書きをみながら執筆していきます。要旨とも関連する部分もありますが、自身の論文テーマとの関連から考察し、文章にまとめることが必要です。
論文の結論の記載については、当該論文の適用領域でやや異なります。
自然科学領域では、英語ではSummaryといわれる部分とも一部は重なります。論文の本論で記載した実験結果やその考察を箇条書きで、論理性を保った状態で記載します。自然科学では、自身の研究の有用性を主張するためにも、多数の論文をもれなく検索する必要があります。このため結論部分の記載には、当該研究に関連する専門用語やキーワードなどが含まれていなければなりません。
人文科学領域でも、必要なキーワードを含み、本論で記載した事実やその考察を箇条書きで、論理性を保った状態で結論を作成します。本論で記載した考察部分を深堀しておくことも必要となります。
研究背景や本論で記載した問題提起に対して、結論部分では、何を明らかにしたのかが明示されていなくてはなりません。また、今後の課題としてどのような問題が残されているのかなどのポイントも含まれます。自然科学領域でも同じですが、単一の論文ではなく、今後も研究成果を連続して公開する場合があります。このような場合は、今後の展開にもつながるあらたな命題なども文章化しておくとよいでしょう。
論文作成には、結論以外にも要旨Abstractをまとめとして作成します。
要旨では、結論部分の内容を簡潔に記載しておく必要があります。当該論文が研究手法、とくに実験方法などでも有用性を主張する場合は、実験方法の一部を含むときもあります。とくに当該の実験方法が、当該分野で注目される手法である場合はなおさらです。このため実験に関する専門用語やキーワードも、必要十分な条件で含まれている必要があります。
また要旨は、文献検索などでもよく使用される部分でもあり、過不足なくまとめることが大切です。
自然科学系の学術雑誌では、要旨がタイトルの直下にある場合が多数あります。要旨をまず読んでから、それ以外の部分を読む必要があるか判断する場合が多いため、とくに重要箇所となります。
なお要旨の書き方には、構造化要旨と非構造化要旨のふたつがあります。
構造化要旨では、論文の背景、目的、実験方法、実験結果や結論などにわけて
その内容を記載します。背景では、研究背景を簡潔に記載し、目的は当該研究が目指すところなどを含めて、各段階とも、論文内容を丁寧に、いわゆる必要十分な程度に記載していきます。
非構造化要旨では、そのような区分は行わず、同じ段落の中で記載していきます。そのため構成が難しくなる場合もありますが、メリットもあります。先ほども記載したように、論文が実験方法の開発に力点を置く場合は、その部分を幅広く書いていきます。逆に実験方法が既存の論文と同様なら、最小限で方法を記載し、実験結果の部分に力点をおくことができます。
学会誌などの場合、要旨に代わり、抄録を記載するという場合もありますが、基本的には同様なものです。両者とも、論文内容において主要な点をまとめて作成します。英語では、両方ともにabstractと記載されることが多いようです。

次に論文の結論部分の書き方において、書く順序や記載する専門用語などについても解説します。
論文全体の内容をまとめたものが結論となるので、論文の本論の完成後にそれをまとめます。
研究論文は、主に研究タイトル、研究背景からなる序論、研究方法や研究結果からなる本論、さらに考察や要約からなる結論と、最後の謝辞・文献から成っています。このため、論文の序論や本論を完成させてから、結論部分を記載します。
なお結論部分を含む、研究論文全体を作成する場合には、作成の際の設計図ともなる、研究論文のアウトラインを作成しておくことをおすすめします。論文アウトラインについては、「仮タイトル⇒ 序文⇒ 実験方法⇒ 実験結果⇒ 考察⇒ 要旨」の順に、作成します。また実験方法や実験結果があれば、すぐ執筆開始できると思われがちですが、段階をふんで準備して行く方が完成度が高く、研究論文の質も高くなります。いきなり論文本文の作成を始めると、完成した論文が本人が最初意図していたものと異なる可能性もあります。アウトライン作成などの準備作業が終了すれば、論文本文の作成にとりかかります。
なお結論部分は、まず箇条書きで整理しておき、結論執筆後に再度検討や修正して完成させるのがよいでしょう。論文全体のまとめとなる部分であり、研究中に疑問に思った課題などに対して、自身の考えも記載します。序論や本論で記載した問題提起に対して、当該研究で何を明らかにしたのか、今後の課題としてどのような問題が残されているのかなどの研究課題のポイントも含みます。
論文の結論部分の書き方において、提出先の作成規定を参照することも大切です。
たとえば研究論文を投稿する学術雑誌の「投稿要領」も執筆前に確認しておき、問題ないようにしておくことが大切です。結論部分の内容や要約の方法、さらには文字数などが細かく規定されているときもあります。先ほど学術雑誌の要旨について記載しましたが、結論も同様に、当該雑誌の規定によって作成されます。場合によっては、要旨の文字数なども決められている場合があり、投稿規定を参照の上、要旨も作成する必要があります。
自然科学系論文のみならず、人文科学系の論文でもあらかじめ作成規定を把握しておき、それに沿って執筆することが大切です。大学などの授業で作成するような論文でも、学部によっては、文字数や要約スタイルが指定されていることもあります。
結論部分は、研究論文の中でも重視されている部分ですので、書き方をマスターしておくと、今後の研究活動にも役立ちます。結論を読めば、何を研究したのかがわかるように書くのがポイントですが、具体的にどういう問題について、どのような研究を行って、結果的にどのような結論が得られたかということが明確にわかることが大切です。
論文の結論では、正確な情報や専門用語を、適切に過不足なく使用するようにします。
たとえば実験方法などの方法論は、脇役の感じもある個所かと思いますが、自然科学系では非常に重要な箇所で、これをおろそかにした論文は成り立ちません。場合によって、実験方法が異なると、別の結果がでてしまう可能性もかなりあり、実験方法の開発自体が研究課題となっている分野も存在します。宇宙物理などの分野では、実験方法である観測系の設定・確立自体が、大切な課題です。
このような場合は、結論部分にも、それ相応の専門的な手法に関する記載は必須となります。既に開発済みの実験手法を用いる場合は、既存文献を参照することとして引用しますが、それでも重要な手法は、結論にも記載しなければなりません。
自然科学系の研究では、実験方法の開発が鍵となった例は数多くあり、論文の結論部分でも、正確な情報や専門用語による解説が必要です。専門用語は、当該分野の研究者なら容易に理解しやすい用語でもあり、自身が作成した研究論文の理解の醸成にもつながります。このような研究者間での研究課題の相互推進が、当該分野のサイエンスの発展に寄与しているといえます。

ここでは論文の結論部分の作成例について、和文として修士論文、さらに英文として博士論文を例にとって説明します。
和文の結論の例として、当方の研究論文(修士論文)をとりあげ下記に記載します。
(修士論文名:固定化プロテアーゼの調整とチーズ製造への利用)
まず本論部分は、以下の6つの段落(パラグラフ)から構成されています。
1. プロテアーゼの固定化
2. 固定化プロテアーゼの性質
3. 連続酵素反応における立ち上がり現象について
4. 反応器の連続酵素反応に対する影響
5. 固定化プロテアーゼによるチーズ製造
6. チーズ熟成に関する凝乳酵素と乳酸菌の寄与
本論の6つの段落内容にもとづいて、結論部分が作成されています(下記括弧部分)。
「本研究は、凝乳作用を有するプロテアーゼを固定化し、それをチーズ製造に利用することを目的として行ったものである。」
として、本研究(修士論文研究)の本論のあとに紹介しています。さらに続けて、
「本研究の目的に適するプロテアーゼとしては、市販の各種起源のプロテアーゼについて検討した結果、〇〇起源のアルカリプロテアーゼを選定した。・・・
・・・
次に以上のような諸結果をふまえて、固定化プロテアーゼを用いる新しいチーズ製造方法を考案した。・・・これに対して、固定化アルカリプロテアーゼを用いて作ったチーズでは、水分量が若干多く、組織の粘着性がやや不足しているようであったが、熟成度は通常のチーズと、ほとんど差がなかった。また、生菌数や酸度に関しても、固定化アルカリプロテアーゼチーズと通常のチーズの間には、著しい差はなかった。
従って以上の研究により、高価で入手の困難なレンネットに代え、安価で入手の容易な微生物起源のプロテアーゼを用い、しかもこれを固定化酵素の形で使うことにより、連続的な凝乳処理をおこなって、チーズを製造することが、かなりの程度可能となったと考える。」
なおプロテアーゼは酵素のひとつですが、このようなキーワードに類する専門用語も適切に使用することが大切です。
本研究では、酵素を固定化して利用する「固定化酵素」もキーワードとして重要な範疇となっています。なお固定化酵素、固定化プロテアーゼ、固定化アルカリプロテアーゼが意味するところの範囲の程度は、以下のような順番となります。
固定化酵素> 固定化プロテアーゼ> 固定化アルカリプロテアーゼ
固定化アルカリプロテアーゼが、意味する領域としては一番狭いことになり、本研究でとくに検討された固定化酵素のひとつです。
以上のように当該研究の本論をふまえて、本研究の結論部分が作成されています。なお「本論」の書き方については、以下の記事も参照してください。次の英文の結論例についても、本論部分を参考にされたいときは、同様にご参照頂けます。
参照先:「本論とは?その特徴や書き方から注意点まで解説」
次に、英文の結論の例としては、当方が作成した研究論文(博士論文)をとりあげます。
(博士論文名:PSYCHO-PHYSIOLOGICAL STUDIES ON BITTER TASTE SENSITIVITY/
苦味感受性に関する心理生理学的研究)
本論部分は、以下の4つの主段落(パラグラフ)から構成されています。
1. Relationship between ingestion of and bitter taste responsiveness to caffeine
1.1. Caffeine taste thresholds in caffeine users and non-users
1.2. Relationship between caffeine ingestion and caffeine threshold
2. Effect of acute and chronic dosing on caffeine to bitter taste sensitivity
2.1. Detection of salivary caffeine in users and non-users of caffeinated products under free-living conditions
2.2. Effect of acute caffeine ingestion on taste sensitivity
2.3. Effect of chronic caffeine ingestion on taste sensitvity
3. Effect of consumption of bitter substances to bitter taste sensitivity and individual differences of taste sensitivity
4. Neuro-physiological analysis of bitter taste sensitivity in mice
本論の各パラグラフに対して、本研究の結論記載部では、以下のように始めています。
The role of taste sensitivity in guiding the selection and ingestion of foods is poorly characterized in humans. This is especially true for bitter taste.
In this thesis the author proposed that taste sensitivity to bitter food constituents exerts a significant influence on food selection, because of the intrinsic warning message the taste can note in humans. ・・・
と続いており、研究の本論部分のまとめから紹介する部分です。
さらに最後の部分では、以下のように本研究をまとめています。
From these results, it is concluded that‘bitter taste sensitivity’ controls ‘intake of bitter substances’(Fig. 〇〇). Subjects that have low sensitivity to
Bitter substances (caffeine in this case) mostly depend to be heavy user (of coffee, et al.). Low sensitive subjects have developed the preference of bitterness during their lives. On the other hand, highly sensitive subjects to bitter substances must be non or light user of bitter substances. So, it is considered as follows;
In mammals including humans, genetic factor mainly determines the status of individual sensitivity to bitter substances. Insensitive subjects can develop the intake of specific substances (specificity to bitter substances is determined by inner factor) in his life. To contrast, sensitive subjects reject the intake of bitter food. Even though they are forced to take bitter substances, their sensitivity is not decreased, but rather maintained to constant.
結論にある‘bitter taste sensitivity’苦味感受性は、研究タイトルの中にもあるようにキーとなる専門用語となっています。心理生理学的研究は、日本ではあまり注目されていませんが、米国では従来から研究が盛んな分野です(米国ではこのような実験心理学的手法が、単に基礎的研究ばかりではなく、各種商品開発にも応用されています)。
だいぶ昔にはなりますが、米国の当該研究所に企業から留学したとき、心理学出身者による生理学的実験研究がかなりの部分を占めていたので、びっくりした経験があります。米国の大学には「心理学部」を持つところが多く、ハーバード大学やカリフォルニア大学などは実験心理学なども盛んで、学部間の連携を重視する学際的研究に注力しています(当方の博士論文課題も学際分野となります)。臨床心理分野が大半の国内大学とはかなり異なっており、米国産業界にはその当時多くの出身者が進出していました。たとえば米国の食品系企業の研究所などは、その当時すでに心理学出身者が大半を占めています。一度関連のセミナーに出席したとき、10名中8名が心理学部出身の女性で、当方を含む残り2名が男性でそれ以外の学部出身者でした(その1名は、食品企業ではなくタバコ会社研究所所属)。
東京大学でも2027年秋に、文理融合で学際的分野をまなぶカレッジ・オブ・デザインという新課程をはじめるとアナウンスされています。ようやく国内でも融合領域の重要性が理解されてきたようです。

結論を書く時に注意すべき点として、キーワードやパラグラフライティングの使用などがあげられます。
論文の結論には、いわゆるキーワードをいれるようにします。先ほど専門用語の記載の重要性を紹介しましたが、キーワードも同様で、専門用語以上に大切です。また当該分野特有の用語もあり、これらを使用することにより、論文の理解が進むという効果も期待できます。
先ほどの和文の結論例では、固定化酵素に関するキーワードが取り入れられています。最近は、固定化酵素に関する研究も下火ですが、その当時はかなり注目された研究分野でした。修士論文自体が注目されることは少ないですが、当該論文の内容の一部は、その後、指導教官によってバイオテクノロジー関連の学術雑誌に投稿されています(当方もセカンドオーサーとして、当該論文にも記載されています)。
固定化酵素、固定化プロテアーゼは、その当時のキーワードですが、最終的に使用した固定化アルカリプロテアーゼ(当該研究で使用)もキーワードに類するものです。
論文掲載後、他の研究者からの検索時には、結論の内容が参照されることになります。他の研究者が使用する検索において、自身の論文が正しく把握されるためにはキーワードの選定にも十分注意します。
論文の結論の記載には、パラグラフライティングを使用することも有効な対策です。
自然科学系の論文では、序論や、本論である実験方法、実験結果、考察などについて、順をおって記載していきます。とくに研究論文では、問いと答えの間の実験方法や実験結果が重要な要素となります。その段落であるパラグラフをふまえて記載していくことが大切です。
先ほどの和文の結論例をみると、1~6までの段落(パラグラフ)が当該修士論文の本論を構成しています。この本論の段落ごとに、まとめを記載したものが、当該論文の「結論」です。
博士論文による英文の結論例でも、4つの主段落(パラグラフ)から構成された本論に対応しています。これらの主段落の研究内容とアピールすべきポイントが結論にも記載されているといえます。
論文全体もそうですが、論文の結論部分は、作成後かならず、専門家や第3者などにチェックしてもらうようにします。
まだ研究開始して間もない場合は、同じ研究室の専門家などにみてもらうことが大切です。専門用語やキーワードなどにくわえて、当該分野で多用されている表現なども教えてもらうと大変役立ちます。論文作成開始時点から、所属研究室での支援を受けている場合も多いですが、とくに結論の記載には細心の注意を払うようにします。
研究論文の結論部分や要旨は、他の研究者からもよく引用される重要な部分です。他の研究者へのアピールとなるだけでなく、自身の研究成果を主張する大切な部分であり、キーワードを含めて、その詳細が十分に網羅されている必要があります。
論文での結論の書き方に関して、作成方法や作成例に加えて注意すべき点について解説しました。
論文の結論とは、自身の研究成果を公表する上で欠かせない部分です。その研究を広く認めてもらうためには、論文の本論のみならず、結論の細部にも注意を払うことが必要です。とくに研究をはじめて間もない研究者にとっては重要な作業といえます。
本記事が、論文の結論について今後検討を予定している方々のお役に立てば幸いです。

研究や論文執筆にはたくさんの英語論文を読む必要がありますが、英語の苦手な方にとっては大変な作業ですよね。
そんな時に役立つのが、PDFをそのまま翻訳してくれるサービス「Readable」です。
Readableは、PDFのレイアウトを崩さずに翻訳することができるので、図表や数式も見やすいまま理解することができます。
翻訳スピードも速く、約30秒でファイルの翻訳が完了。しかも、翻訳前と翻訳後のファイルを並べて表示できるので、英語の表現と日本語訳を比較しながら読み進められます。
「専門外の論文を読むのに便利」「文章の多い論文を読む際に重宝している」と、研究者や学生から高い評価を得ています。
Readableを使えば、英語論文読みのハードルが下がり、研究効率が格段にアップ。今なら1週間の無料トライアルを実施中です。 研究に役立つReadableを、ぜひ一度お試しください!
Readable公式ページから無料で試してみる
都内国立大学にて、研究・産学連携コーディネーターを9年間にわたり担当。
大学の知財関連の研究支援を担当し、特にバイオ関連技術(有機化学から微生物、植物、バイオ医薬品など広範囲に担当)について、国内外多数の特許出願を支援した。大学の先生や関連企業によりそった研究評価をモットーとして、研究計画の構成から始まり、研究論文や公募研究への展開などを担当した。また日本医療研究開発機構AMEDや科学技術振興機構JSTやNEDOなどの各種大型公募研究を獲得している。
名古屋大学大学院(食品工業化学専攻)終了後、大手食品メーカーにて31年間勤務した経験もあり、自身の専門範囲である発酵・培養技術において、国家資格の技術士(生物工学)資格を取得している。国産初の大規模バイオエタノール工場の基本設計などの経験もあり、バイオ分野の研究・技術開発を得意としている。
学位・資格
博士(生物科学):筑波大学にて1994年取得
技術士(生物工学部門);1996年取得